解決できるソリューション
Products 製品一覧

- 統合型IT運用管理AssetView
-
IT資産管理をはじめとする
企業が抱えるセキュリティ課題をまとめて解決。
お客様のニーズに合わせて、運用提案をする
それがAssetViewです。
Case 導入事例
-

- 株式会社Looop様
-
Looopが統合型IT運用管理「AssetView CLOUD」を導入
業種:サービス
台数:300~999台
-
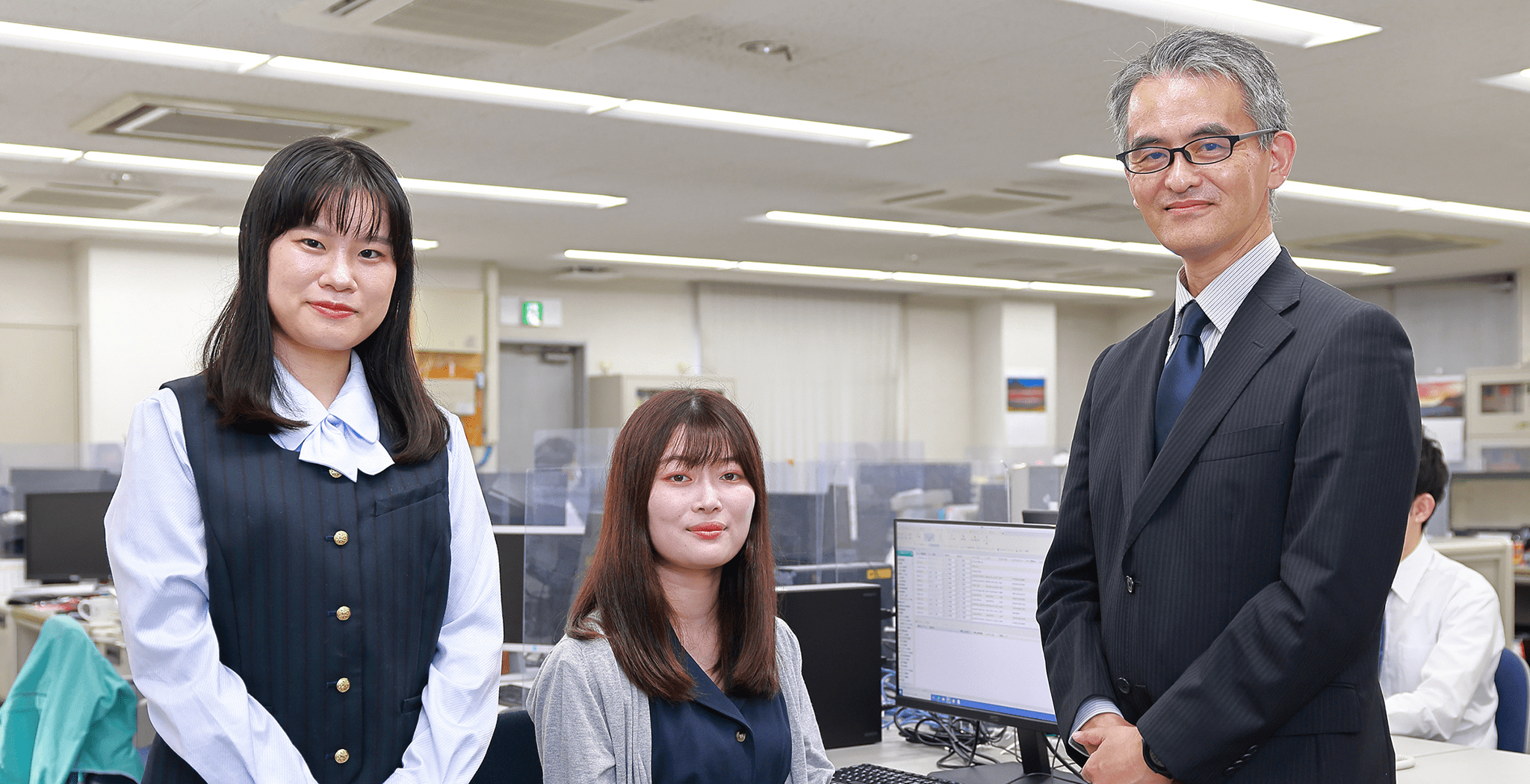
- ミドリ安全株式会社様
-
「安全」をつくる会社のセキュリティ 若手情シスチームがAssetViewと共に実現
業種:製造
台数:1000台~
-

- 株式会社日比谷花壇様
-
花き業界のリーディングカンパニー、日比谷花壇が統合型IT運用管理「AssetView CLOUD」を導入
業種:小売・卸売
台数:1000台~
-

- 株式会社ガモウ様
-
情シスの業務効率化、セキュリティ向上に貢献。業界トップの総合美容商社を支えるAssetView
業種:小売・卸売
台数:300~999台
-

- 株式会社データセレクト様
-
データセレクトが統合型IT運用管理「AssetView」を導入
業種:サービス
台数:300~999台
-

- 株式会社東武ホテルマネジメント様
-
AssetViewオンプレミスからAssetViewCLOUDへ。サーバーレスによる省力化・若手職員がはたらきやすい職場環境に
業種:サービス
台数:300~999台
-

- 株式会社コプロ・ホールディングス様
-
コプロ・ホールディングスが統合型IT運用管理「AssetView CLOUD」を導入
業種:サービス
台数:300~999台
-

- ニッポンレンタカーサービス株式会社様
-
ニッポンレンタカーが統合型IT運用管理「AssetView CLOUD」を導入
業種:サービス
台数:1000台~
-

- タツタ電線株式会社様
-
必要な時に必要な機能を追加導入。中堅電線メーカーの業務効率・セキュリティに貢献するAssetView
業種:製造
台数:1000台~
業種・規模問わず様々な企業様に
ご導入いただいております
ご導入いただいております




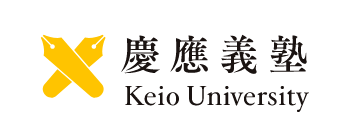

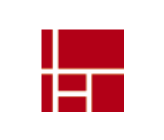





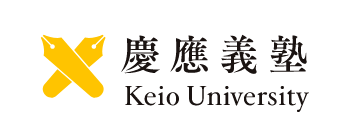

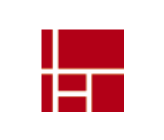

- 今後もお客様からいただいたご要望をもとに、サービス向上・機能強化に努め、お客様のIT資産管理やセキュリティ強化をご支援してまいります。

- すぐにダウンロードできます! 今すぐ資料ダウンロード
- AssetViewを詳しく知る! セミナー申し込み
お電話でのお問い合わせも受付中
平日9:00〜12:00 | 13:00〜17:00(休業日を除く)
※お問い合わせの際は【企業名・氏名・製品名】をお伝えください。
※お問い合わせの際は【企業名・氏名・製品名】をお伝えください。
0120-922-786
携帯電話からは03-5291-6121
最短1分で問い合わせ完了! お問い合わせはこちら


