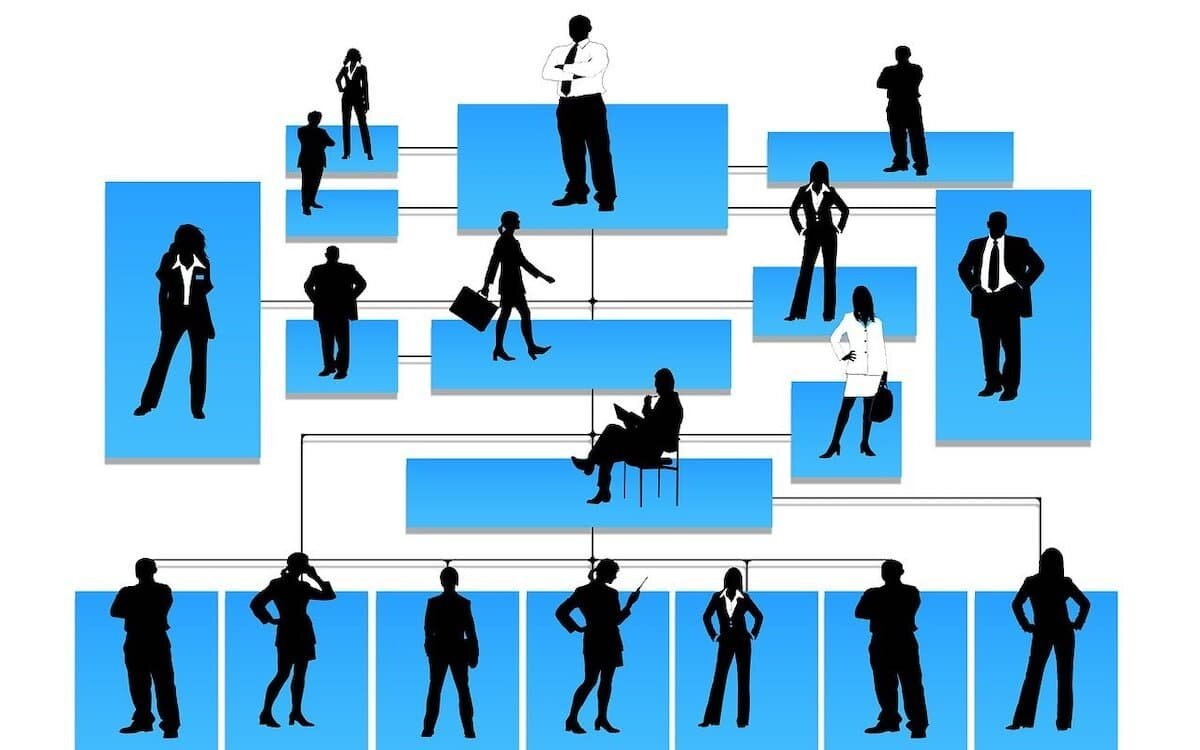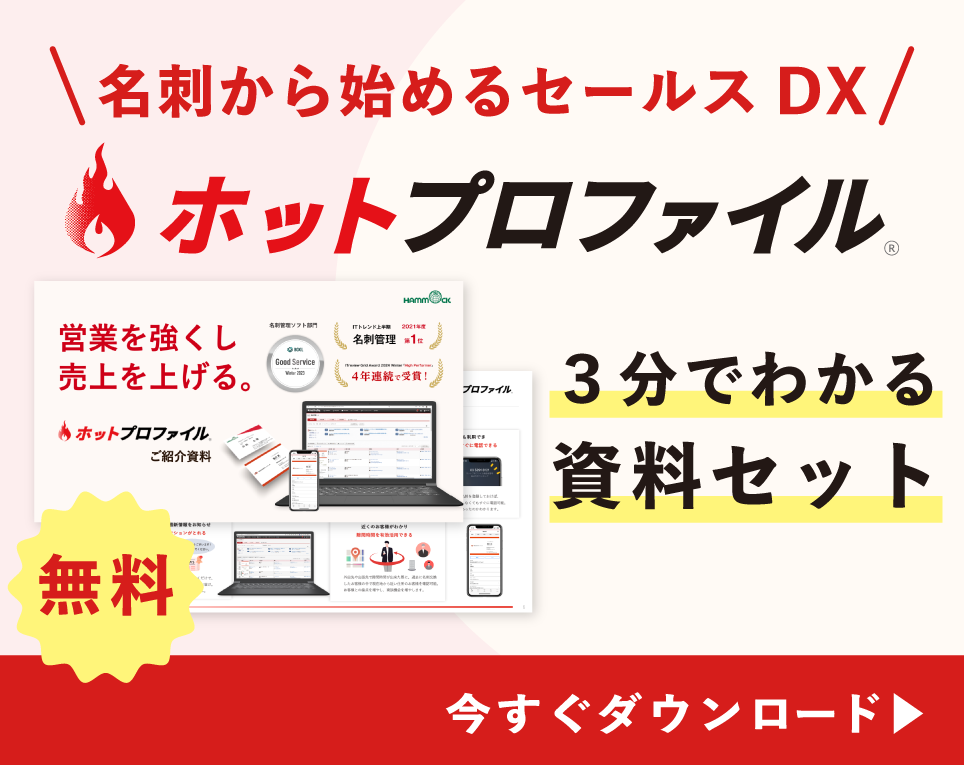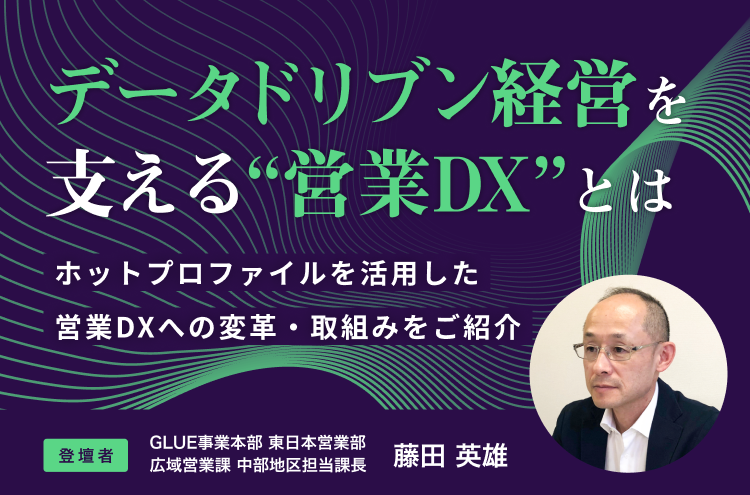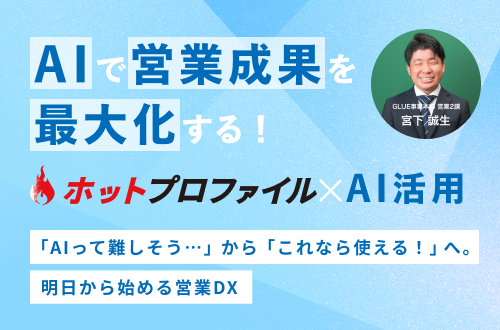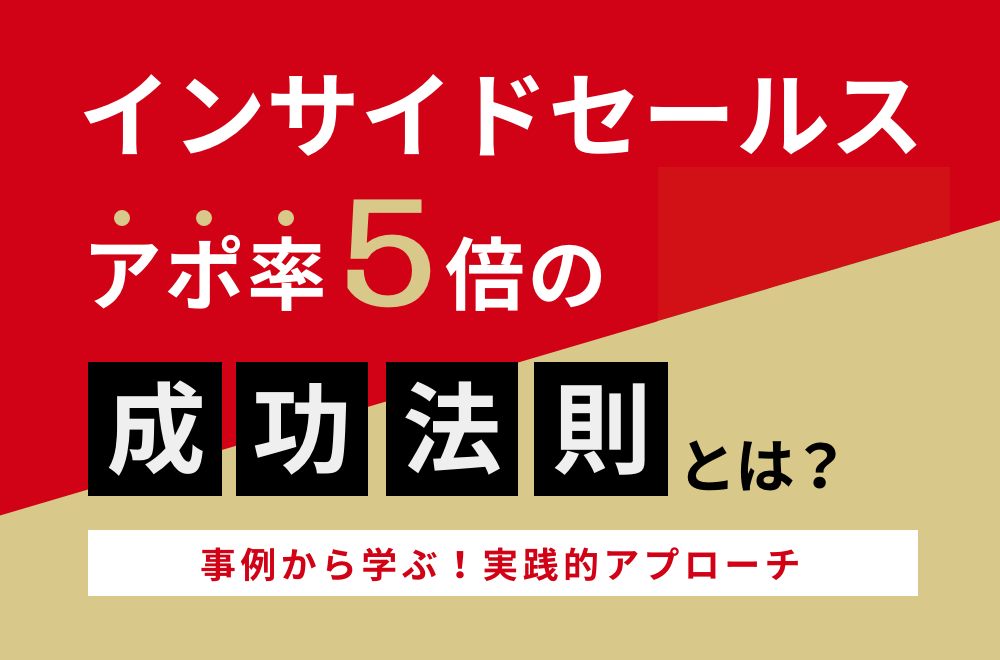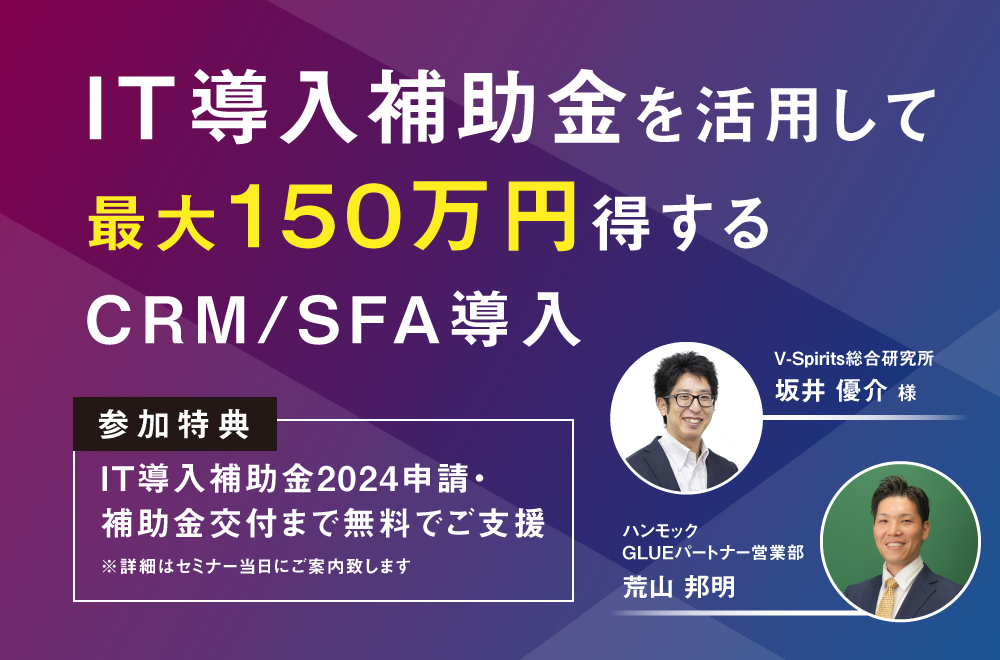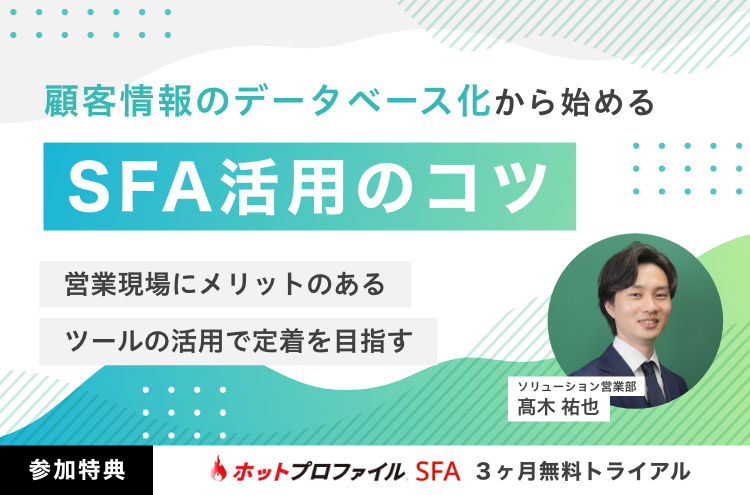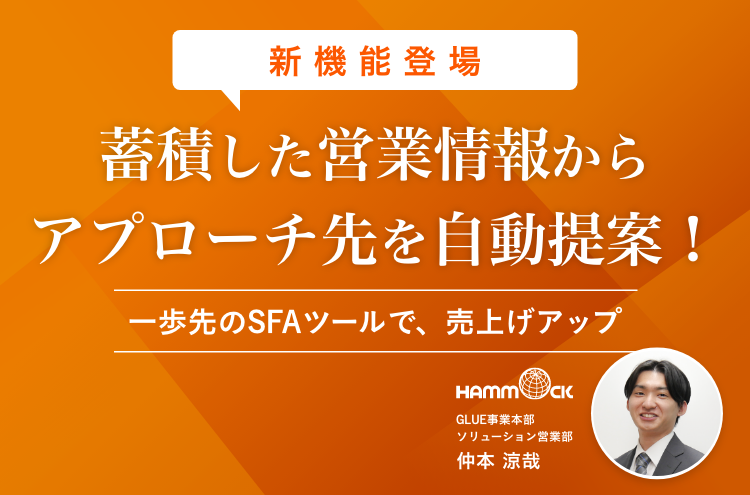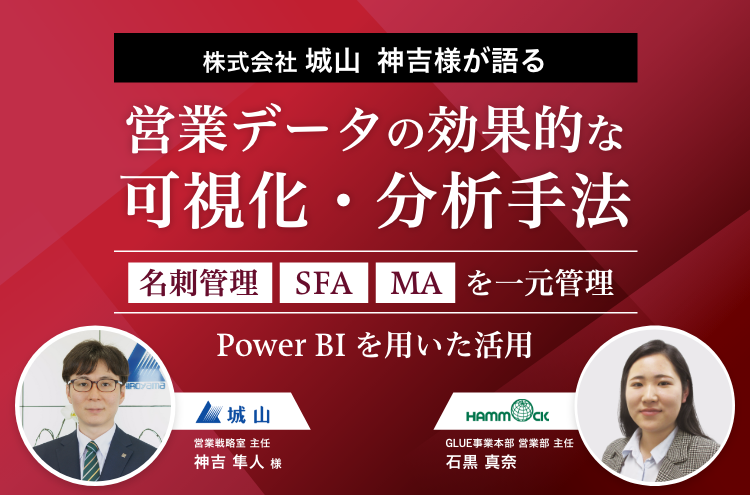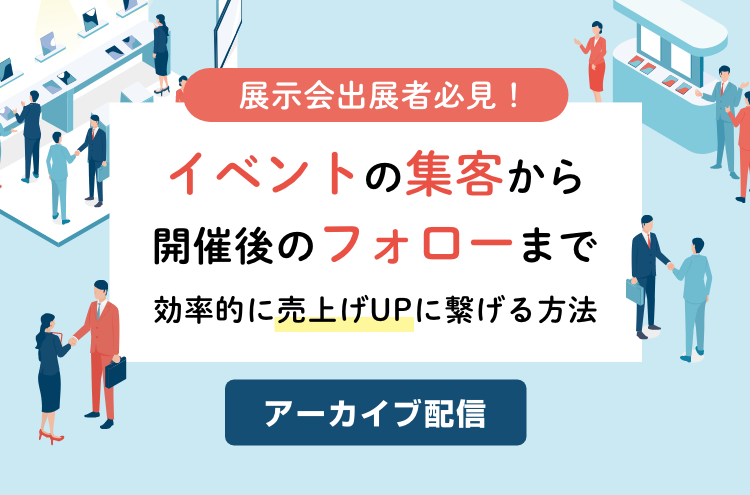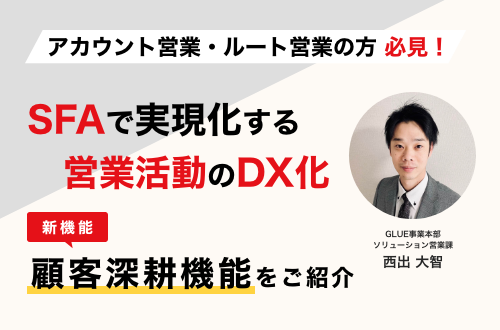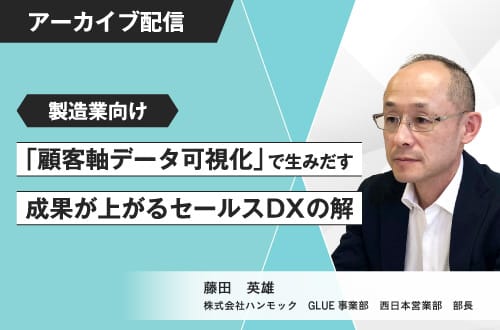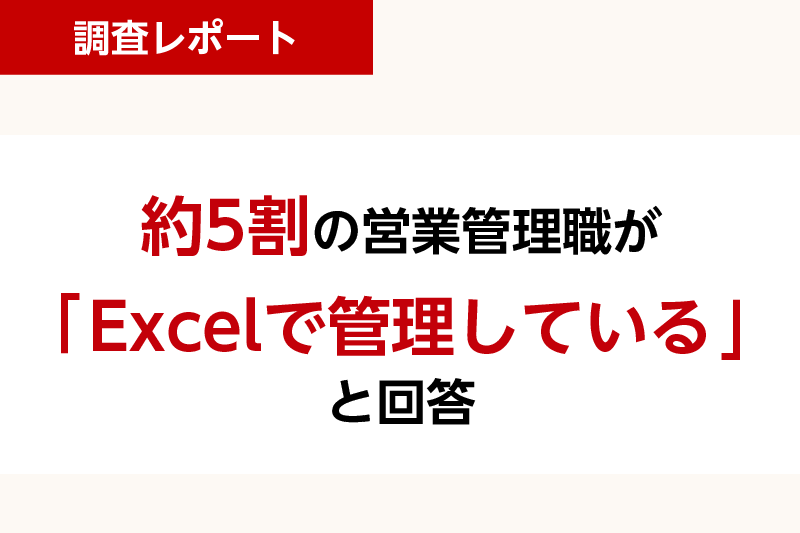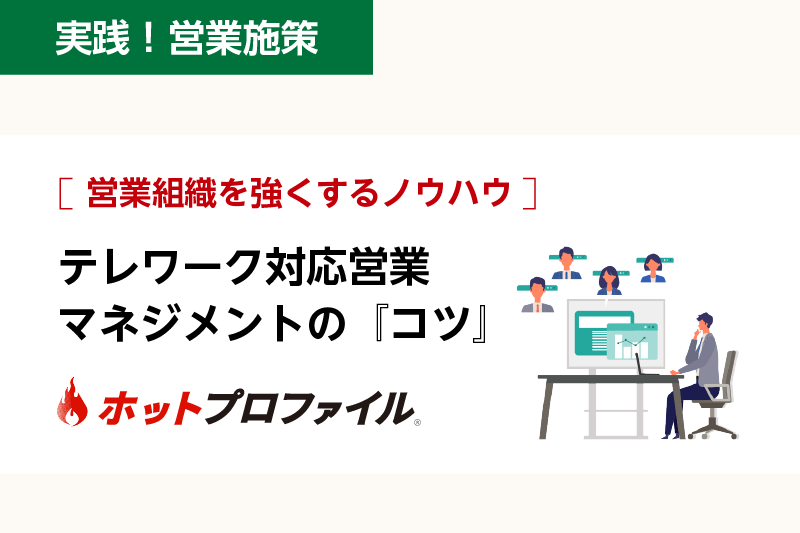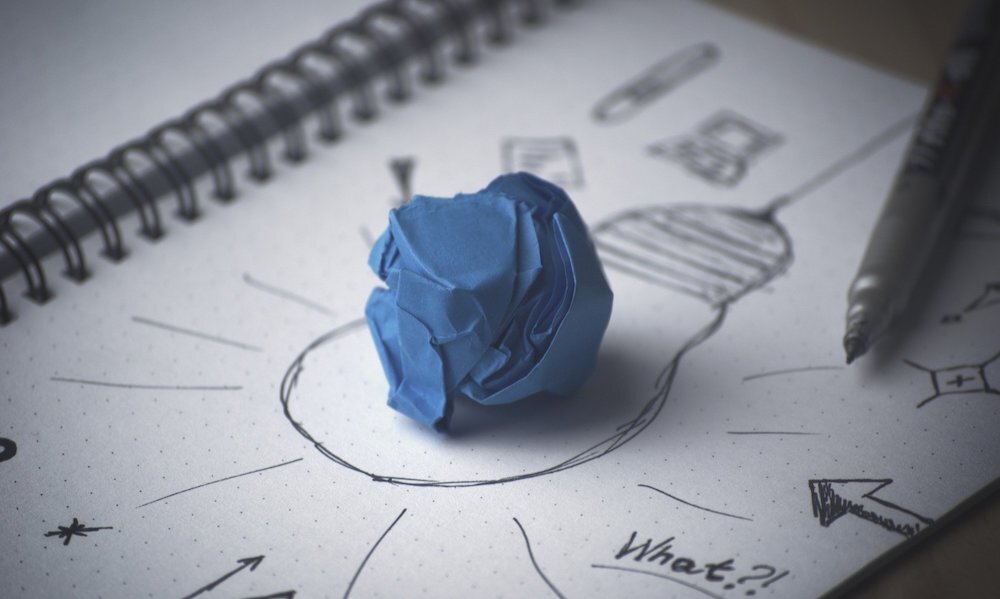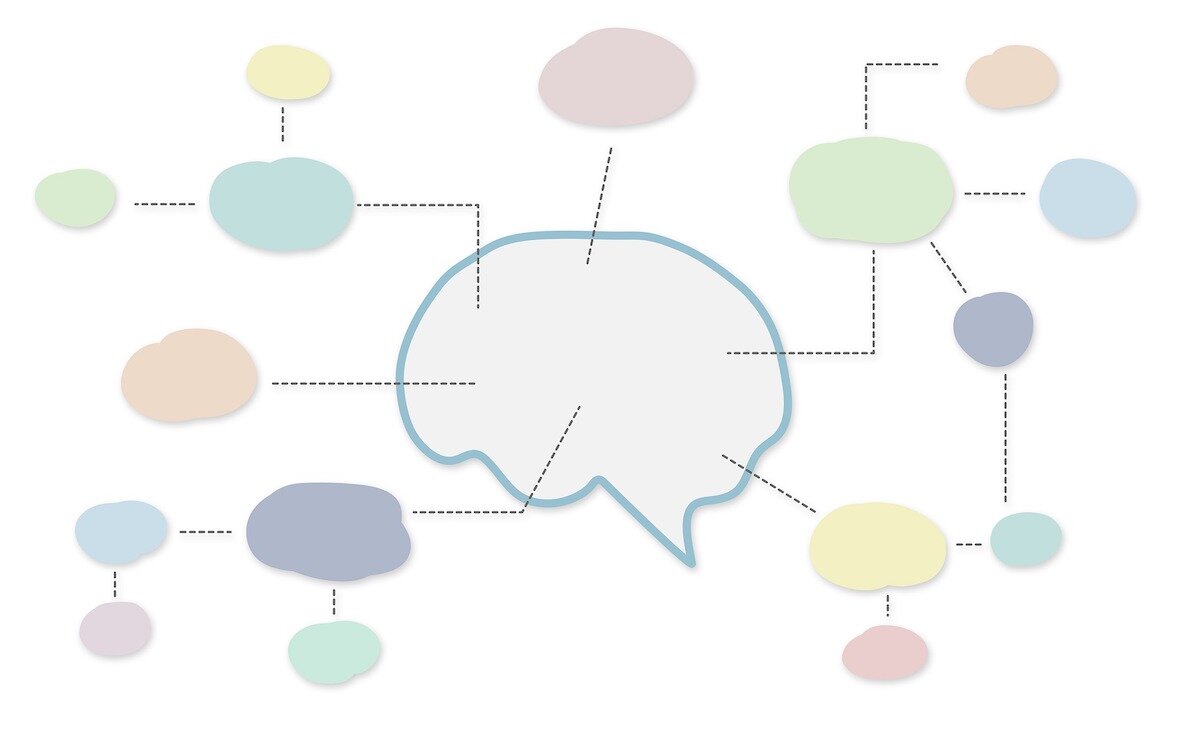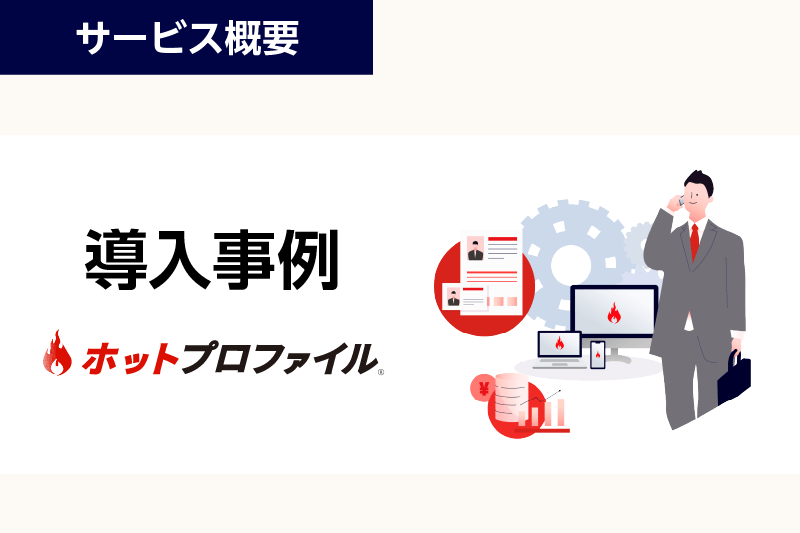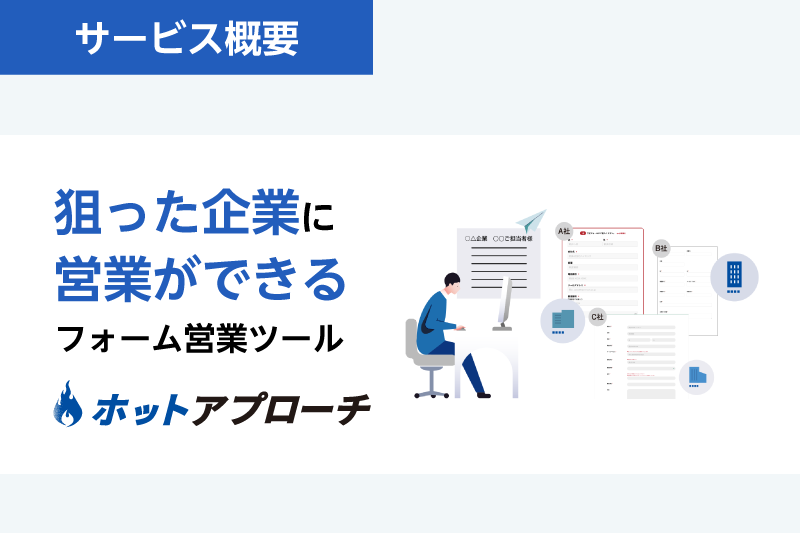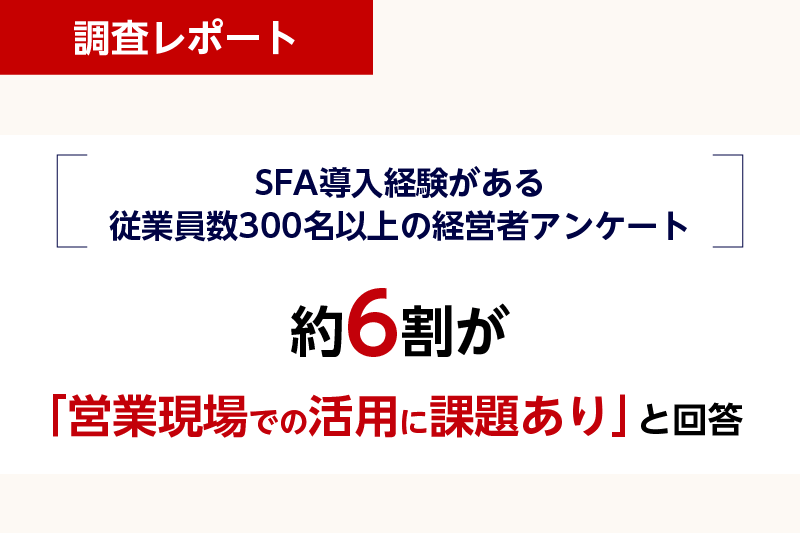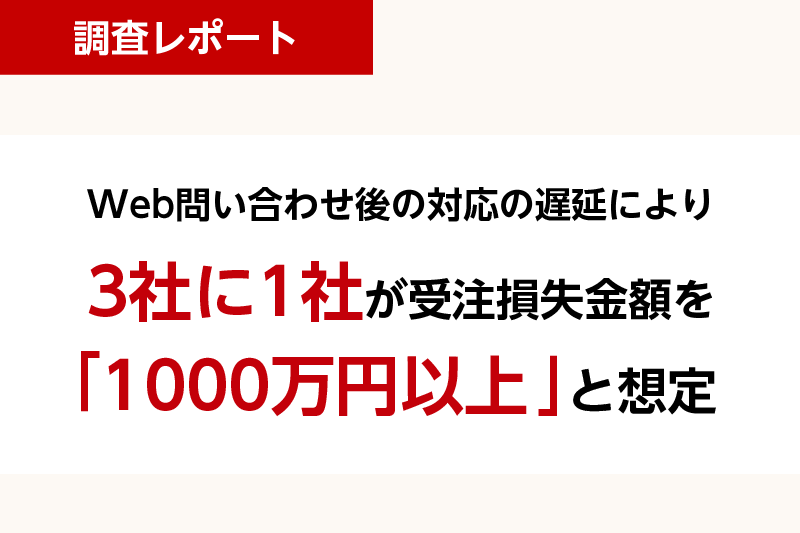ナレッジマネジメントとは?暗黙知の共有方法から導入ステップ・成功ポイントまで徹底解説
- INDEX
-

ナレッジマネジメントとは、社員が持つ知識・経験・ノウハウを組織全体で共有し、業務効率化や生産性向上につなげる経営手法です。暗黙知の言語化や業務プロセスへの組み込みが進めば、属人化の解消や人材育成にも大きく貢献します。本記事では、ナレッジマネジメントの基本、手法、SECIモデル、導入手順、成功のポイント、最新ツールまで体系的に解説します。
ナレッジマネジメントとは?基本の意味と注目される理由
ナレッジマネジメントは、社員一人ひとりが日々の業務で培った知識や経験を組織全体の財産として活用するための取り組みです。情報を管理するだけでなく、現場に埋もれたノウハウを共有し、新たな価値を生み出す基盤づくりともいえます。近年は人材不足や業務の複雑化から、より効率的な知識共有が求められ、企業の競争力を高める重要なテーマとして注目されています。ナレッジ(知識・経験)とは何か?暗黙知と形式知の違い
ナレッジとは、業務を進めるうえで必要となる知識や経験の総称です。大きく分けると、言語化できる内容と、言語化しづらい内容の二種類があります。前者はマニュアルや手順書として残せる形式知で、後者は熟練者が感覚的に身につけている暗黙知です。ナレッジマネジメントでは、この暗黙知をどれだけ引き出し、活用しやすい形にできるかが大きな鍵になります。例えば顧客対応の細かな判断や、トラブル時の勘どころなどは暗黙知に該当し、共有されることで業務全体の底上げにつながります。参照:令和5年度 経済産業省政策関係調査事業
ナレッジマネジメントが求められる背景と企業課題
ナレッジマネジメントの必要性が高まっている背景には、企業が直面する環境変化があります。業務の複雑化や専門知識の増加により、個々が持つ知識を整理しなければ、組織全体として十分に活かしきれない状況が生まれています。さらにテレワークの拡大で自然な情報交換の場が減り、知識が部署内や個人の中に留まりやすくなりました。このような状況では、知識を可視化し誰でもアクセスできる状態にする仕組みが欠かせません。属人化防止・技術継承が重要視される理由
属人化は、特定の社員に業務が集中し、担当者が不在になるだけで業務が停滞してしまう状態を指します。長年の経験で培われたノウハウが担当者の頭の中にだけ存在する場合、退職や異動によって知識が失われるリスクも生まれます。ナレッジマネジメントは、このリスクを軽減するための有効な取り組みです。日々の業務内容や経験を言語化し記録として残すことで、誰が担当しても一定の品質で業務を進められる環境が整います。結果として、新人育成の負担が軽減され、組織の長期的な成長にもつながります。参照:統計局ホームページ/労働力調査
関連記事:属人的な名刺管理から組織的な管理・共有化へ
ナレッジマネジメントの目的は何か?
ナレッジマネジメントの目的は、単に情報を共有することにとどまりません。業務の質を高め、組織としての成長を実現するための土台をつくる役割があります。現場で蓄積される知識を活用すれば、業務のバラつきを抑えたり、新たな価値を生み出すきっかけにもつながります。ここでは、代表的な目的を整理して解説します。業務効率化・生産性向上を実現する目的
ナレッジマネジメントが重視される大きな理由のひとつが、業務効率化と生産性向上です。同じ作業でも担当者ごとに進め方が異なると、判断に迷いやムダな時間が生まれやすくなります。過去のトラブル対応の記録や成功パターンが共有されていれば、似た状況に遭遇した際に迅速に判断でき、作業の精度も向上します。また手順書やFAQが整備されることで、新人や他部署のメンバーでもスムーズに業務を引き継ぎやすくなり、組織全体の生産性に良い影響をもたらします。人材育成・技術継承を加速させる目的
長年の経験で培われた技術や判断基準は、言語化しなければ引き継ぐことが難しい場面があります。ナレッジマネジメントは、この暗黙知を形式知に変えて共有する取り組みを後押しします。具体的には、熟練者の業務プロセスの記録、判断理由の整理、事例の蓄積などが挙げられます。こうしたナレッジが整うことで、育成のスピードが上がり、担当者による品質の差も縮まりやすくなります。育成の効率化は組織の持続的な成長を支える重要な要素です。顧客価値向上や新規事業開発につながる目的
ナレッジは社内業務だけでなく、顧客との関係や事業づくりにも影響します。たとえば顧客対応で得た情報や、問い合わせの傾向、過去の改善提案などを整理して共有すれば、より質の高いサービスや提案につなげることができます。また、現場で得られた知見が集まれば、新しいサービスのヒントが生まれたり、既存事業の見直しにも役立ちます。ナレッジをただ蓄積するのではなく、顧客価値へと変換していくことが、組織の競争力を高める鍵になります。どんなナレッジを共有すべきか?種類と具体例
共有すべきナレッジは一種類ではなく、業務の進め方から経験に基づく判断まで幅広く存在します。特に、形式知として整理できる情報と、言語化しにくい暗黙知の両方を扱うことで、組織全体の判断力や業務品質が安定しやすくなります。ここでは、実務でよく扱われるナレッジの種類を具体例とともに取り上げます。業務手順・FAQ・トラブル対応などの形式知
形式知は言葉や文書としてまとめやすく、共有や教育に活用しやすいナレッジです。代表的なものとして、業務手順書、チェックリスト、FAQ、トラブル発生時の対応フローなどがあります。これらが整っていれば、担当者による作業の差が小さくなり、作業品質の安定につながります。また、問い合わせ対応の記録やマニュアルも形式知の一つで、新人が業務に慣れるまでの期間を短縮する効果も期待できます。熟練者のコツ・顧客対応ノウハウなどの暗黙知
暗黙知は、経験の積み重ねによって身につく判断基準や動き方など、文章化が難しい性質を持っています。例えば、顧客が何を求めているかを読み取る感覚、商談でのタイミングの見極め方、機器の異常に気づく微妙な違和感などが挙げられます。これらは放置すると個人の中に留まりやすいため、インタビュー、動画記録、ケースレビューなどを通じて徐々に言語化し、共有する取り組みが効果的です。暗黙知の共有は、組織全体の経験値を引き上げる大きな力になります。成功事例・失敗事例から得られる知識
業務で得られる学びは、成功だけでなく失敗からも生まれます。特に失敗事例は再発防止に役立つ重要なナレッジですが、担当者間で共有されずに埋もれてしまうこともあります。過去の取り組みで上手くいった理由や、逆にうまくいかなかった要因を整理して共有すれば、次の改善策を考える材料になります。部署を超えて事例を蓄積していくことで、新しい取り組みを検討する際の判断材料にもなり、組織全体の知識資産として価値を持つようになります。
ナレッジ創造のプロセス「SECIモデル」とは?
SECIモデルは、個人が持つ経験や知識がどのように組織全体へ広がり、新しい価値を生み出すかを示したプロセスです。暗黙知と形式知が循環しながら変化していく仕組みを理解すると、ナレッジマネジメントを実行する際の指針として役立ちます。ここでは、それぞれの段階でどのように知識が生まれ、共有され、活かされていくかを解説します。共同化で経験知を共有する方法(暗黙知×暗黙知)
共同化は、暗黙知を暗黙知のまま共有する段階です。例えば、現場で熟練者の作業を観察したり、一緒に仕事をしながら学ぶような形式がこれに当たります。言葉にしづらい感覚や判断のコツは、対話や共同作業を通じて伝わることが多く、チーム内での影響力も大きい部分です。研修やOJT、現場同行など、経験をそのまま感じ取れる環境を用意することで、このプロセスはより進みやすくなります。表出化でノウハウを言語化する手順(暗黙知→形式知)
表出化は、暗黙知を形式知へ変換する工程です。熟練者の感覚や判断の裏にある理由を言葉にし、誰でも利用できる形にします。例えば、成功した対応の背景にあった判断基準を文章化したり、トラブル対応の経験を整理して手順としてまとめるといった取り組みです。この段階では、インタビューやケースレビューが役立ちます。感覚的だった知識が文書として残ることで、部署を超えた共有がしやすくなります。連結化・内面化で知識を定着させる方法
連結化では、さまざまな形式知を組み合わせ、新しい知識体系として整理します。例えば、手順書やFAQを統合して業務の基準を整備したり、事例をまとめて改善策のガイドラインにするなどの作業が該当します。その後の内面化では、整理された形式知を実際の業務で活用し、個人が新たな暗黙知として身につけていく段階です。反復することで知識が身体化され、組織としての総合的な経験値が積み上がっていきます。こうした循環が続くことで、ナレッジは自然と蓄積され、組織全体の力へと変わります。参照:知識創造企業 | 東洋経済STORE
ナレッジマネジメントはどう進める?導入の手順
ナレッジマネジメントを成功させるには、取り組みを始める前に目的や共有すべき知識を明確にし、実際の業務フローに落とし込んでいくことが欠かせません。システム導入だけでは定着しないため、プロセス設計や改善の仕組みまで含めて一連の流れを整える必要があります。ここでは、現場で無理なく運用できる形にするための導入手順を解説します。関連記事:【情報共有の基本】メリットや方法、役立つツールなどを解説
目的・KPIの設定と共有すべき情報の選定
ナレッジマネジメントの導入では、まず目的とKPIを明確にすることが大切です。たとえば業務効率化を目指すのか、属人化の解消を優先するのかによって、集める情報や共有の仕組みは変わります。目的が定まったら、どの知識を共有するべきかを選定します。作業手順やFAQのような形式知だけでなく、熟練者が持つ判断の基準や注意点といった暗黙知も対象に含めます。無理にすべてを網羅する必要はなく、まずは日々の仕事で活用度が高いものから整理すると運用が進みやすくなります。業務フローに情報共有を組み込む方法
選定したナレッジを活かすには、既存の業務フローに自然な形で共有の動線を組み込むことが重要です。たとえば、商談後の振り返りで事例を登録する仕組みを設けたり、問い合わせ対応の履歴をデータベース化してFAQに転記するなど、日々の業務とつながる形にすると負担が増えにくくなります。システムを使う場合も、入力作業が複雑だと定着しづらいため、現場が使いやすい操作性かどうかを確認することが欠かせません。業務の流れに溶け込むように設計することで、ナレッジが自然と蓄積される環境が整います。定期的な見直しで運用を定着させるポイント
ナレッジマネジメントは、一度仕組みを作れば終わりというものではありません。運用が始まると、新しく必要になる情報が出てきたり、逆に使われていないコンテンツが見つかることがあります。こうした状況を把握するために、定期的な見直しが不可欠です。運用状況を振り返り、改善点を確認し、不要な情報を整理することで、常に使いやすく価値のある状態を保てます。現場の声を反映しながら仕組みを更新していく姿勢が、長く続くナレッジマネジメントの土台になります。ナレッジマネジメントを成功させるためのポイントは?
ナレッジマネジメントは仕組みを導入しただけでは定着しません。知識を共有したくなる空気づくりや、言語化しやすい環境、部門を超えた連携など、日々の行動に影響する要素を整えることが欠かせません。ここでは、現場で運用が続き、組織全体にナレッジが広がっていくための実践ポイントを整理します。社員が参加したくなる仕組みづくり
ナレッジが集まらない原因の多くは、社員にとって共有のメリットが見えにくいことにあります。業務に役立つ情報がすぐに見つかる、問い合わせの負担が減る、自分の取り組みが評価されるといった小さな成功体験が積み重なると、自然と参加意欲が高まります。また、投稿や改善案に対して感謝を伝える仕組みを設けると、心理的なハードルも下がります。負担を強いるのではなく、参加すると仕事が進めやすくなる体験を作ることが鍵になります。言語化を促進する環境整備と共有文化の醸成
暗黙知の多くは、本人にとって「当たり前」に感じられるため、言語化するきっかけが必要です。短いメモから登録できる仕組みや、事例レビューを定例化するなど、話す・書く機会を増やすことで言語化が進みます。また、未完成の情報でも歓迎する姿勢を示すと、共有の敷居が下がります。完璧さよりも「まず出すこと」を評価する文化が醸成されると、ナレッジは自然と蓄積されやすくなります。管理部門・現場・経営層の連携体制を強化する
ナレッジマネジメントは特定の部門だけで進めると、運用が途中で止まりやすくなります。現場は実際の知識を持ち、管理部門は運用設計やルール整備を担い、経営層は目的と方向性を示す、といった役割分担が必要です。特に経営層が重要性を明確に示すと、全社的な取り組みとして浸透しやすくなります。部門をまたいで連携することで、知識が組織全体の資産として扱われ、継続的な運用が可能になります。ナレッジマネジメントに活用できる手法・ツールは?
ナレッジを残し、広げ、活かしていくためには、運用の目的や組織規模に応じて適切な手法やツールを選ぶことが欠かせません。手軽に始められる仕組みから、本格的なナレッジ管理システムまで選択肢は幅広く、組み合わせ次第で業務効率化や情報共有の質も大きく変わります。ここでは代表的な方法と特徴をわかりやすく整理します。エクセル・マニュアル・共有フォルダのメリット
エクセルや共有フォルダは、初期コストをかけずに始められる点が大きな利点です。既存の業務環境と相性がよく、誰でも扱えるため導入のハードルが低いという強みがあります。FAQや手順書の更新も簡単で、小規模なチームなら十分に機能します。ただし、情報量が増えてくると検索性や更新管理が難しくなるため、どこまでを手軽な運用で対応し、どこからをシステム化するのかを見極めることが大切です。ナレッジ管理システム(KMS)の機能と選び方
本格的にナレッジを蓄積・活用したい場合は、専用のナレッジ管理システムを検討すると効果が高まります。検索性の高いデータベース、権限管理、ワークフロー、コメント機能、FAQ作成、レコメンドなど、多様な機能が一つに集約されているため、属人化の防止や情報の一元管理に向いています。選ぶ際は、現場が無理なく使える操作性かどうか、既存システムとの連携が可能か、共有文化を育てられる仕組みがあるかといった点が判断材料になります。運用負担が軽いほど、現場の情報が自然に蓄積されやすくなります。チャット・社内SNS・FAQ管理との組み合わせ
チャットツールや社内SNSは、日常のコミュニケーションの中にナレッジが生まれやすい点が魅力です。質問や気づきがリアルタイムで流れるため、情報の速さと質が上がります。ただし、流れてしまうという弱点もあるため、重要なやり取りはFAQやKMSへ整理して蓄積する仕組みが必要です。日常の会話で生まれた暗黙知をキャッチし、正式なナレッジとして残す一連の流れが整うと、組織全体で知識が循環しやすくなります。複数ツールを連携させることで、現場の動きに沿った自然なナレッジマネジメントが実現します。まとめ:ナレッジを資産に変え、組織の成長力を高めよう
ナレッジマネジメントは、単に情報を集める仕組みではなく、知識を共有し合い、組織全体で活かし続けるための取り組みです。暗黙知と形式知を循環させることで、業務の質が高まり、属人化の防止や技術継承にもつながります。また、現場で得た気づきや経験が組織の財産として蓄積されれば、新しい価値創造にもつながります。取り組みを根づかせるには、共有しやすい環境づくりと部門を越えた連携が欠かせません。営業活動にもナレッジの活用は大きな効果を生みます。顧客情報の一元管理や案件進捗の可視化が進むことで、営業チーム全体の動きがスムーズになり、成果につながる行動が自然と増えていきます。
ハンモック社が提供するホットプロファイルは、名刺管理・SFA・MAを一体化した営業支援ツールとして、こうしたナレッジ活用の基盤を整えるのに役立ちます。顧客データの自動整理から商談管理、見込み顧客の検知まで、営業に必要な要素がそろっているため、日々の活動がより効率的になります。営業DXを進めたい企業にとって、導入検討の価値は十分にあるツールです。
関連記事:名刺管理ツール活用で解決できる課題や導入メリット