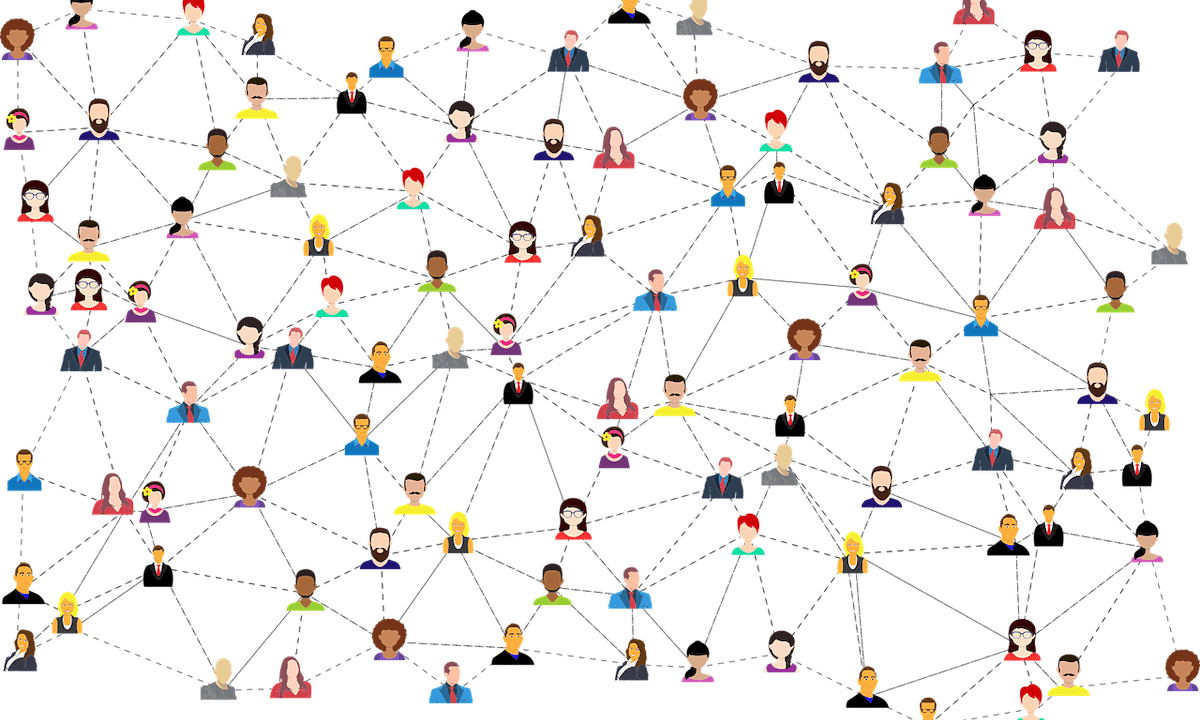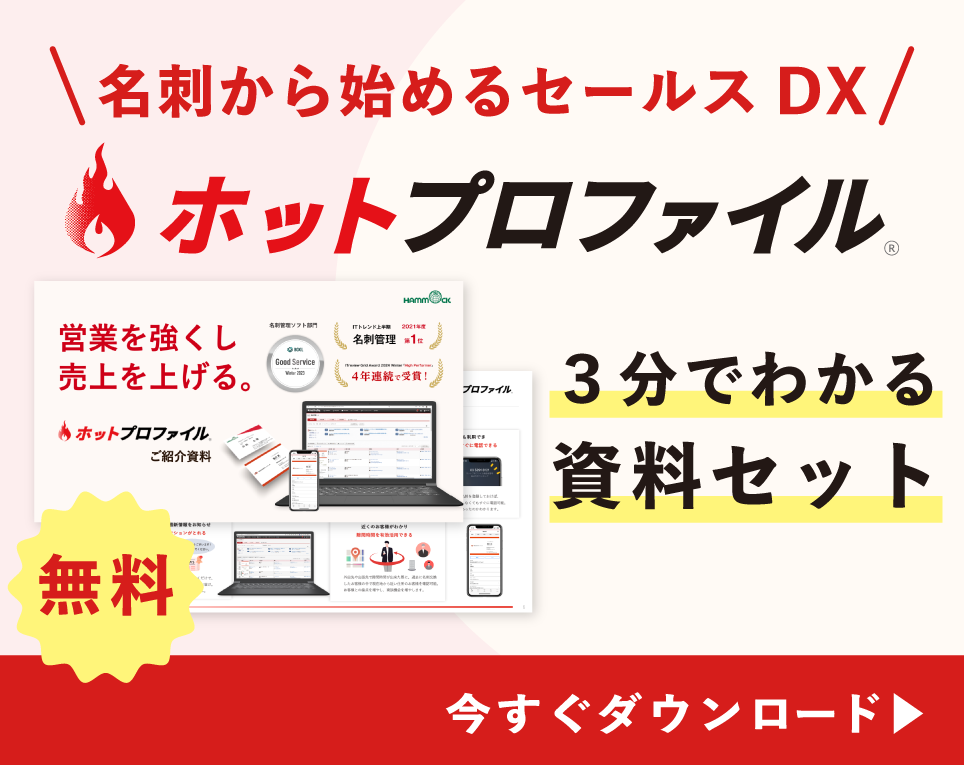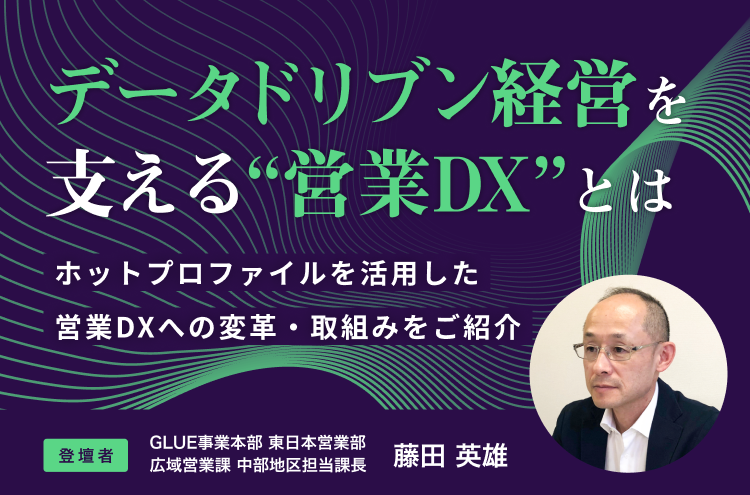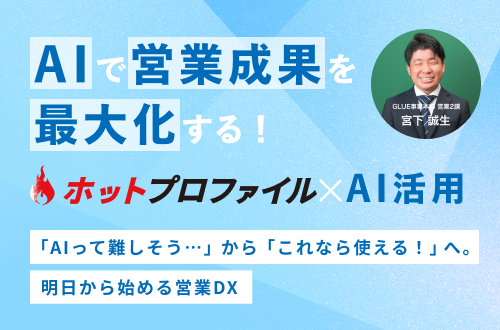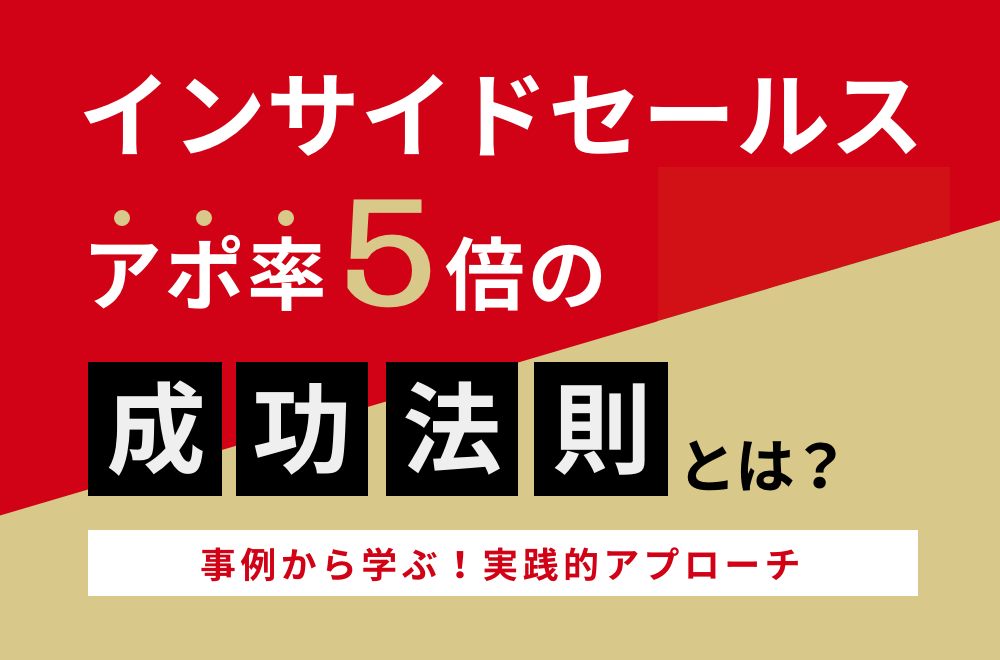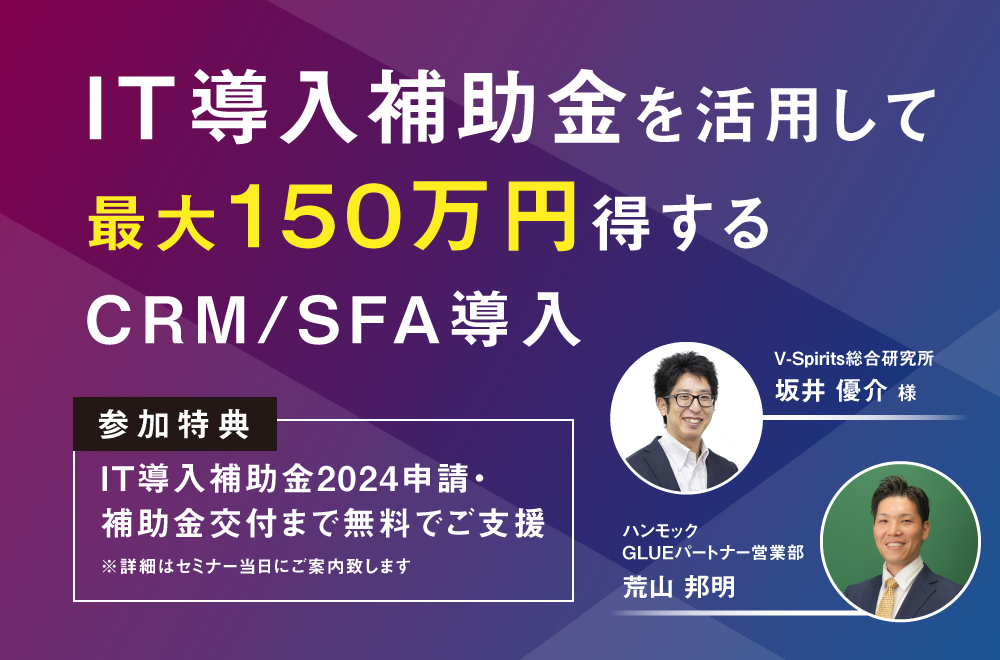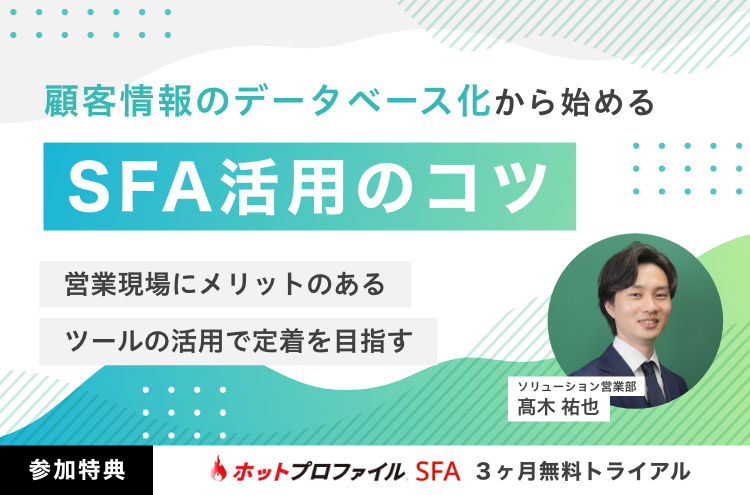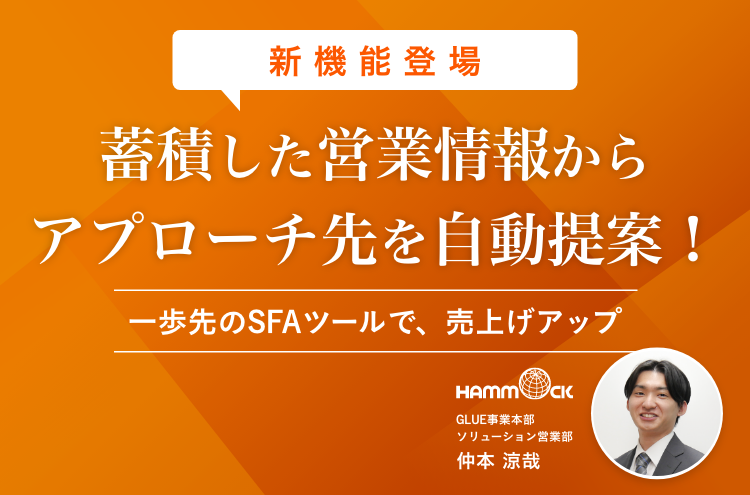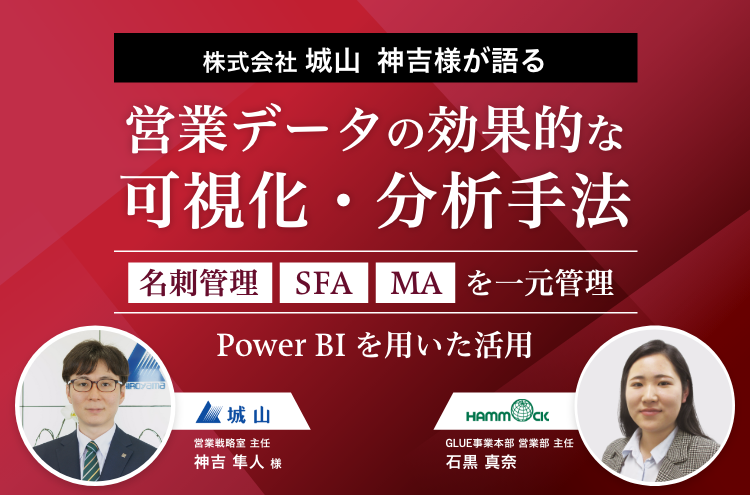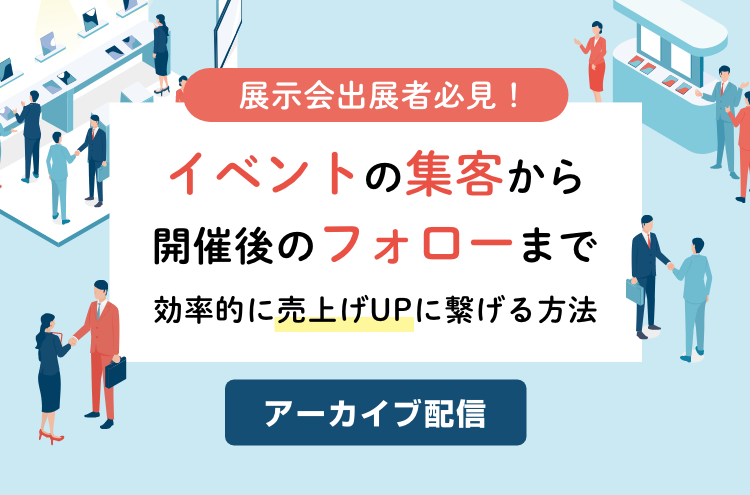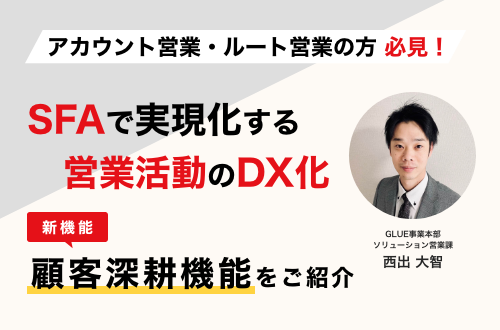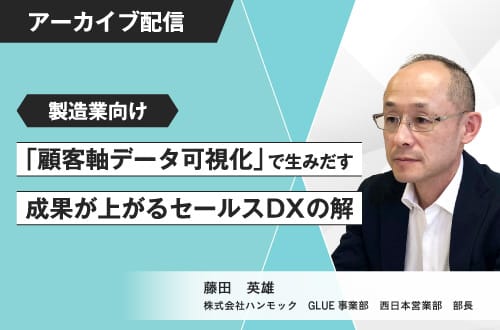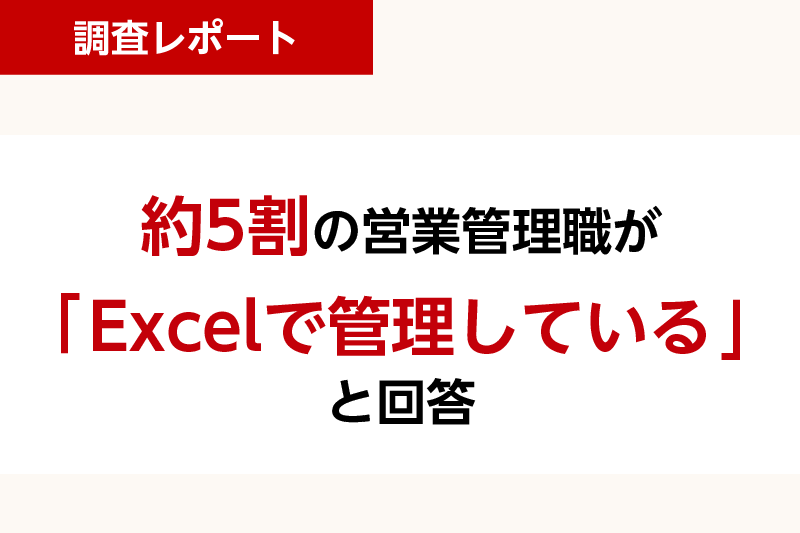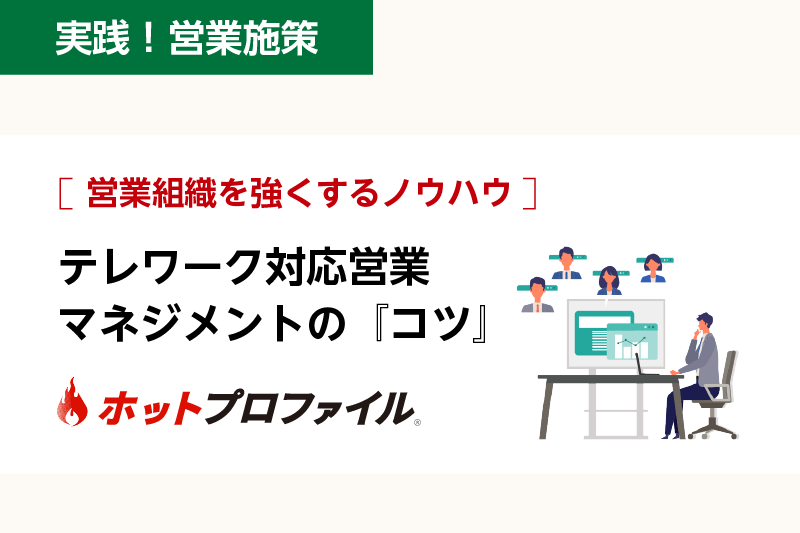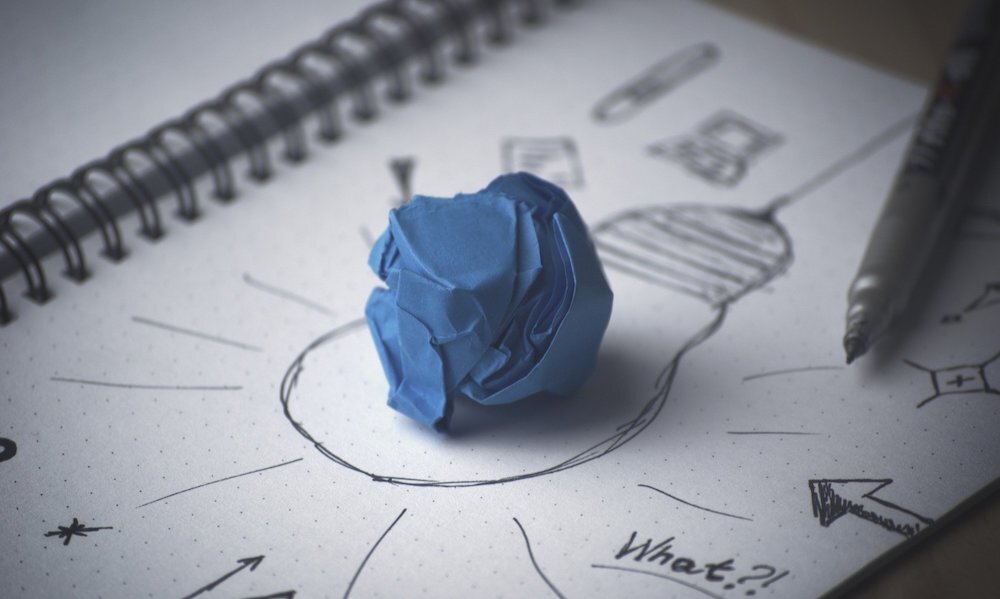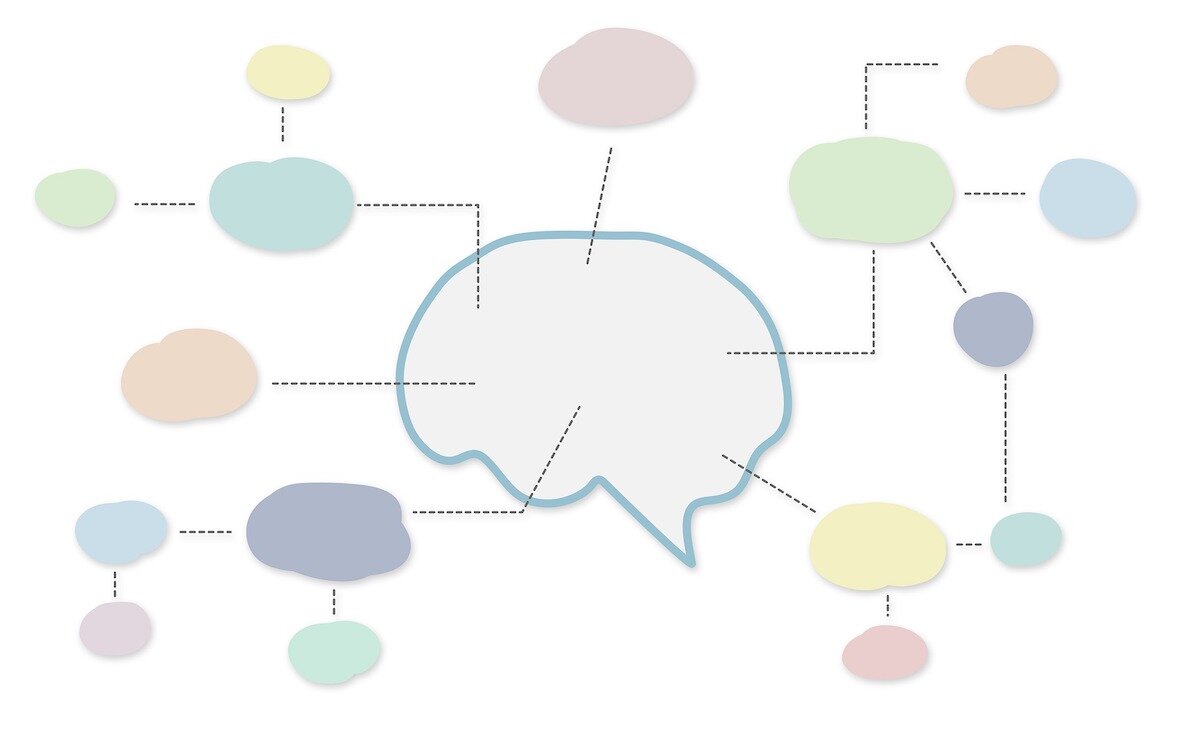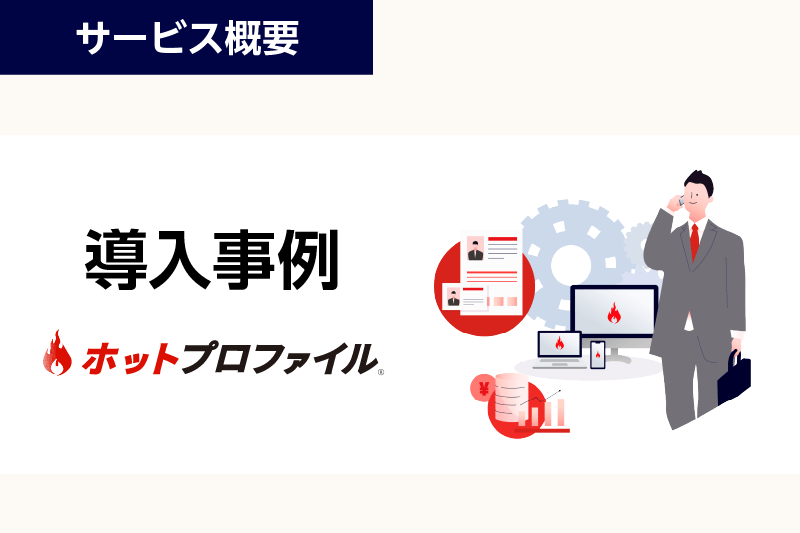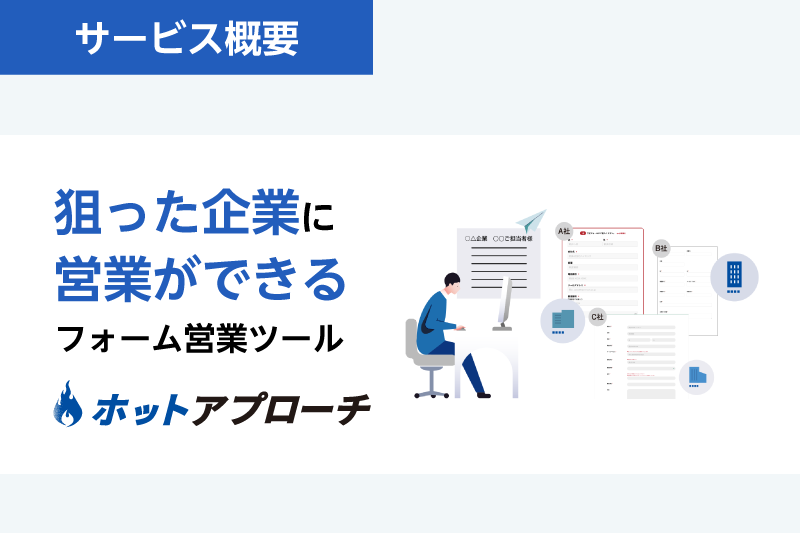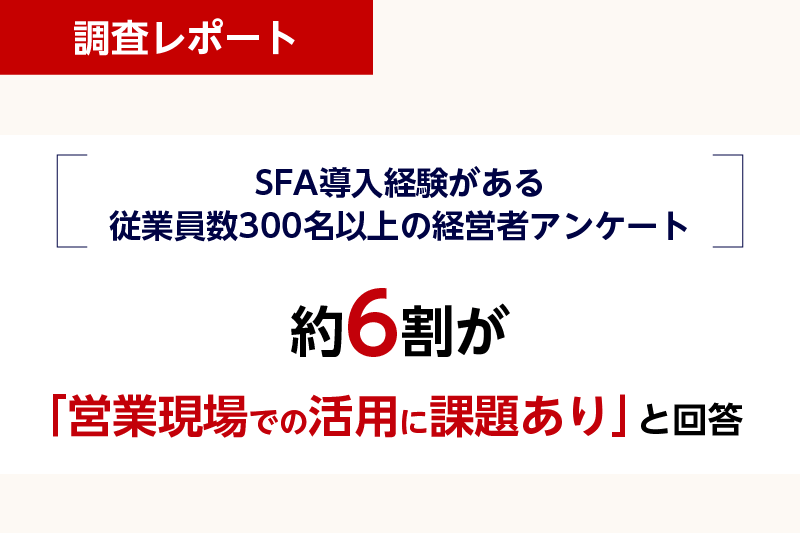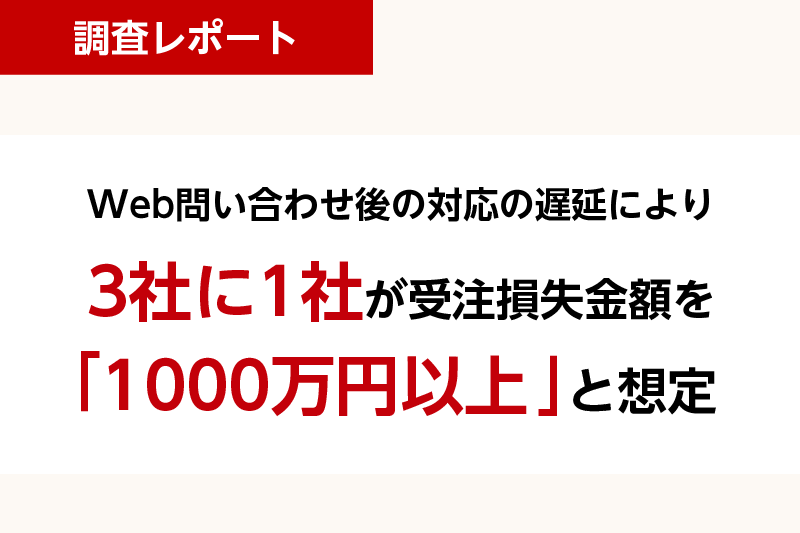【ケース別】名刺のもらい方やポイントをわかりやすく解説
- INDEX
-
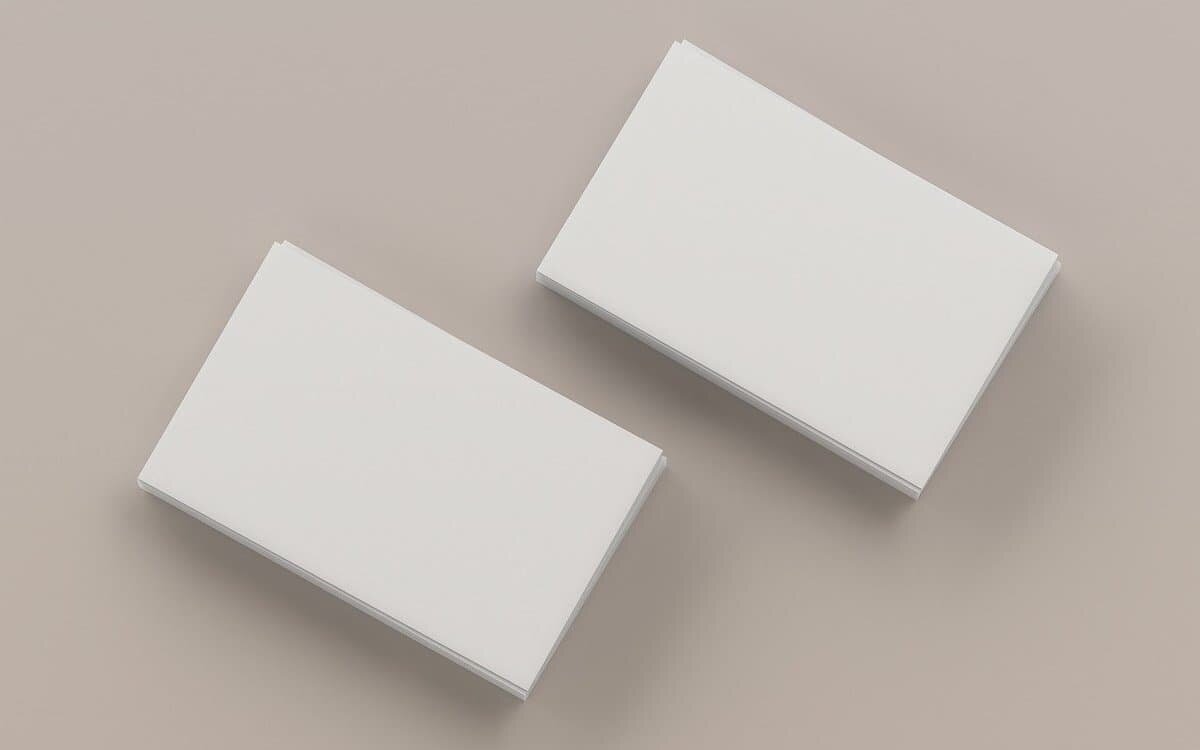
・名刺のもらい方にセオリーはあるの?
・相手が複数いる場合、どうやって名刺をもらうの?
・もし自分が名刺を忘れた場合はどうなるの?
初めて営業の現場に出る方や新入社員の方は、冒頭のような疑問を抱えておられると思います。
そこでこの記事では名刺のもらい方の基本に加えて、営業現場で起こりうる様々なケースごとに、名刺のもらい方やポイントを分かりやすく解説しています。
これから名刺交換を行うことになる方は、是非一度この記事を最後まで読んで、正しい名刺のもらい方を身に着けてください。
基本となる名刺のもらい方
まずは名刺をもらう際の基本的な所作についてお話していきましょう。
基本となる名刺のもらい方
名刺は基本的に「両手で受け取る」ことが望ましいです。
とはいえビジネスの名刺交換シーンでは、多くの場合こちらも渡しながら受け取ることになります。
その場合は名刺入れを持つ方の手で、相手の名刺をもらうと良いでしょう。
もらった後は両手を添えつつ、胸の高さあたりまで引き寄せるようにすれば、マナーの観点でも十分と言えます。
商談中、もらった後の名刺をどうするのか
名刺交換は往々にして商談開始前に行われることになるので、「もらった名刺を商談中どうすればいいのか」という懸念点が出てきます。
この懸念に対する回答は実にシンプルで、「机の上に置く」です。
ただし、ただ単に机の上に置いておけばいいというものでもなく、自分の名刺入れの上に置くことが基本になります。
商談相手が複数人いる場合は、相手の座る位置と連動させて名刺を置いておくと良いでしょう。
この際相手側でもっとも役職の高い人の名刺を、名刺入れの上に置く形になります。
商談終了後、名刺を回収する時はどうするのか
無事商談が終われば、机の上に置いている名刺を回収しなければなりません。
この時は相手が自分の渡した名刺をしまうタイミングを見計らって、「頂戴します」という風に一声添えた上で、名刺入れにしまうと良いでしょう。
なお回収の際に雑に扱って名刺が折れ曲がったり、落としたりしないように、丁寧に取り扱うことが重要です。
【ケース別】名刺のもらい方とポイント
ここからはビジネスシーンでよく発生するケース別に、名刺のもらい方や注意点をお話していきます。
ケース①:相手が複数いる場合のもらい方
まず一つ目のケースは相手が複数いる場合です。
先程お話した基本となる名刺のもらい方のところでは、1対1を前提にお話ししてきたので、読み進めている中で「複数いる場合は?」と思われた方もいらっしゃるでしょう。
相手が複数いる場合は、基本的に役職の高い人から順番に名刺をもらうというのが基本です。
例えば相手方が以下のようなメンバーだとします。
・担当者A
・担当者Aの上司
この場合は「担当者Aの上司」⇒「担当者A」の順番に名刺をもらいましょう。
<ポイント>
商談開始時に相手の役職がわからないこともあります。
その場合、入り口から一番遠い位置(上座)に座っている人から順番にもらうようにすれば、問題ありません。
ケース②:こちらが複数いる場合のもらい方
続いてこちらが複数いる場合の名刺のもらい方を見ていきましょう。
こちらが複数いる場合でも先ほどと同じく、役職の高い人から順番に相手の名刺をもらう形になります。
例えば
・自分
・自分の上司
・自分の現場教育担当
というメンバーで商談に臨んだ場合は以下の順番となります。
①自分の上司
②自分の現場教育担当
③自分
<ポイント>
相手側も「誰が役職の高い人かわからない...」と思っている場合があるので、「上司の○○です」、「教育担当の○○です」といったように紹介すると、スムーズに名刺交換を開始できます。
ケース③:こちらも相手も複数いる場合のもらい方
続いてのケースはこちら側も相手側も複数いる場合です。
こちら側も相手側も複数いる際は、ケース①・②と同じく役職の高い人同士から順に名刺交換に臨みます。
例えば以下のようなメンバーで名刺交換を行うとします。
【自社】
・A:自分
・B:自分の上司
【相手先】
・C:担当者
・D:担当者の上司
この場合の順番は
①BとD
②BとC
③AとD
④AとC
となります。
<ポイント>
上記のケースでいうところの②と③は同時に行っても構いません。
その方がスムーズに商談に入ることができるので、自分の上司が名刺をもらい終わった相手から順番に名刺交換を行うと良いでしょう。
ケース④:自分が名刺を持っていない場合のもらい方
次に自分が名刺を持っていない場合のケースです。
名刺を切らしている場合は勿論のこと、名刺を忘れてきてしまったといった事態も中にはあるでしょう。
そういった状況下で名刺交換の場に臨まなければならない場合は、「ただいま名刺を切らしておりまして...」と謝罪しつつ、名刺をもらうことが基本となります。
その上で名刺の代わりに社名・部署名と氏名を口頭で伝えるようにしましょう。
<ポイント>
仮に名刺を忘れてきてしまった場合でも、正直に名刺を忘れたとは言わないようにしましょう。
また帰社後相手の名刺に記載されているメールアドレス宛に、改めての謝罪とともにこちらの名刺情報を記載して、メールしておくことも重要なポイントです。
ケース⑤:相手が名刺を出してこない場合のもらい方
最後にご紹介するのは相手が名刺を出してこないケースです。
営業の現場に出ると様々なお客様に会うことになり、中には名刺を渡してくれない担当者もいます。
そのような場合は、商談終了後に「恐れ入りますがお名刺を一枚頂戴できますでしょうか」と丁寧にお願いして、名刺をもらうようにしましょう。
<ポイント>
もし相手が名刺を切らしている場合は、自分の名刺に記載されているメールアドレスまでご連絡いただくようにお願いするか、電話番号を口頭で確認しておくようにすれば、今後の連絡もスムーズに行えます。
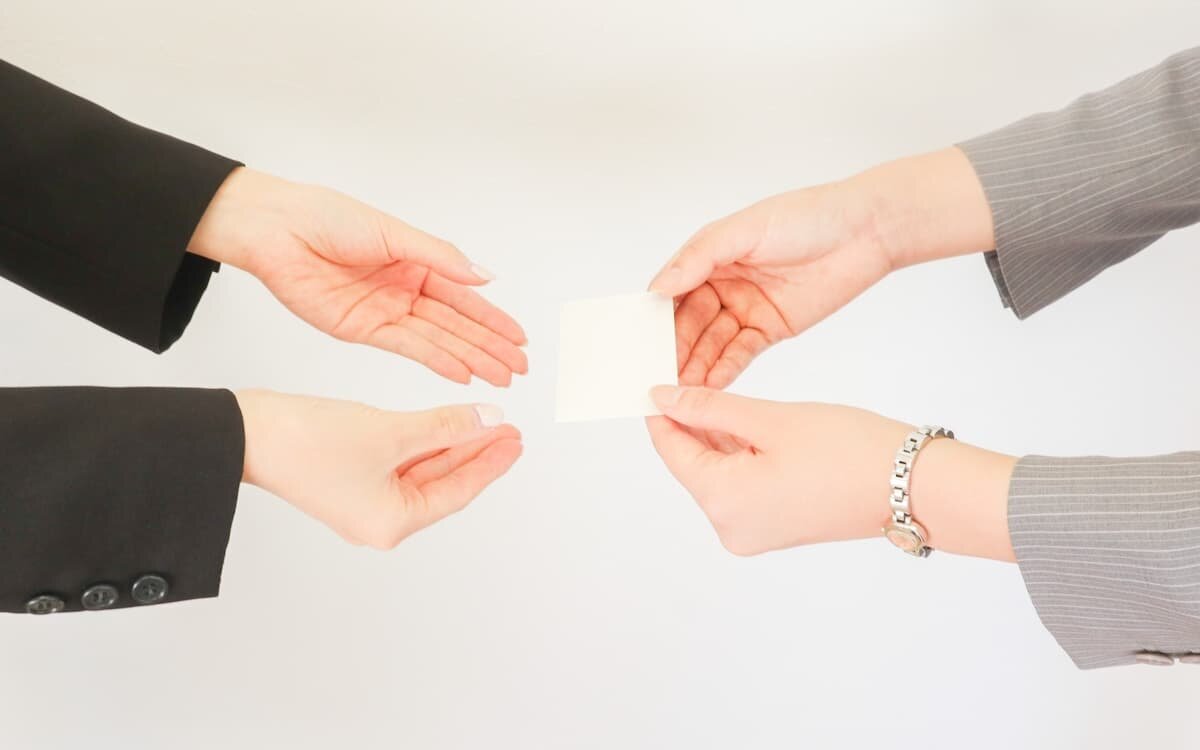
もらった名刺をフルに活用するには
最後にもらった名刺を最大限活用するためのポイントをお話しておきます。
ポイント①:データ化し、部門全体で共有する
一つ目のポイントはもらった名刺をデータ化した上で、部門で共有するという点です。
名刺をフル活用するには、データ化することが大前提になってきます。
もし紙のまま名刺フォルダなどを用いて個人で管理していると、名刺を紛失してしまったり、必要な時になかなか見つけられなかったリ、といった事態が起こり得るのです。
また部門内に、「自分が名刺をもらった担当者と深い関係にある人物の名刺」を持っている社員がいても、それを把握することができません。
そういったリスクや機会損失を回避するためにも、もらった名刺はデータ化し、営業部門全体で共有すべきでしょう。
名刺をデータ化するには
・PDF化する
・EXCELファイルに入力する
・名刺管理システムを導入する
といった方法があります。
ポイント②:名刺管理システムを導入する
これらの方法の中でも特にオススメしたいのが名刺管理システムの導入です。
名刺管理システムは名刺情報の管理に特化した機能を豊富に搭載しており、名刺情報をフルに活用する上で欠かせないシステムと言えます。
名刺管理システムには以下のようなメリットがあります。
・スキャナやアプリを利用して簡単にデータ化できる
・いつでもどこでも名刺情報にアクセスできる
・アクセスしたい名刺情報を簡単に検索できる
・商談内容などの関連情報を紐づけできる
・社内全体での共有や連携が簡単にできる
これらのメリットを見ていただくだけでも、名刺を活用する上で非常に役立つことがお分かりいただけると思います。
導入にある程度の費用は掛かりますが、一度検討してみてください。
まとめ
今回は名刺のもらい方にフォーカスしてお話してきましたが、いかがでしたか。当社は最後にご紹介した名刺管理システムである「ホットプロファイル」を、多くの企業様に提供させていただいております。
ホットプロファイルは名刺管理システムとしての機能だけに留まらず、営業プロセスやタスク管理機能といった、SFA(営業支援ツール)としての機能も搭載している点が特徴です。
「名刺管理含めた営業活動全体の効率化を図りたい」ということであれば、是非一度お問い合わせください。