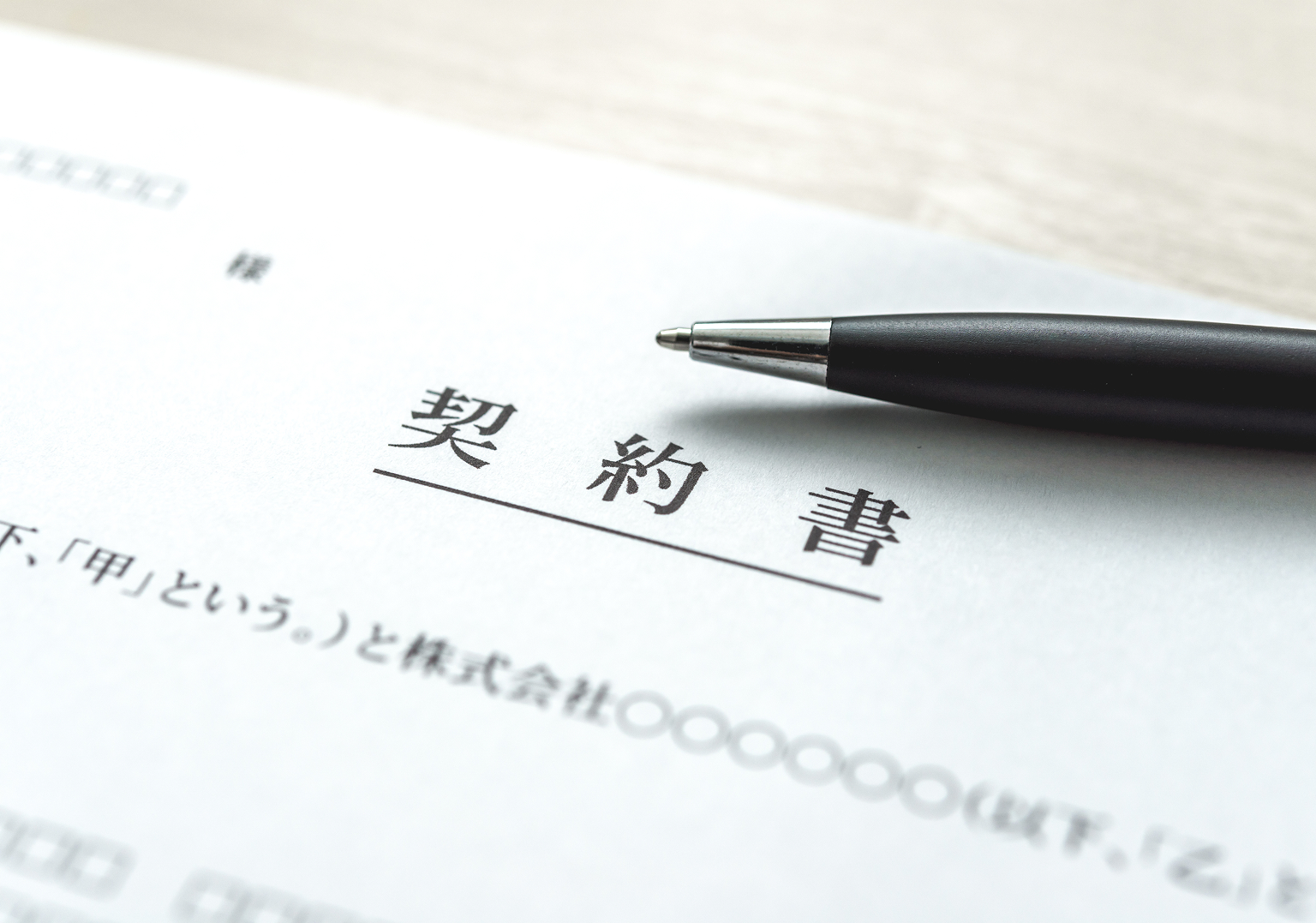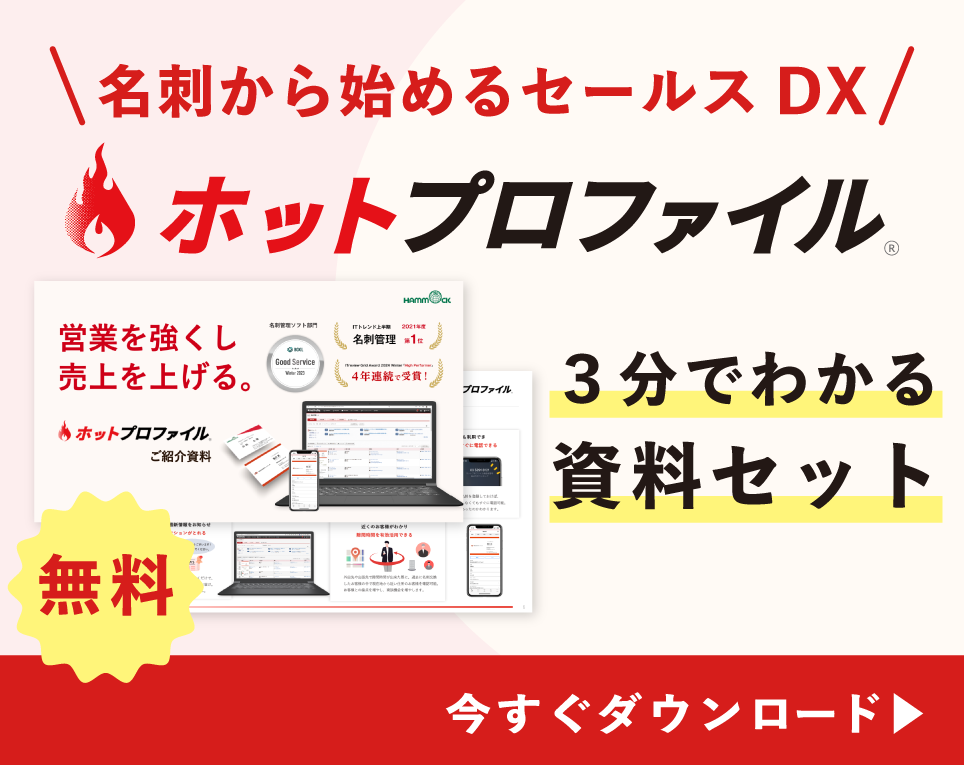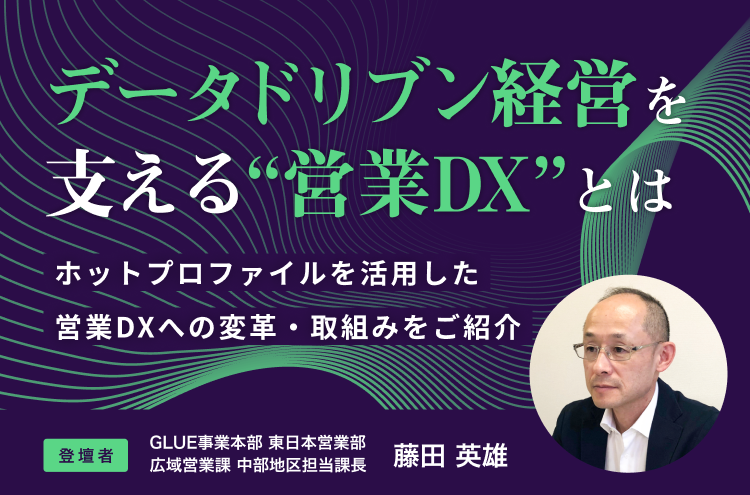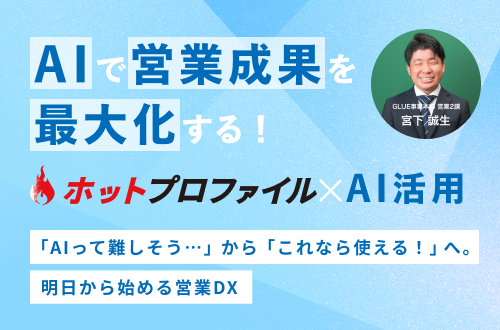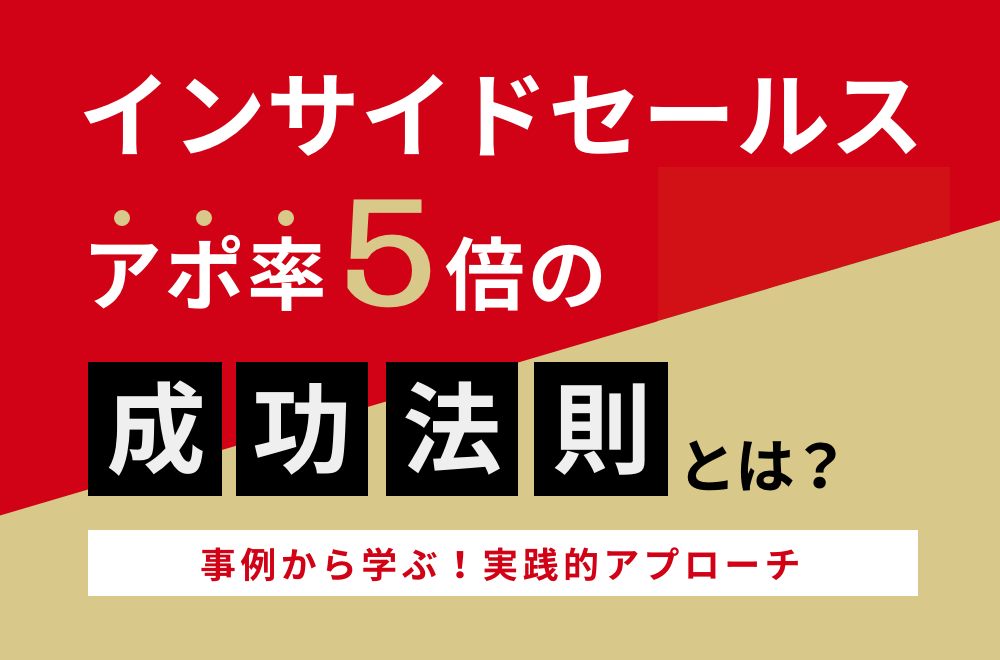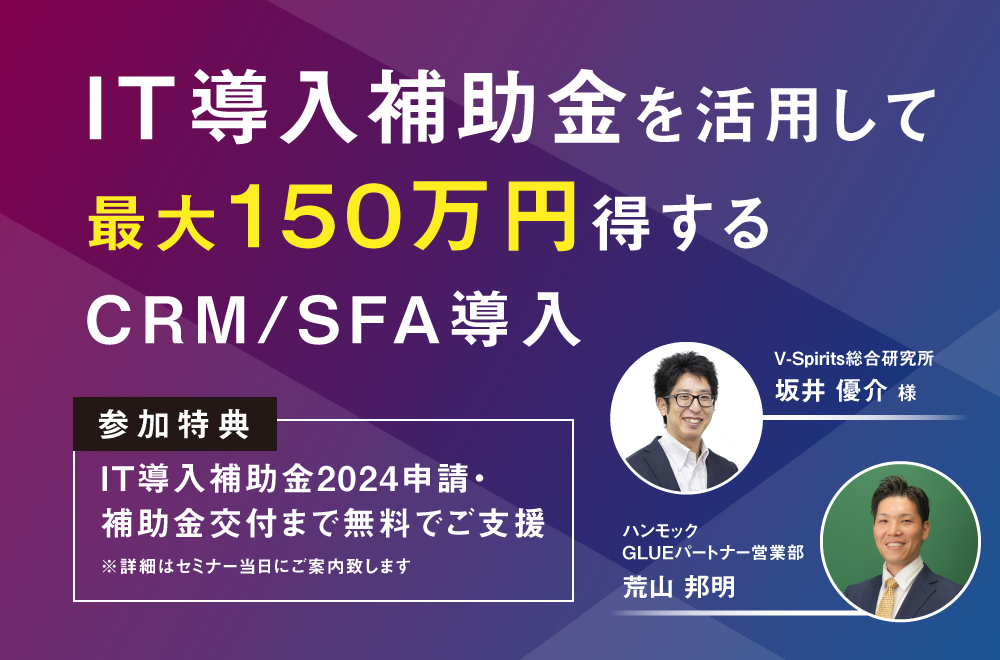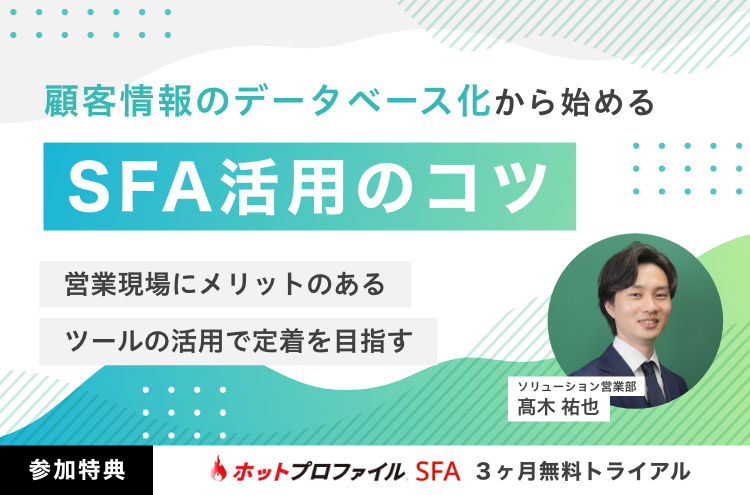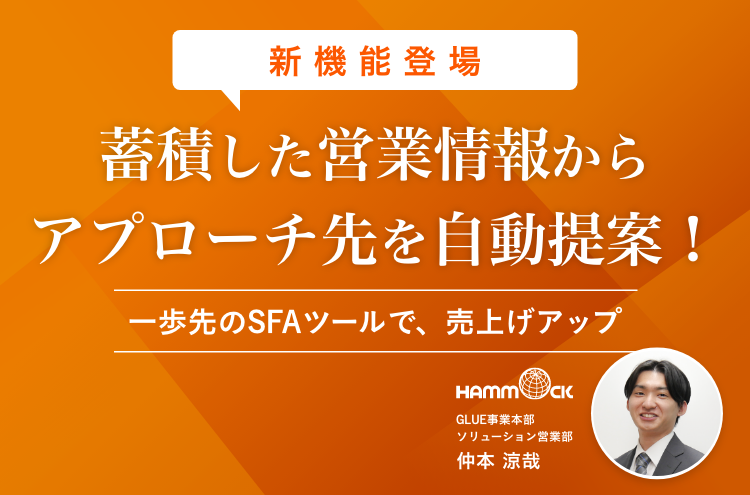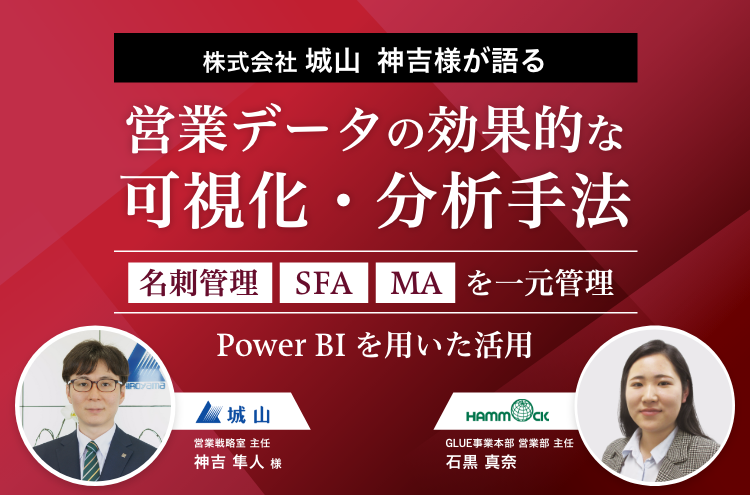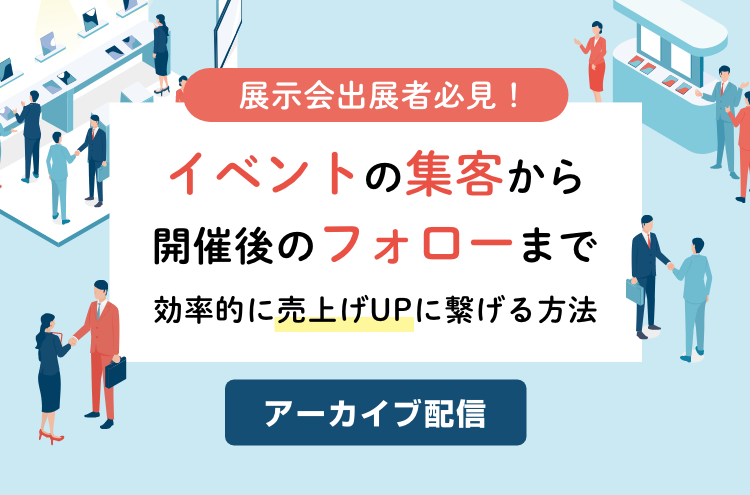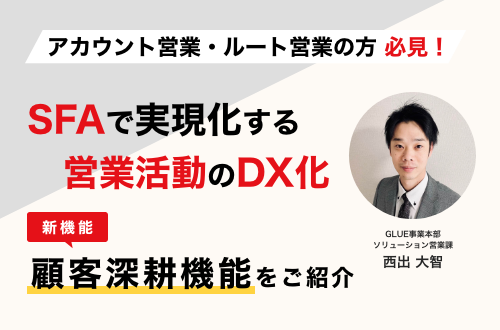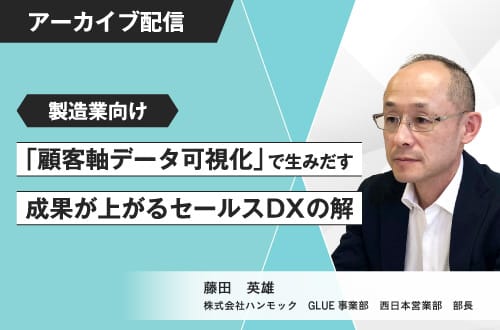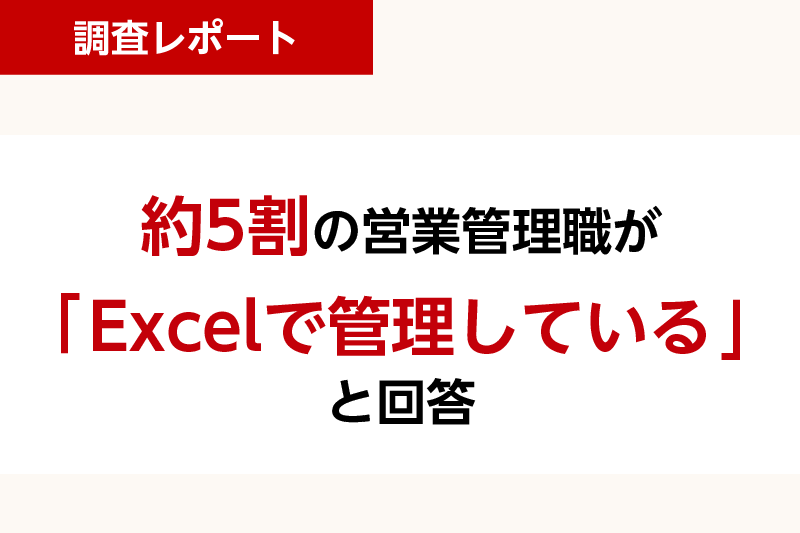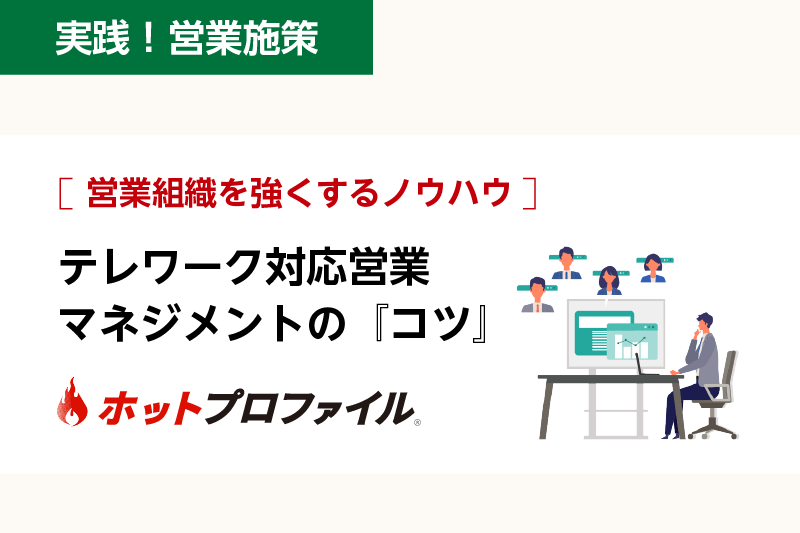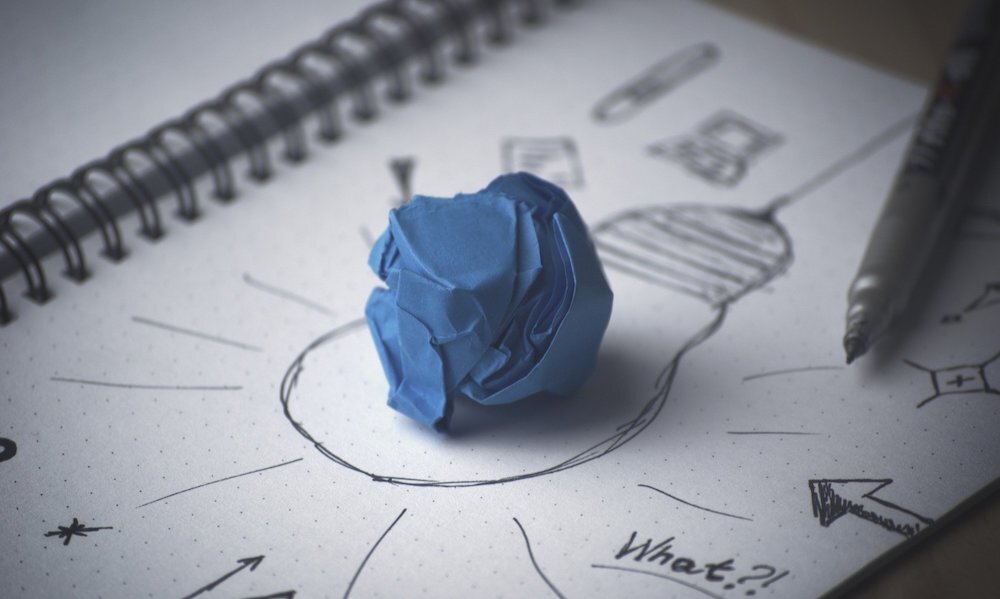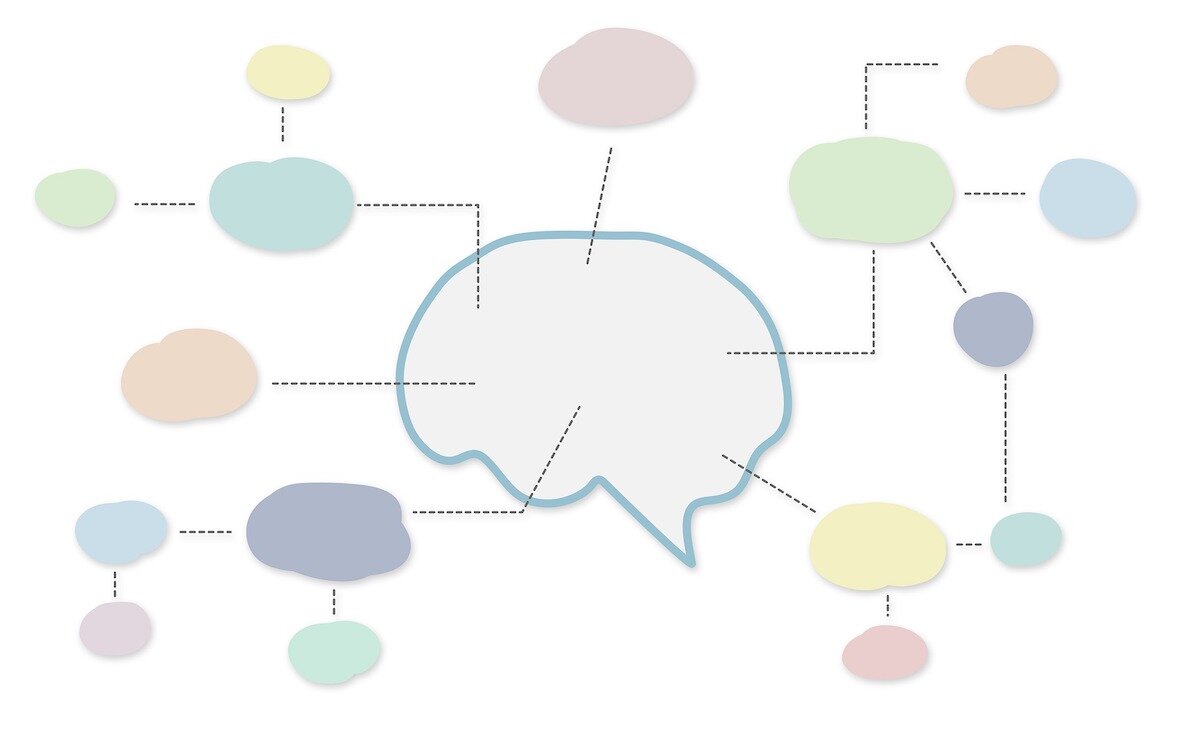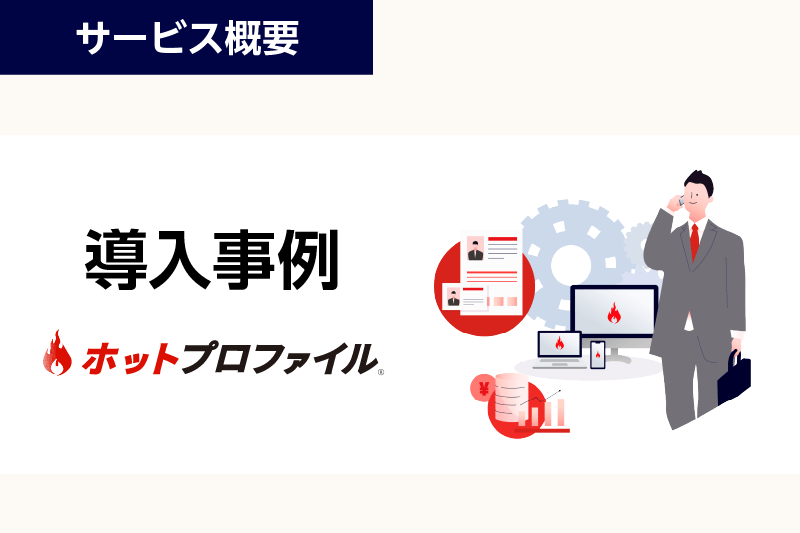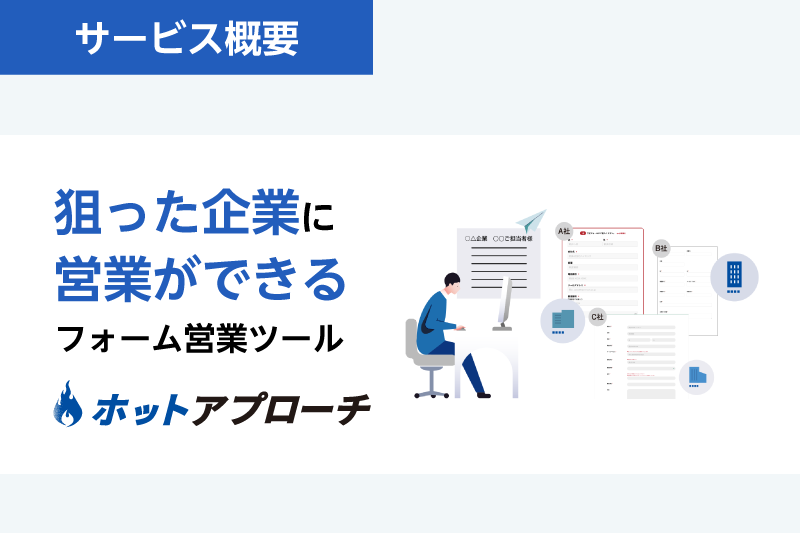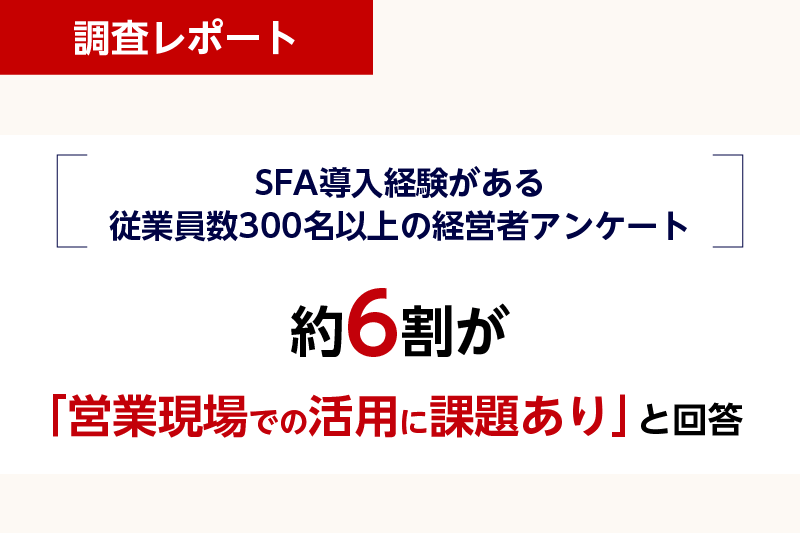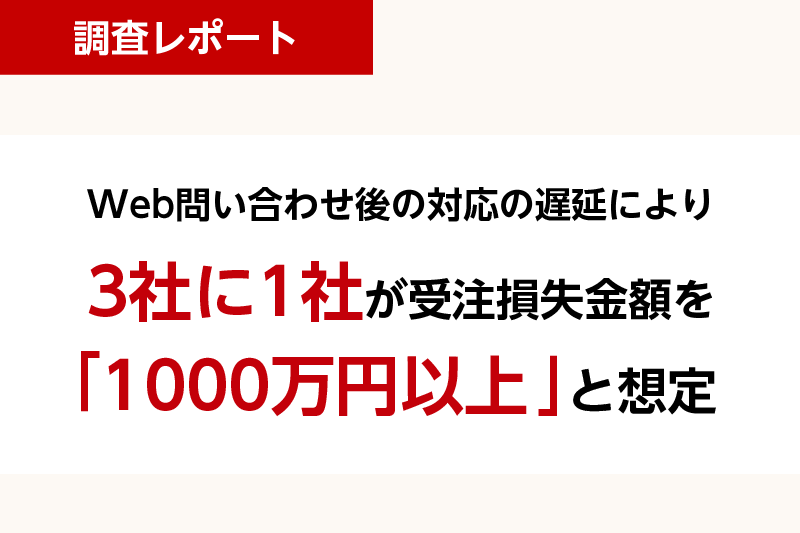【営業とマーケティング】その違いや連携のポイントなどをご紹介
- INDEX
-

貴方は営業とマーケティングの違いを理解できていますか。
この記事では営業とマーケティングの違いをご紹介した上で、両部門を連携させるメリットや方法まで解説しています。
営業とマーケティングの違いを理解した上で、しっかりと連携したいとお考えの方は是非最後までお付き合いください。
営業とマーケティングの違いとは
まずは営業とマーケティングにどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
違い①:役割
営業とマーケティングの違いとして、最も大きな違いはその役割です。それぞれの役割がどのようなものかをお話していきます。
・製品・サービスを売り込む営業部門
対して営業部門の役割は、シンプルに「自社の製品・サービスを見込み顧客に売り込むこと」です。
マーケティング部門が策定したターゲットに対して、どのように売り込むのかといった営業戦略を定めます。
基本はマーケティング部門が営業部門を包括する形となり、マーケティング戦略という前提のもとに活動していくこととなるでしょう。
・価値を生み出し、顧客との関係を構築するマーケティング部門
マーケティング部門は自社がターゲットとすべき見込み顧客像を明確にした上で、そのターゲットに対して提供すべき価値(製品・サービス)を策定し、それをどのようにして届けるのか、というマーケティング戦略を決める役割を担います。
さらに様々な施策を通じて、ターゲットである見込み顧客を獲得し、さらに購買意欲を醸成するためのコミュニケーションを実施していくことも、マーケティング部門の役割の一つです。
違い②:持つべき視点
二つ目の違いは持つべき視点です。・営業部門は短期的視点で活動する
その点、営業部門は決められた期間に一定の売り上げを上げることが求められます。
そのため半年から1年といった短い期間で、どのように見込み顧客を開拓していくのかといった思考が必要となるのです。
とはいえ短期間で開拓できないケースも往々にしてあるため、場合によっては長期的な視点で見込み顧客へのアプローチを行う必要も出てくるでしょう。
・マーケティング部門は長期的視点が必要
マーケティング部門は自社の提供すべき価値やターゲットを策定するとともに、顧客とコミュニケーションを図り、関係を構築していくことになります。
これらの活動にはある程度の期間がかかりますし、「ここまでやれば終了」といった類のものでもありません。
そのためマーケティング部門は長期的な視点を持ち、様々な活動の検討や実施をしていく必要があるのです。
違い③:コミュニケーションの対象となる顧客の購買プロセス
コミュニケーションの対象となる顧客の購買プロセスも異なります。
・比較検討~購買段階の顧客は営業部門
マーケティング部門の活動により購買意欲が醸成され、比較検討段階に達すれば、次は営業部門の出番です。
営業担当者が実際に見込み顧客へとコンタクトし、製品・サービスの特徴や独自の強みなどを説明したり、見込み顧客からの細かな質問などに答えたりすることで、契約締結まで結びつけます。
・認知~情報収集段階の顧客はマーケティング部門
認知や興味・関心、情報収集の段階にいる見込み顧客に対するコミュニケーションは、マーケティング部門が中心となって実施していきます。
認知段階にいる見込み顧客に対して、各種WEB広告やデジタルコンテンツなどを提供し、興味・関心や情報収集段階へと進んでもらうように、購買意欲の醸成を図っていくことになるでしょう。
違い④:求められるスキル
また求められるスキルも営業とマーケティングでは大きく異なります。
・コミュニケーション系のスキルが重視される営業部門
営業部門の仕事と言えば、見込み顧客との商談シーンが中心となるでしょう。
そのため顧客とのコミュニケーション能力を始め、ニーズや課題を聞き出すヒアリング力や購買を促すクロージング力が重視されるのです。
・高い分析力と企画力を求められるマーケティング部門
マーケティング部門は顧客に関する様々なデータや数値に基づいて、新たな製品・サービスやアプローチ施策の企画・展開を行います。
そのため高い分析力や、見込み顧客のニーズを的確に捉えた施策を検討する企画力が重要になるのです。
もっと知りたい! "ホットプロファイル製品情報" はコチラ >>

営業部門とマーケティング部門が連携するメリット
ここまで営業部門とマーケティング部門の違いについてお話してきましたが、ここからはそんな2つの部門が連携することで得られるメリットをご紹介していきます。
連携メリット①:業務効率が向上する
一つ目のメリットは業務効率が向上するという点です。
営業部門とマーケティング部門が連携できていない場合、同じ見込み顧客に重複してアプローチをしてしまっていたり、マーケティング部門から引き継いだ見込み顧客へのアプローチが漏れていたりと、無駄や機会損失を招くことになります。
しかし営業部門とマーケティング部門が連携を密にすることで、これらの無駄や機会損失を防ぐことができ、その結果として業務効率を向上させることができるのです。
連携メリット②:見込み顧客の信頼度を高めることができる
また連携することで見込み顧客の信頼度を高めることができます。
マーケティング部門がこれまで実施してきた見込み顧客とのアプローチ内容などを、正確に営業部門に伝えることで、営業部門からの提案もより効果的な内容となります。
そのため見込み顧客としても、「ちゃんとこれまでの話を踏まえて、提案してくれているんだな」といった印象を持ち、信頼を獲得することができるのです。
営業部門とマーケティング部門が連携するには
続いて、営業部門とマーケティング部門が連携する方法をご紹介します。
連携方法①:情報共有の仕組みを構築する
一つ目にご紹介する方法は「情報共有の仕組みを構築する」ことです。
営業部門とマーケティング部門の連携には、お互いの持つ見込み顧客に関する情報の共有は欠かせません。
しかし情報共有をすると言っても、担当者レベルで属人的に行っていては意味がないのです。
そのため部門同士での情報共有を実現する仕組みを、しっかりと構築することが必要と言えるでしょう。
連携方法②:部門横断的な部署を立ち上げる
また部門横断的な部署やプロジェクトチームを設置することも一つです。
部門横断的な部署やチームで、定期的な状況共有や意見交換といったミーティングを実施したり、そのミーティングの内容を基にして両部門へ提言を実施したりすれば、連携は一気に加速するでしょう。
営業部門とマーケティング部門を横断する機能を設けることは、両部門の連携を促進する上でとても効果的なのです。
連携を成功させるためのポイント
最後に営業部門とマーケティング部門の連携を成功させるためのポイントについて、お話しておきましょう。
連携を成功させるにはシステムを活用する
営業部門とマーケティング部門の連携をスムーズに行い、成功させるにはシステムの導入が不可欠と言えます。
先程両部門の連携には情報共有の仕組みを構築することが必要とお話しましたが、その際にカギとなってくるのがシステムというわけです。
具体的には営業支援ツールであるSFAや、マーケティング支援ツールのMAなどを導入することになるでしょう。
SFAやMAには顧客情報やアプローチ内容の管理に加え、Webサイト上の行動分析やWeb広告の効果測定といった、両部門の活動を支援する機能が多数搭載されています。
これらのシステムを導入し、両部門のメンバーが自由にアクセスできるようにすれば、お互いの持つ顧客情報やアクション状況などを、必要な時に参照することができるのです。
いずれのシステムも導入する上で費用こそ掛かりますが、両部門の連携を成功させたいのであれば、一度検討してみることをオススメします。
まとめ
今回は営業部門とマーケティング部門の代表的な違いを踏まえ、両部門が連携することのメリットやその方法などについてお話してきましたが、いかがでしたか。
当社は営業部門とマーケティング部門の連携にも役立つとご紹介した、SFAとMAの機能と連携可能な営業支援システム「ホットプロファイル」を、企業様に提供させていただいております。
両部門の連携だけでなく、それぞれの活動を効果的かつ効率的に実行していくために役立つ機能も多数提供しておりますので、ご興味のある方は是非お問い合わせください。
もっと知りたい! "ホットプロファイル製品情報" はコチラ >>