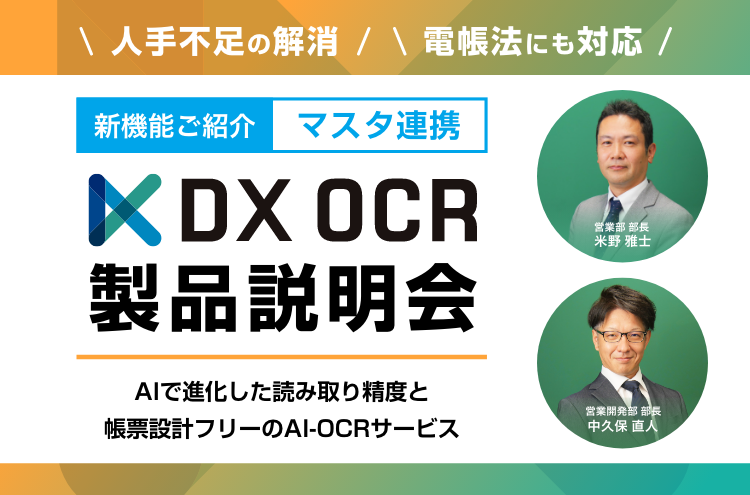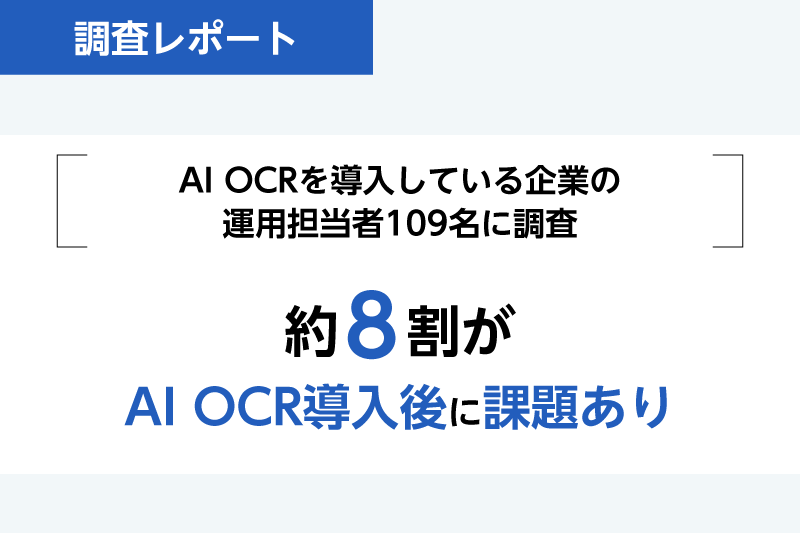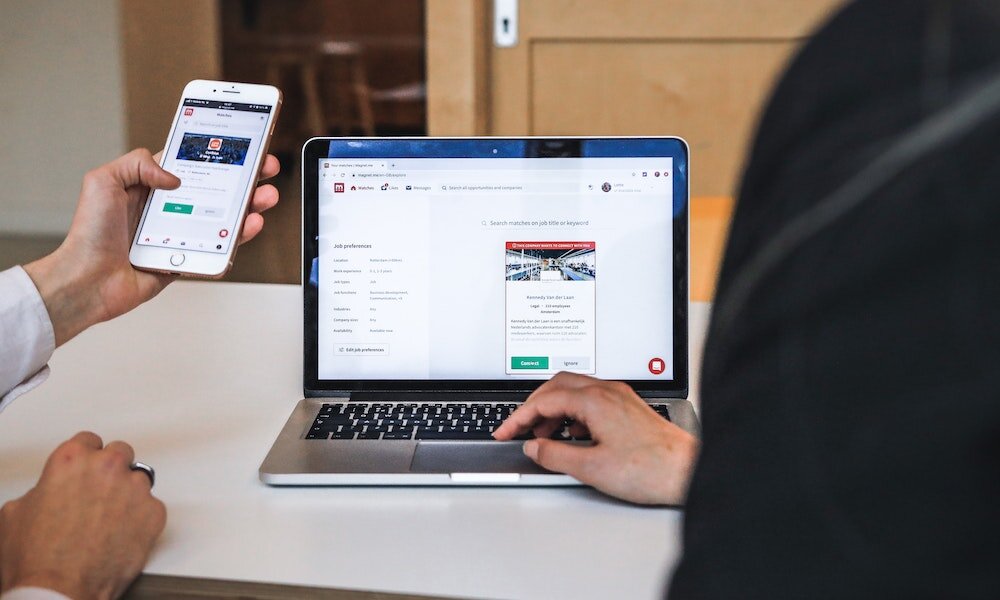生産性向上とは?業務改善するポイントがわからない時にチェックすべきこと
- INDEX
-

生産性向上や働き方改革、DXの推進など企業や組織として取り組むべき課題は山積みと言えます。
中でも生産性向上は概念や考え方としてわかりにくいこともあり、かつ具体的な行動につながりにくいことから、経営者や雇用主の悩みの種になりがちです。
今回は生産性向上に関する基礎知識や生産性向上と業務改善の関係性、そして業務改善するポイントがわからない時にチェックすべきことについてお話します。
生産性向上に関する基礎知識
はじめに生産性向上に関する基礎知識について簡単に説明します。
そもそも、生産性向上とは何か
総務省では生産性を定量的に示す指標として「労働生産性」という言葉を用いています。そして、厚生労働省では生産性の中で最も一般的なものとして「付加価値労働生産性」という言葉を用いて、「労働者1人が1時間でどれだけの付加価値を生み出したか」という形で生産性を数字で算出する計算方法を示しています。
どちらも一定の労働投入量において、どれだけ経済的な効果があったのかを具体的にするものであり、生産性の向上とはこれらの指標や数字をアップさせることと言えます。
これらのことから、生産性向上とは単なる標語ではなく、PDCAサイクルで言うところの評価、改善によって具体的な数値と改善をしていける要素であることがわかります。
厚生労働省:労働生産性の向上に向けた我が国の現状と課題
生産性向上はDXの推進と深い関わりがある
生産性の向上はDXの推進と深い関わりがあります。例えば、残業時間が多く、日々の疲れが抜けない状態では、肉体的にも精神的にも生産性が下がることは明白です。特に事務作業やバックオフィス系の業務はどれもが企業活動に必須の業務でありながら、生産性が高い仕事とは言えず、一昔前のアナログかつ古い作業手順であれば非効率で多くの時間を必要とします。
事務作業の主である目視によるチェックや人力でのデータ入力はOCRやFAXの電子化の導入によって、DXが推進され、短時間で事務処理が終わるようになり、同時に人的資源と時間的な資源の浪費を防ぐことにつながります。
また、少子高齢化や団塊の世代の引退および退職が重なることで、労働人口自体が少なくなっていることもあり、単に最適化や効率化を叫ぶだけではなく、DXを推進し、具体的に生産性を向上するための行動をとらなければならない時期に差し掛かっていることも理解しておかなくてはなりません。
生産性向上で従業員個人の負担は増える?
生産性向上は「生産性のある仕事に集中・従事する時間を増やすこと」が重要です。そのため、従業員個人の肉体的かつ精神的な負担を減らすことが前提となるため、生産性向上が進めば従業員個人の負担は減ります。
同時に、キャリアがあるから、ベテランだからと業務量が偏っており、一人に負担が押し付けられているような状況を改善する必要もあることから、作業の再分配によって負担を減らし、お互いがお互いを助けられる余力を持てるようになり、結果として誰もが無理をしない職場環境の構築にもつながります。
生産性向上と業務改善の関係性
次に生産性向上と業務改善の関係性について解説します。
業務改善とは既存の業務プロセスや作業手順の見直し
業務改善とは既存の業務プロセスや作業手順を見直し、結果的に生産性向上となるようにすることです。言い換えれば、生産性が向上しないのに業務プロセスや作業手順を見直しても意味がないと言えます。
実際にDXの推進をしたつもりが、前後の業務の担当者の負担が増えたり、業務全体のバランスが崩れることによって遅延や停滞が発生してしまうようなケースも存在します。そのため、言葉だけの業務改善ではなく、生産性の向上となる業務改善を行うことが求められます。
必ずしも効率化や最適化が生産性を向上させるとは限らない
業務改善と言えば、効率化や最適化という言葉が頻繁に出てきます。しかし、効率化や最適化においても、局所的に業務改善を行い、局所的に効果測定を行って改善できたとしても、必ずしも生産性を向上させるとは限りません。
例えば、テレワークの導入によって自宅で仕事ができるようになり、ライフワークバランスが整ったことで、生産性が向上する人もいます。その反面、テレワークよりも出社した方が効率的であり、生産性が向上する人もいるため、テレワークで生産性が上がる人、下がる人がいるように局所的に生産性が向上するだけではプラスマイナスゼロ、もしくはマイナスになることもあるでしょう。
テレワークのように業界や業種によって異なる点も理解しておこう
生産性が向上するとされる施策が業界や業種によって異なる点も理解しておくべきと言えます。そもそも、テレワークが導入できない業界や業種もありますし、同様にDXの推進となる技術には相性があるということです。
古くアナログで非効率と思われているような作業手順をDXの推進によって一手間も二手間も増やしてしまい、導入や運用が上手くいかずに遅延や停滞が発生し、結果としてより多くの時間を要してしまっては意味がないということも忘れてはいけません。
これらのことから、生産性向上のための業務改善は特効薬のようなものは少なく、手探りで見つけなければならず、業界や業種問わず苦慮しているのが理解できると言えます。

業務改善するポイントがわからない時にチェックすべきこと
次に、業務改善するポイントがわからない時にチェックすべきことをご紹介します。
従業員ごとの残業時間・業務量/作業量・責任区分の精査
まずは従業員ごとの残業時間・業務量/作業量・責任区分を精査し、偏りがないか、属人化していないかをチェックしましょう。誰か一人に負担が押し付けられていないか、またはほとんどの人が残業していないのに、誰か一人が残業しているような状況が無いかなど見ておくべきです。
同時に事務作業やバックオフィス系の業務は定量による評価がしにくいこともあるため、実際の作業や業務をしている勤務状況をチェックし、誰が忙しいのか、誰が暇をしているのかを把握しましょう。
生産性の向上を前提とした効率化・最適化による事務や作業の手順の見直し
生産性の向上を前提とした効率化・最適化を行うためにも次の段階として業務量や作業量の再分配、必要に応じて人員の再配置を行うべきです。その上で事務や作業の手順の見直しを行いましょう。目視によるチェックや人力でのデータ入力など、OCRやFAXの電子化、ペーパーレス化で事務作業の負担を軽減できるのであれば、作業手順の見直しとともに業務プロセスの再構築も行うべきです。同様にデータの一元管理、適切な権限によるデータの共有を行い、今まで人員や時間を多く必要とした作業や業務のスリム化を進めるのがおすすめです。
DXの推進が実務や現場レベルで具体的に進んでいるかどうか
・OCRによる紙の帳票のペーパーレス化
・FAXを用いる業務の電子化およびペーパーレス化
・電子化やペーパーレス化、データ化した情報の一元管理
・FAX送受信を基幹システムと連携
・その他、マーケティングツールやRPAとの連携できるシステムの導入
上記は事務作業やバックオフィス系業務におけるDXの推進となる技術の一例です。どれもがデータの入力や転記、目視によるチェックなど人員が必要な作業や業務の負担を低減する仕組みと言えます。同時にどれもが作業や業務に要する時間を大幅に削減する仕組みです。
これらの技術が実務や現場レベルで利用されているか、未導入でないかなどをチェックし、積極的、活用することに注力しましょう。
まとめ:一昔前の事務作業やバックオフィス系業務から脱却しよう!
今回は生産性向上に関する基礎知識や生産性向上と業務改善の関係性、そして業務改善するポイントがわからない時にチェックすべきことについてお話しました。
生産性を向上させたいのであれば、既存の事務作業やバックオフィス系の業務から脱却する必要があります。例えば、一昔前であれば人力かつ頭数を揃えることで対応していたような業務全般と言えます。もちろん、必ずしもITやICTに置き換えることができない業務もありますが、置き換えられるもの、任せられるものは機械に任せて、まずは「生産性のある仕事に集中できる時間の創出」を行いましょう。
当社の提供する帳票のデータエントリー業務を効率化するソリューション「DEFACT」シリーズであれば、企業活動における帳票を要する事務作業の負担を軽減することができます。帳票に要した人員・時間・人的コストを低減し、社内や組織における大切な人材を活かすことにもつながりますので、ぜひともこの機会にご相談、お問い合わせください。