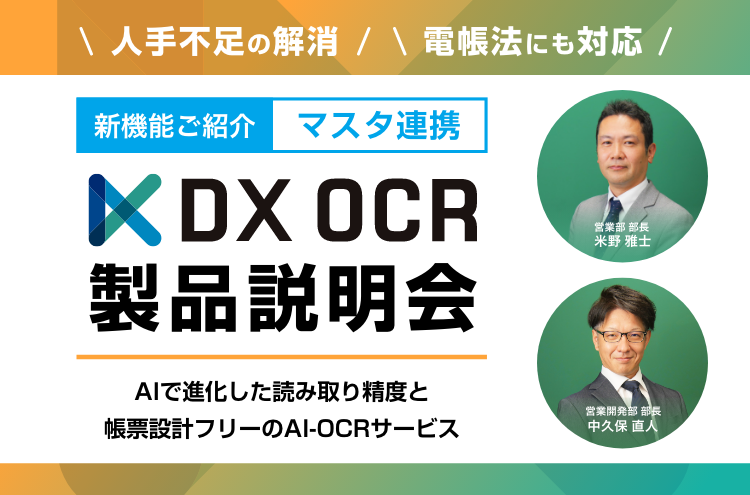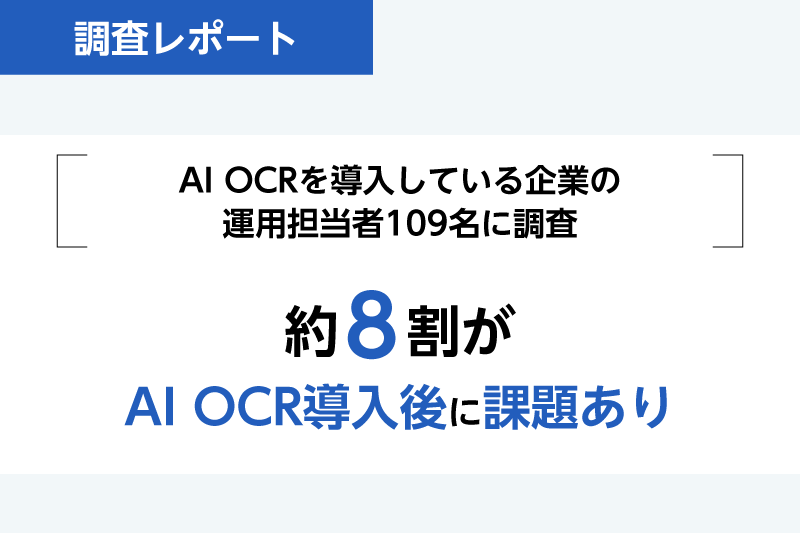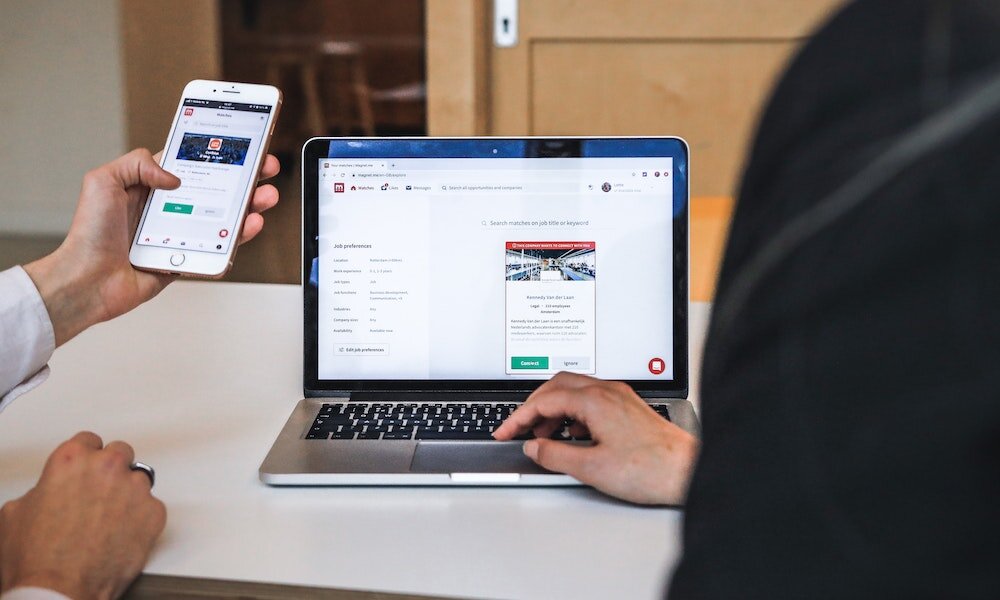ペーパーレス化を浸透させる方法や理解を深めてもらうための方法や考え方について
- INDEX
-
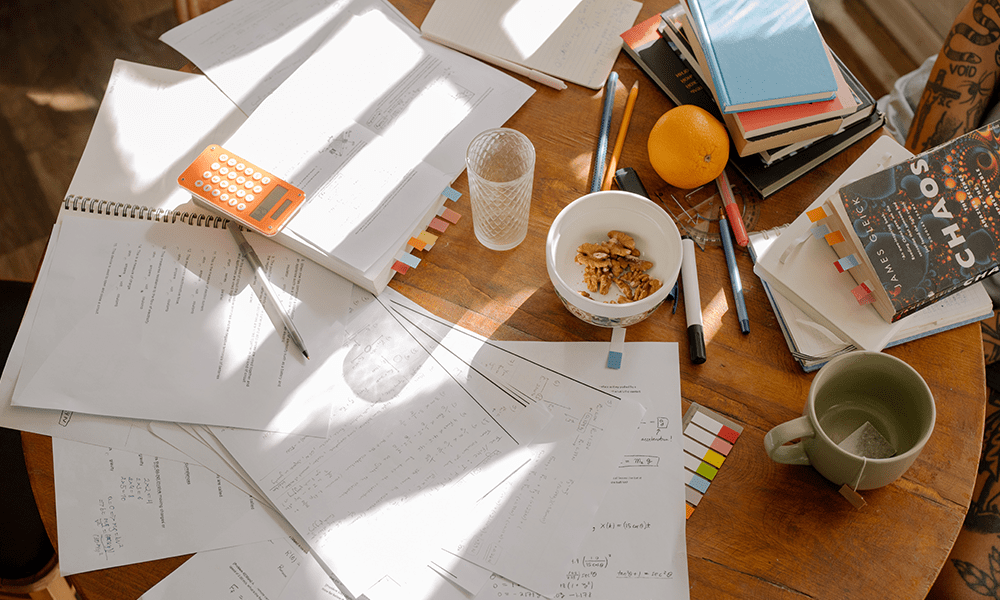
その他にもペーパーレス化の導入そのものの意義を理解してもらえず、検討する段階で停滞してしまうケースも現実問題として存在するのも事実です。
今回は、ペーパーレス化を浸透させる方法や理解を深めてもらうための考え方、さらに過去に導入したOCRが原因でOCRを使ってもらえないケースの対処法についてご紹介します。
ペーパーレス化を浸透させる方法
はじめにペーパーレス化を浸透させる方法について簡単に説明します。
誰もがOCRを利用できるように環境を整える
OCRは文字を認識する技術であり、誰もが利用できる技術です。企業や組織の業務において生じる請求書や注文書、各種伝票などの帳票をOCRで読み込むことで電子化およびデジタル化し、ペーパーレス化を可能にします。
もちろん、特定の部署や部門など必要に応じて配置すべき技術でもありますが、日常的に行う業務において、紙ベースの帳票を目視によるチェックと手入力でデータ化する煩雑な作業があるのであれば、積極的にOCRに切り替えていくことが大切です。一昔前で言うところのFAXやコピー機と同様に、要不要ではなく、誰でも扱えるようにすることで、日々蓄積されがちな事務作業の一部を低減することができます。
段階的にペーパーレス化することが大事
ペーパーレス化は段階的に行うことが大事です。いきなり部門や部署を問わずにペーパーレス化するのではなく、まずは経理や精算の関わる部門や部署から、もしくは受発注業務に関連する担当からなど、範囲を決めて徐々に拡大するようにしましょう。
実際に同僚がOCRを使い始めることで、OCRがどれだけ便利かを社内で共有することにつながります。同時にペーパーレス化したデータを一元管理し、共有や活用するための基盤を整えることも大切です。せっかくデータ化したのに活用できない、または特定の部門や部署でしか使えないのはもったいないということも覚えておきましょう。
ペーパーレス化しにくい部分を無理にペーパーレス化しない
ペーパーレス化の課題でもありますが、ペーパーレス化しにくい部分を無理にペーパーレス化しないことも大切です。例えば、顧客からデータを受け取る、または顧客にデータを受け渡す部分など「紙からデータ」や「データから紙」となる部分はペーパーレス化しにくい場合があります。顧客やユーザーが紙ベースの方が良ければ、紙ベースの部分も残しておくようにしましょう。
また、データを受け取る部分はWeb注文やフォームからの送信など入力自体をオンライン化することもできますし、データを受け渡す場合もメールやメッセージに切り替えることもある意味ペーパーレス化ですので、OCRでなければならない、または紙に印刷しなければならないという固定観念を捨てることも時には大切です。
ペーパーレス化への理解を深めてもらうための考え方
次にペーパーレス化への理解を深めてもらうための考え方をご説明します。
ペーパーレス化がDXの推進の基盤となることを周知
ペーパーレス化が浸透しない、または普及しない理由に「仕事がなくなる」という誤解があります。実際には現在のIT技術であれば、やらなくて良い作業を無理やり人力で行っているケースも少なくなく、IT技術の導入によって「仕事を奪われる」というような意識がDXの推進を阻んでいることを理解してもらいましょう。
もちろん、ハンコや押印の廃止となれば、ハンコを押すのが仕事だった人は一時的に仕事が減るかもしれません。OCRによって紙ベースの帳票を簡単にデジタル化できるようになれば、入力業務を行っていた従業員の仕事は一時的に減るでしょう。しかし、DXの推進は「IT技術によって楽をする」ことも目的であり、やらなくていいことをやり続けるのではなく、同じ企業内でより生産性のある仕事に従事できるチャンスであることを理解してもらうようにしましょう。
これからの時代にペーパーレス化が標準になることを周知
一昔前であれば事務員がたくさんいて、膨大な伝票を事務処理するのが当たり前だったかもしれません。しかしこれからはペーパーレス化が標準になる時代と言えます。なぜ、ペーパーレス化が標準になるかと言えば、紙に記載されている情報は電子的に扱いにくく、わざわざ目視によるチェックと人力の手入力でデジタル化しなければ使いものにならないからです。
ペーパーレス化は紙ベースの帳票を目視によるチェックや人力で手入力する労力を省き、はるかに短い時間で情報を読み込んで自動的に分類、データベースに登録されます。OCRを導入し使いこなしている企業や組織であれば、事務作業のための人的リソースやコストが大幅に削減され、事務作業における労力を格段に軽減できるということです。働く側としても煩雑な事務作業が削減されることを受け入れること、生産性のある仕事に従事できるということを受け入れた方が良い時代になるということです。
ペーパーレス化は難しくないことを理解してもらう
DXの推進、ペーパーレス化、デジタル化など、言葉だけを見ると何やら難しそうに感じる人も少なくありません。また、OCRが難しい技術であるという誤解、ペーパーレス化は難しいと考えてしまう方もいらっしゃいます。しかし実際には、ペーパーレス化は難しい作業や業務ではありません。
OCRやペーパーレス化は、業務に対応するためにパソコンを利用している方であれば誰にでも使いこなせる技術であると理解してもらうことが大切です。実際、使い方さえ覚えれば、今まで手入力で10分、20分とかかっていたような事務作業が最終的なチェックを含めても2、3分で完了します。一昔前でいうところのFAXやコピー機、またはエクセルやワードに慣れていくのと同じように、すぐに当たり前に使いこなせるようになるということも理解してもらいましょう。
導入したOCRが原因でOCRを使ってもらえないケースの対処法
次に、導入したOCRが原因でOCRを使ってもらえないケースの対処法についてご説明します。
OCRのデバイスやツール、ソフトウエアの課題や問題点を把握
まずはOCRのデバイスやツール、ソフトウエアの課題や問題点を把握しましょう。OCRによるペーパーレス化が進まないのは「OCRは面倒」や「OCRは使えない」という考えになってしまう原因や理由があるためです。
例えば、使い方がわからない、自分も使って良いのかわからないというレベルであれば、誰でも使えるようマニュアルを用意したり、OCRの利用を推奨するような通達などを出すことをおすすめします。
それぞれの現場や担当が使いやすいOCRを探そう
OCRによるペーパーレス化はバックオフィス系の事務作業というイメージがありますが、実際には各種現場ベースでもOCRを利用することは可能です。部署や部門ごとに異なる帳票が存在している場合でも、対応できるOCRを選ぶことで、それぞれの現場や担当が使いやすいOCRとして浸透しやすくなります。
基本的には外部から受け取る帳票をOCRによって読み込むことでペーパーレス化が推進されます。請求書や注文書、納品書など各部門や部署ごとに異なる場合でもデータ化することができますので、幅広い範囲でOCRが使えるように周知することも大切です。
OCRのツールやソフトウエアが原因なら乗り換えも視野に
古いOCRや業務体系に合わないOCRツールの場合は精度が低かったり、帳票に対応できなかったりと、「使えない」と思われてしまうこともあります。読み込んだのにエラーが多かったり、手直しが多ければ、手入力した方が早いと言う方もいるかもしれません。
その場合は、OCRのツールやソフトウエアを乗り換えることも視野に入れましょう。現在ではOCRの精度は格段に向上し、備えている機能による差はあるものの、実務レベルで十分使えるツールやソフトウェアも増えています。既存のOCRで物足りない、対応できない場合は、早い段階で乗り換えることをおすすめします。
まとめ:ペーパーレス化が「当たり前」になるように工夫しよう
今回はペーパーレス化を浸透させる方法や理解を深めてもらうための考え方、そして既に導入したOCRが原因でOCRを使ってもらえないケースの対処法についてご紹介しました。
ペーパーレス化が浸透しないのはOCRに対する誤解か、OCRが使えないという思い込みによる可能性が高いです。実際にはOCRは誰でも使える、ペーパーレス化は便利なだけでなく「楽」であることも理解してもらい、当たり前となるように工夫することが大切です。
もし、既に導入したOCRの精度や機能に満足できていない場合は、当社の提供する「AnyForm OCR」をおすすめします。高い読み取り精度と現場ベースでも馴染みやすいユーザーインターフェースや機能を備えており、さまざまな帳票に対応できる仕組みもありますので、ぜひともこの機会にご相談、お問い合わせください。