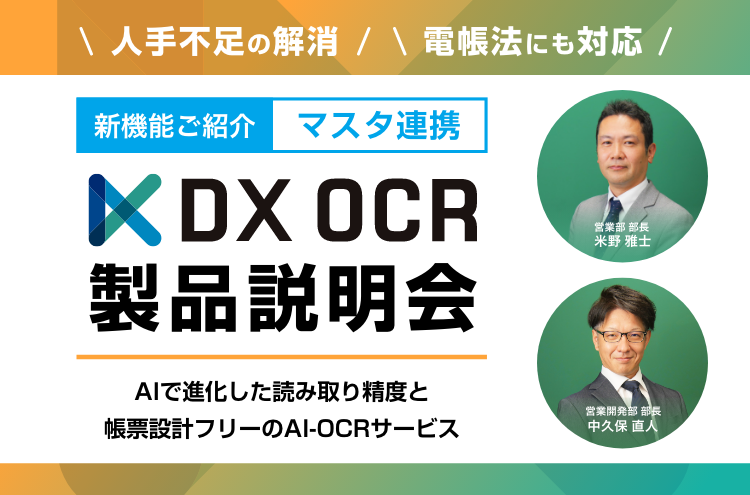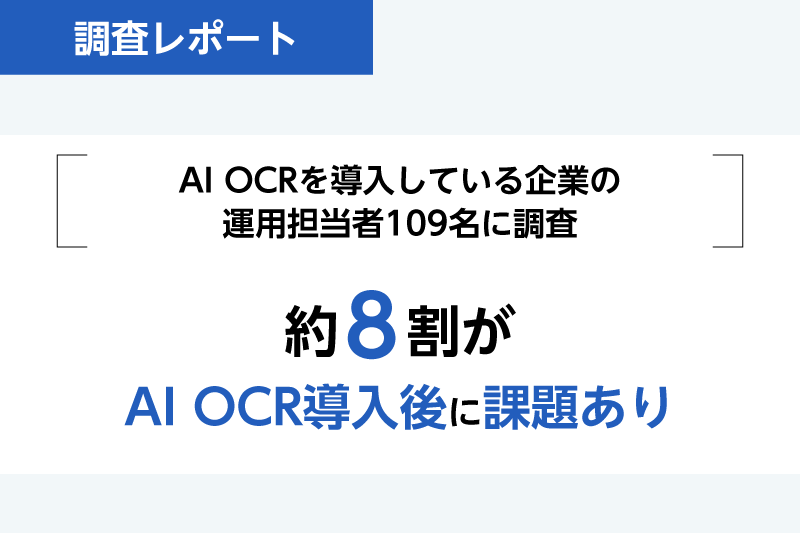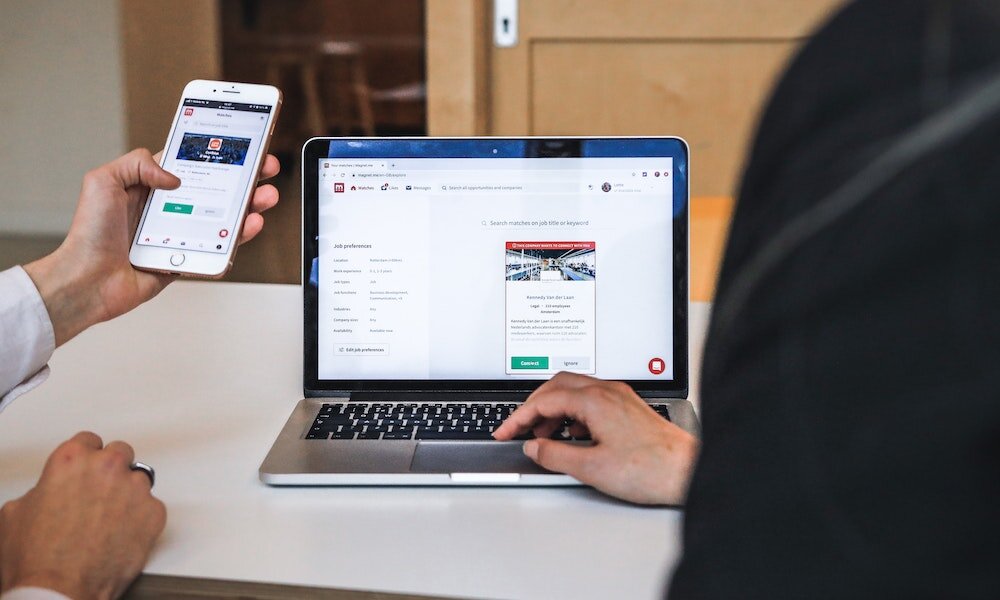業務プロセスを見直すべき理由と改善ステップ|可視化・効率化・DXへの道筋
- INDEX
-

業務プロセスとは、企業が業務目標を達成するために一連のタスクや活動を体系立てて構成した"流れ"のことを指します。業務効率化やDX推進の観点からも、業務プロセスの見直しは重要な課題となっています。しかし「業務フローとの違いが曖昧」「改善したいがどこから着手すべきかわからない」と感じる方も少なくありません。
本記事では、業務プロセスの定義や業務フローとの違い、改善の必要性、具体的な可視化手法やツールの活用方法までを網羅的に解説します。自社の業務課題を明確にし、生産性の高い組織運営へとつなげるための第一歩を踏み出しましょう。
業務プロセスとは
企業が目標を達成するためには、日々の業務をスムーズかつ効率的に進めることが不可欠です。そこで重要となるのが「業務プロセス」の考え方です。業務プロセスを理解し、可視化・改善していくことは、組織全体の生産性を高め、持続的な成長を支える基盤づくりにもつながります。この章では、業務プロセスの基本的な定義や似た概念との違いについて整理していきましょう。
業務プロセスの定義と意味
業務プロセスとは、企業が製品やサービスを提供するために行う一連の業務の流れを指します。たとえば、受注から納品、アフターフォローに至るまでの業務が、ひとつの業務プロセスと捉えられます。
このプロセスは単なる作業の羅列ではなく、「誰が」「何を」「どの順番で」「どのように」行うのかを体系的に捉えたものです。目的達成のために業務を連携させ、効率的に運用する仕組みといえるでしょう。
企業によって業務の内容は異なりますが、業務プロセスの概念を正しく理解することで、課題の見える化や改善の手がかりを得ることができます。
業務フローとの違い
「業務プロセス」と似た言葉に「業務フロー」がありますが、両者は厳密には異なる意味を持ちます。
業務フローは、業務の流れを図や表で視覚的に表したものを指し、どちらかといえば「見せ方」に重きを置いたものです。一方で、業務プロセスは「業務そのものの構造」や「業務間の関係性」にまで踏み込んだ概念です。
つまり、業務フローが業務の"見取り図"だとすれば、業務プロセスはその"設計思想"や"仕組みそのもの"にあたると捉えると分かりやすいかもしれません。
両者を併用することで、可視化と改善の両面からアプローチできるようになります。
ビジネスプロセス/業務工程などの言い換え表現
業務プロセスは、文脈によって「ビジネスプロセス」や「業務工程」といった言葉で表現されることもあります。これらはいずれもほぼ同義で使われるケースが多く、どれも業務の流れやその構造を表す言葉です。
ただし、使われる場面によって若干ニュアンスが異なる場合もあるため、注意が必要です。
たとえば「ビジネスプロセス」は経営的視点を含む広い意味合いで用いられることが多く、「業務工程」は製造業などの現場作業を連想させることもあります。とはいえ、根本的な意味合いは近いため、用語の違いに過度にとらわれすぎず、本質を捉えることが重要です。
業務プロセスを改善すべき理由
業務プロセスは、企業活動の土台となる部分です。普段あまり意識されないこともありますが、業務の質やスピード、ミスの発生頻度、そして社員の働きやすさにも深く関わっています。この章では、なぜ今あらためて業務プロセスの改善が求められるのか、その背景と目的を掘り下げていきます。
業務効率の向上と無駄の排除
業務プロセスを見直す大きな目的の一つは、「時間の無駄」や「重複作業」を減らし、全体の効率を高めることです。
たとえば、同じ情報を複数の担当者が別々に入力していたり、確認作業が過剰だったりする場面は少なくありません。こうした非効率は、コストや人材リソースの浪費につながります。
業務プロセスを改善することで、こうした無駄を洗い出し、必要な手順とそうでないものを見極めることができ、結果として業務のスピードアップとコスト削減が可能になります。
属人化の防止と標準化の推進
ある業務が特定の社員だけに依存している状態、いわゆる「属人化」は、組織にとって大きなリスクです。その人が異動や退職をした途端に、業務が滞ってしまうというケースは決して珍しくありません。
業務プロセスを見える化し、明文化しておくことで、誰が担当しても一定の品質で業務が遂行できる「標準化」が進みます。これにより、引き継ぎの負担も軽減され、組織全体の安定性と柔軟性が高まります。
リスクマネジメントと内部統制
業務プロセスの整備は、企業のガバナンス強化にもつながります。
たとえば、承認フローが曖昧だったり、チェック体制が不十分だったりすると、不正やミスが発生しても気づけない恐れがあります。あらかじめ業務の流れと責任範囲を明確にすることで、こうしたリスクを抑制し、監査対応や内部統制の観点でも有効に機能します。
特にコンプライアンスが重視される現代において、業務プロセスの透明性は企業の信頼性に直結するといえるでしょう。
DX・働き方改革との関連性
業務プロセスの改善は、DX(デジタルトランスフォーメーション)や働き方改革の実現にも深く関係しています。
業務の現状を整理し、可視化・最適化したうえで初めて、ITツールの導入や自動化を効果的に行うことが可能になります。逆に、プロセスの整備を行わずにツールだけ導入しても、かえって混乱や属人化を招くリスクがあります。
また、業務のムダをなくすことで、社員の時間に余裕が生まれ、より創造的な業務や顧客対応に集中できる環境も整います。これは企業だけでなく、働く一人ひとりにとっても大きなメリットといえるでしょう。
業務プロセスの可視化とは
業務プロセスを改善する第一歩として欠かせないのが「可視化」です。普段行っている業務が、どのような流れで、どの部署や担当者に関わっているのかを見える形にすることで、課題や非効率な部分が明確になります。この章では、可視化の目的やメリット、プロセス図の種類や作成方法について解説していきます。
可視化の目的とメリット
業務プロセスを可視化する目的は、「全体像を明らかにし、改善につなげる」ことにあります。
組織の中では、自分の担当する業務しか見えていないことが多く、他部門の動きや全体の流れを把握できていない場合もあります。業務プロセスを可視化することで、業務の重複、手戻り、ボトルネックとなる箇所などが見えてきます。
さらに、客観的な視点で業務を見直すきっかけになり、社員同士の認識のズレをなくす助けにもなります。
プロセス図と業務フローチャートの違い
業務を可視化する手段として代表的なのが、業務フローチャートやプロセス図といった図表です。これらは一見似ているようでいて、活用の目的や記述内容に少し違いがあります。
業務フローチャートは、業務の流れを工程ごとに直線的・手順的に描いた図で、主に「処理の順番」や「判断の分岐」を視覚的に表現するのに適しています。
一方で、業務プロセス図は、業務間のつながりや担当者ごとの動きも含めて、より全体的・構造的に業務を整理する目的で使われます。部署間連携や複数の視点から業務を見る際には、プロセス図の方が適しているといえるでしょう。
業務プロセス図の基本的な書き方と図形の使い方
業務プロセス図を作成する際は、いくつかの基本ルールを押さえておくと、誰が見ても理解しやすい図になります。
例えば、業務の開始点と終了点は「楕円形」、作業は「長方形」、判断が必要な分岐は「ひし形」といった形で表すのが一般的です。これらの図形を使い分けながら、業務の流れに沿って矢印でつなげていきます。
重要なのは、実際の業務に忠実であること、そして第三者が見てもすぐに内容を把握できるように、簡潔で明瞭な表現を心がけることです。
スイムレーン図の活用と設計ポイント
業務プロセス図の中でも、特に部門間や担当者間の役割分担を明確にしたい場合に有効なのが「スイムレーン図」です。
スイムレーン図では、各部門や担当者を"レーン"に見立てて業務を横断的に配置することで、誰がどの業務をいつ行うのかが一目で分かるようになります。
この図を使うことで、部門間のやりとりや情報の受け渡しポイント、ボトルネックの所在が明確になります。プロセス改善に取り組む際には、最初の現状把握フェーズでこの図を活用する企業も多く、特に複数部門が関与する業務においては欠かせない可視化ツールです。
業務プロセス改善の具体的な手順
業務プロセスの改善は、一度の見直しで終わるものではなく、段階的に進めていくことが成果につながります。やみくもに改善を図るのではなく、現状の把握から検証までを体系的に行うことが重要です。この章では、業務プロセス改善を成功に導く6つのステップをご紹介します。
STEP1:現状の業務をヒアリング・洗い出し
まずは、現状の業務内容を正確に把握するところから始めます。現場の担当者にヒアリングを行い、実際にどのような業務が、どのような流れで行われているのかを一つひとつ洗い出していきます。
ここでは「理想的なフロー」ではなく、実際に日常的に行われている"リアルな流れ"を可視化することが大切です。形式的な資料だけでは見えてこない、属人的な作業や例外対応も丁寧に拾い上げましょう。
STEP2:業務プロセスを可視化する
ヒアリングで得られた情報をもとに、業務プロセス図やスイムレーン図などを活用して業務の流れを図式化します。
図にすることで、全体像や業務のつながり、各工程にかかる時間や負荷の偏りなどが明確になります。業務の重複、処理の滞留、ムダな手順なども、この段階で発見しやすくなります。
また、チーム内での共通認識の形成にもつながり、後工程での合意形成がスムーズになるというメリットもあります。
STEP3:業務プロセスの課題を抽出し、改善ポイントを明確化する
可視化された業務フローをもとに、どこに課題が潜んでいるのかを洗い出します。
たとえば「業務が特定の担当者に偏っている」「確認作業に時間がかかりすぎている」「入力ミスが頻発している」といった問題点を整理し、それぞれの根本原因を探っていきます。
ここでは、「何が問題なのか」だけでなく、「なぜその問題が発生しているのか」という背景まで掘り下げることが肝心です。
STEP4:改善策を検討し、優先順位を決める
課題が明らかになったら、次は改善策の検討に移ります。
すべての問題に一度に対応しようとすると、現場の負担が大きくなり、プロジェクトが頓挫してしまう恐れもあります。そのため、改善施策には優先順位をつけ、効果の大きいものや早期に着手しやすいものから実行していくのが現実的です。
また、改善によるコスト削減効果や人的負担の軽減度など、定量的な視点も交えて施策を評価しておくと、社内での合意形成がしやすくなります。
STEP5:改善策を実行する
決定した改善策を現場で実行に移します。
たとえば、ワークフローの簡略化や、手作業の一部を自動化するツールの導入、業務分担の見直しなどが代表的な施策です。
この段階では、現場の理解と協力が不可欠です。無理な変化を押しつけず、現場の意見を反映させながら進めることで、スムーズな導入と定着が期待できます。
STEP6:効果検証とPDCAサイクルの運用
改善を行った後は、必ずその効果を検証しましょう。
改善前と後で業務の所要時間やミスの発生件数に変化があったか、担当者の負担が軽減されたかなど、定量・定性の両面から評価することが重要です。
評価結果を踏まえ、必要があればさらなる改善を加えていく──。この「PDCAサイクル」を継続的に回していくことで、業務プロセスは徐々に洗練され、変化に強い組織が育っていきます。
業務プロセス改善に役立つツールと活用例
業務プロセスの改善は、人の手だけで完結するものではありません。近年では、可視化や自動化、情報共有を支援するさまざまなITツールが登場しており、それらを上手に活用することで改善効果をより高めることができます。この章では、具体的なツールの種類や活用シーンを紹介しながら、導入のヒントをお伝えします。
業務プロセスマネジメントツール(BPMツール)の導入
BPM(Business Process Management)ツールは、業務プロセスの設計・可視化・改善を一元的に管理できるツールです。
これらのツールは、業務の流れをモデル化し、進行状況をリアルタイムで可視化したり、業務ごとのパフォーマンスを分析したりすることができます。特に複数部門にまたがる複雑な業務を整理したい場合に有効で、業務改善の基盤づくりに役立ちます。
一部のツールでは、業務プロセスを変更した場合にどのような影響が出るかをシミュレーションする機能もあり、計画段階での精度向上にもつながります。
ワークフローシステムの活用
業務の中でよくある申請・承認・報告といったルーティン作業には、ワークフローシステムの導入が有効です。
これにより、紙やメールでのやり取りが不要になり、承認の遅れや抜け漏れを防ぐことができます。また、システム上で進捗状況が一目で把握できるため、管理側にとっても業務の見通しが立てやすくなります。
クラウド型のワークフローシステムであれば、初期費用を抑えつつ柔軟に運用できるため、中小企業にも導入しやすい点が魅力です。
業種別の活用事例(製造・建設・小売など)
業務プロセス改善に役立つツールは、業種によって適した種類や活用方法が異なります。
たとえば製造業では、生産管理システム(MES)を用いて工程のムダを見直したり、建設業では工程管理アプリを使って現場の進行状況を可視化したりと、現場のニーズに応じた導入が進んでいます。
小売業では、在庫管理や発注業務の自動化ツールを通じて、属人化や人的ミスの防止に成功している事例もあります。ツールはあくまで手段ですが、自社の課題に合わせて適切に選ぶことが鍵です。
中小企業でも導入しやすいツールの紹介
「大企業向けの高額なシステムはハードルが高い」と感じる中小企業でも、手軽に使える業務改善ツールは数多く存在します。
たとえば、無料プランのある業務可視化ツール、テンプレートを使ってすぐに使えるフローチャート作成ソフト、ノーコードで業務アプリが作れるツールなど、導入のハードルが低く、必要な機能に絞って活用できるサービスも増えています。
初めからすべてを自動化しようとせず、「紙の申請書をやめて電子化する」といった身近な改善から取り組むことで、現場の理解も得やすく、業務プロセス改善の成功率が高まります。
業務プロセス改善の成功事例
業務プロセス改善の重要性は理解していても、実際にどのような効果があるのかは、イメージしづらいかもしれません。ここでは、さまざまな企業が取り組んだ改善事例を紹介しながら、具体的な効果や工夫のポイントをご紹介します。実践に向けたヒントとしてぜひ参考にしてください。
部門間連携を強化したケース
ある中堅企業では、営業部門とバックオフィス部門との連携ミスによって、受注後の処理に時間がかかっていました。原因を探った結果、情報の受け渡しが属人的なメモや口頭で行われており、手戻りや抜け漏れが頻発していたことが判明しました。
そこで、業務プロセスを可視化したうえで、部門間のやり取りをワークフローシステムに置き換え、情報共有のルールを明確化。結果として、処理時間が30%以上短縮され、業務の精度も大幅に向上しました。
このように、プロセスのどこで情報が滞っているかを明確にすることで、部門の壁を越えたスムーズな連携が可能になります。
属人化の解消に成功したケース
中小企業に多い悩みとして、「ある担当者しかできない仕事」がボトルネックになっているケースがあります。ある企業では、経理担当者が業務フローの多くを独占しており、他の社員が業務を引き継げない状態になっていました。
この問題に対して、担当者の業務を詳細に棚卸しし、業務マニュアルとプロセス図を整備。さらに、必要な部分にはRPAツールを導入し、定型業務の一部を自動化しました。
結果として、経理部内で業務の共有が進み、担当者の急な休みにも柔軟に対応できる体制が整いました。属人化は業務のリスクを高めるだけでなく、社員の心理的な負担にもなり得るため、早期の対策が有効です。
ITツール導入による大幅な工数削減事例
あるサービス業の企業では、月次報告書の作成に膨大な時間がかかっており、担当者の多くがその作業に追われていました。業務プロセスを調査した結果、情報の集計が各拠点ごとにExcelで行われており、それを手作業で一本化するという非効率な手順が明らかになりました。
そこで、各拠点の入力フォーマットを統一し、クラウド型の業務管理ツールを導入。データが自動集約される仕組みに切り替えたことで、作業時間が約70%削減されました。
このように、ITツールはプロセスそのものを変える力を持っています。ただし導入ありきではなく、現状の課題と目的を明確にしたうえで選定することが成功のカギとなります。
まとめ|業務プロセスの改善で、組織はもっと強くなる
業務プロセスとは、企業活動の根幹をなす「業務の流れ」であり、ただの作業手順ではなく、組織全体の効率・品質・柔軟性に直結する重要な仕組みです。本記事では、その基本的な定義から業務フローとの違い、可視化手法、改善のステップ、さらには具体的なツールや成功事例までを包括的にご紹介しました。
業務プロセスの改善に取り組むことで、業務の属人化やムダが減り、社員一人ひとりがより本質的な仕事に集中できる環境が整います。そしてそれは、組織全体の生産性向上や、変化に強い経営体制の構築につながります。
はじめから完璧を目指す必要はありません。まずは現場の声を聞き、できるところから業務の可視化と整理を始めるだけでも、大きな一歩です。継続的な見直しと改善を積み重ねることで、組織は確実に強く、しなやかになっていくでしょう。業務プロセスの見直しは、未来への投資です。今こそ、その第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。