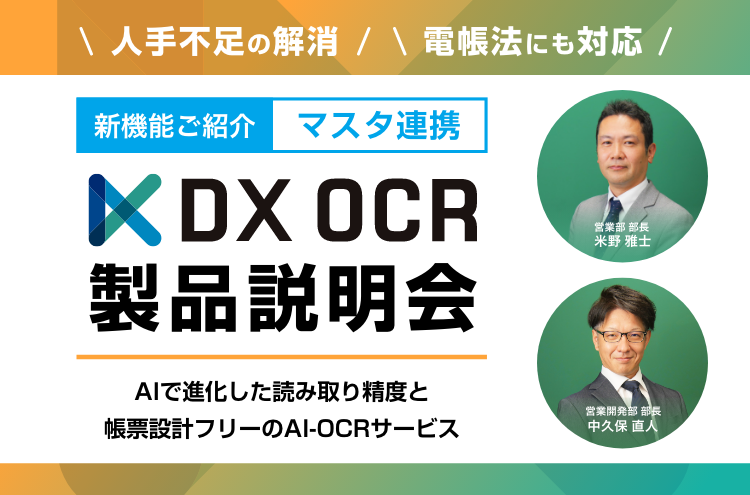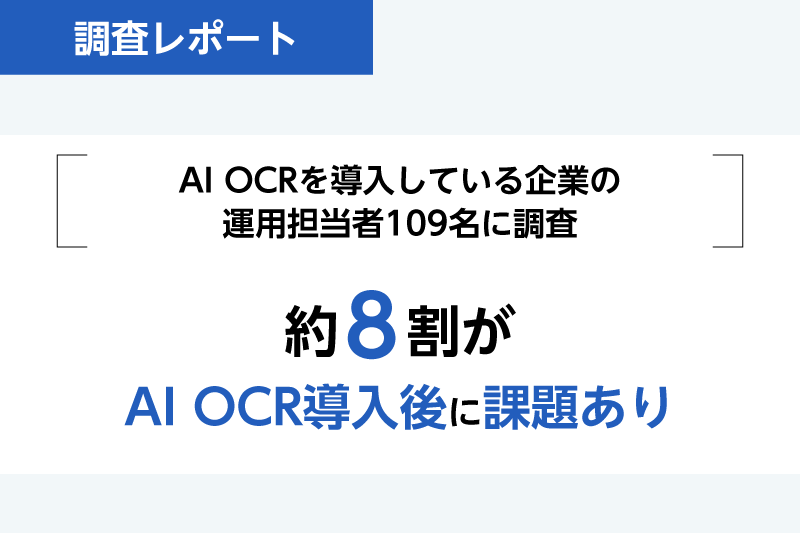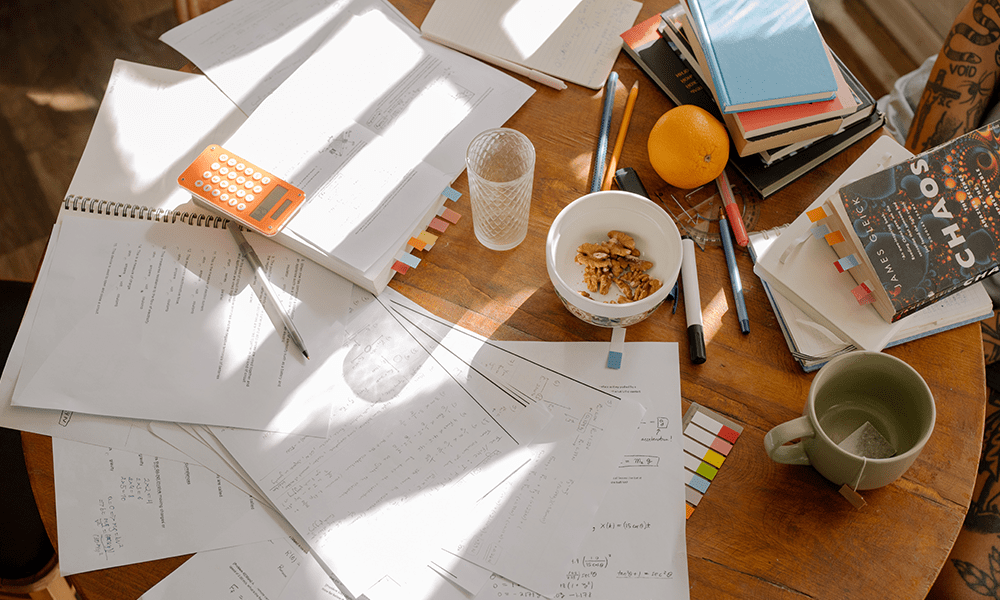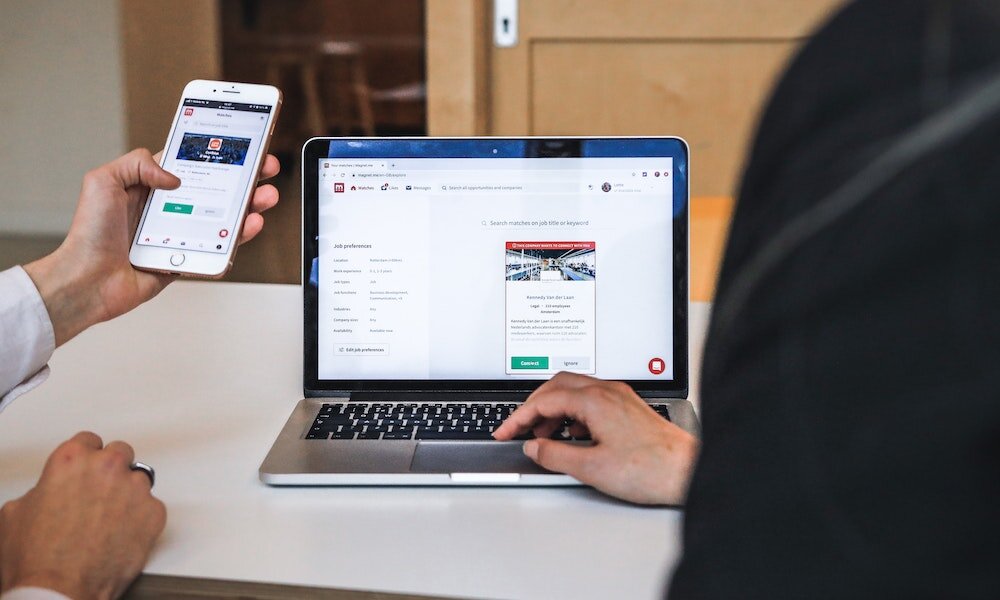手書き文字を人力でデータ化する際のコストやデメリットとIT技術による改善方法について
- INDEX
-
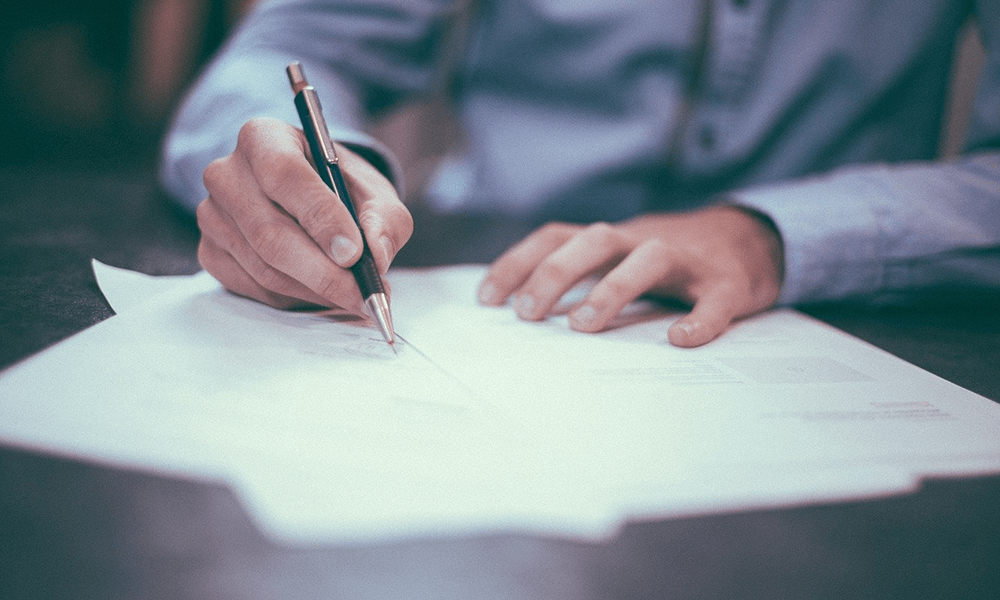
デジタル化や電子化、ペーパーレス化のために手書き文字を人力でデータ化する方法にはコストとデメリットがあります。
しかし、どのようなIT技術を導入すれば手書き文字をデータ化できるのかわからず、改善できないまま、非効率なまま業務や作業に従事しているケースが存在します。
今回は、手書き文字を人力でデータ化する際のコストやデメリットとIT技術による改善方法についてお話します。
手書き文字を人力でデータ化する際のコストやデメリット
はじめに手書き文字を人力でデータ化する際のコストやデメリットを見てみましょう。
手書き文字の文字起こしは人的資源と時間を浪費する
手書き文字の文字起こしは人的資源と時間的なコストを浪費するというデメリットがあります。もちろん、1枚、2枚など少ない量の伝票や帳票であれば別ですが、何百枚、何千枚ともなれば時間も人手も多く必要になります。これらは業界や業種によって異なる部分とはいえ、企業や組織としての規模が大きければ必然的に労力が必要であり、同じく利益や売上を増やそうとすればするほど労力やコストが増えるという悪循環に陥る可能性も高まります。
誤字や脱字が判別できずに二度手間になる
手書きの文字は人によってクセがあることも多く、読めない場合も少なくありません。その場に書いた本人がいれば別ですが、そうでない場合は本人に確認する手間も増えますし、悩んでいる時間は作業が停滞してしまうので、業務全体のスピードが遅延するというデメリットも発生します。さらに誤ってデータ化してしまえば後々の作業に支障が出ることも多く、解決しにくく厄介な課題であると言えます。
そもそも、手書きの書類は郵送なども含めてやりとりに時間が掛かる
手書き文字のデータ化以前の問題とも言えますが、手書きの書類や帳票、伝票は郵送なども含めてやりとりに時間が掛かるのもデメリットです。例えば、役所の手続きなどで考えると、わざわざ役所まで行かなければならない、必要書類や確認事項をその場で満たすことができなければ持ち帰って再度役所に行かなければならないとすれば、行ったり来たりの時間や労力が必要となります。企業や組織においても同様であり、手間が掛かれば掛かるほど処理が遅れる=利益や売上までの期間が間延びするというデメリットにもつながります。
紙ベースの帳票の保管や廃棄、管理の手間
手書き文字をデータ化した後の帳票や書類の保管や廃棄、管理の手間やコストもデメリットと言えます。紙資源のコストだけでなく、保管するコスト、それらに伴う人件費も含めて、企業の規模が大きければ大きいほど負担が増えてしまいます。データ化前の伝票や書類は原紙として簡単に捨てることもできない場合もあることから、削減しにくいコストとして頭を悩ませる存在と言えます。
目視によるチェックや手入力はうっかりミスやヒューマンエラーを起こしやすい
手書き文字のデータ化の際、目視によるチェックや手入力によってうっかりミスやヒューマンエラーを起こしやすいのもデメリットです。また、作業量が増えれば必然的にミスも増え、ミスをカバーするための労力も増大してしまいます。作業量が増えるというのは利益や売上が増えているというポジティブなことであるはずなのに、事務作業の面において対応しきれず、人員が足りないことで利益や売上が頭打ちになることも考えられるでしょう。
手書き文字を人力でデータ化するメリットや今でも手書きがなくらない理由
次に手書き文字を人力でデータ化するメリットや今でも手書きがなくらない理由をご紹介します。
一昔前は事務処理のための人員が豊富に存在していた
今でこそパソコンやその他のデバイスは「ひとりで大量に事務処理が可能」になりましたが、昔はデバイス的にもシステム的にも連携やオンライン化が進んでおらず、その分、人員が豊富に存在していました。
ひとり一台のパソコンで同じシステムに接続して、大量の伝票を処理するのが当たり前であり、事務員を雇用しなければ処理できないのが当たり前だったと言えます。そのため、手書き文字であっても何ら問題もなく、印刷でも手書きでも関係なく人力でデータ化が可能だったということです。
手書きは特別な機器も知識も必要ではないため利便性が高い
手書き自体は特別な機器や知識が必要ではなく、利便性が高いこともメリットだったと言えます。言い換えれば、顧客やユーザーは自分の手で記入することで、商品の注文や申し込みが可能であり、キーボードやマウスを使えなくても問題なかったということです。
これらは社内や組織内でも同じであり、今でこそオフィスソフトを誰もが使えますが、昔は全員がオフィスソフトどころかパソコンが使えなくても大丈夫でした。手書きの文字列を事務の担当が人力でデータ化してくれるので、別段、不便もなかったような状況だったのです。
紙の帳票による管理が当たり前で紙に沿った業務の流れが構築されていた
今でもペーパーレス化が進まない要因、とも言えますが、紙の帳票による管理が当たり前で特に不都合がなかったのも事実です。実際にデジタルでなければならない部分は複雑な計算や蓄積されるデータのみであり、簡単なものは紙ベースで進めることができたからです。
問題となるのは人力でデータ化するための労力や時間の浪費ですが、前述したように人員さえいれば難しいシステムも、複雑なデバイスも覚える必要がないため、誰にでもできることから人手不足にもなりにくい雇用環境があったとも言えます。
ハンコ文化との相性が良く、物理的な紙だからこそのセキュリティ性があった
紙の帳票や伝票、書類は日本のハンコ文化との相性がとても良いです。決して効率的であるとは言えませんが、社内や組織内の決裁や決定、判断においても紙で進めることで、段階的かつ着実に話が進むようになっていたからです。
同様に物理的な紙だからこそ、オンラインで情報漏えいになるようなこともなく、それこそ泥棒などに入られない限りは安心・安全だったのも事実です。もちろん、廃棄のタイミングなどで情報漏えいが起こる可能性があること、物理的な書類の移動に伴う紛失や盗難もあることから、一概にオフラインの方が良いとは言えませんが、サイバー攻撃のような被害を受けにくかったのも事実と言えます。
多少手間に感じたとしても、今までのやり方が完全に間違っているとは考えられないケースも?
実際に企業や組織を構築する従業員や人材にとって、今までのやり方が完全に間違っているというような考え方を持つことが難しいのも理由のひとつと言えるでしょう。間違っているどころか、単調で同じことの繰り返し、多少手間を感じていても給与が支払われて、生活ができれば問題なかったからです。
これらは無理に変化をすることによる歪みをデメリットと感じることと同義であり、変化をしないことで歪みが生じないというメリットがあると誤解してしまう理由とも言えるでしょう。
手書き文字のデータ化をIT技術の活用で改善する方法や考え方
次に、手書き文字のデータ化をIT技術で改善する方法や考え方をいくつかご紹介します。
前提:なぜ、手書きが必要か、手書きでなけれなダメか精査する
業界や業種による部分はあるにせよ、本当に手書きが必要なのか、手書きでなければダメなのかを精査しましょう。実際問題として、普段生活する中で手書きはどれくらいあるか考えてみることから始めても良いかもしれません。ふと思い返しても手書きで何かを処理するというのは少ないことに気が付きます。むしろ、今の時代に手書き?と思うことがあるのではないでしょうか。企業や組織として手書きが必要なのか、代替できる手段がないかどうかを見極めることが大切です。
ユーザーや顧客の「手書き」をゼロにする
手書き文字をデータ化する作業があるということは、言い換えれば顧客やユーザーに手書きという労力を負担しているということでもあります。もちろん、手書きの方が早い現場もありますし、パソコンやスマホによる入力が現実的ではない分野もありますので、必ずしも手書きがダメ!ということではありませんが、手書きが必要なのか見極めつつ、ユーザーや顧客の手書きをゼロにすることを検討しましょう。また、実際に手書きであるべきかを顧客やユーザーにアンケートを取っても良いかもしれません。実は手書きが面倒だった、労力だったとなれば顧客やユーザもその他の代替手段に対応してくれる可能性が高まります。
ペンタブレットで手書きを直接データ化する
どうしても手書きが必要であれば、ペンタブレットなどを用いて手書きを直接データ化する方法もあります。直接紙に手書きするのではなく、データとして手書きを受け取るということです。いわゆるクレジットカードでの支払い時にサインをするような仕組みであり、単に署名やサイン、捺印の代わりとして手書きが必要であれば代替手段として成立する可能性が高いです。また、場合によっては電子的に契約する仕組みを導入することで、書類の郵送などの手間を省くことができます。既に商品の売買やオンラインの有料サービスへの課金など、BtoCやBtoB、CtoCにおいても実現している仕組みでもありますので、前向きに検討してみても良いでしょう。
OCRで手書き文字を読み取ってデータ化する
OCRで手書き文字を読み取ってデータ化するのも良いでしょう。昨今ではOCRによる文字認識の精度も高くなっているので、決められたフォームや枠組みの中であれば認識しやすくなっています。OCRのソフトウェアやツールによっては実務レベルの運用も可能ですので、目的や用途に合わせて高性能なOCRの導入も視野に入れておきましょう。OCRによって手書き文字を認識する仕組みが導入できれば、ペーパーレス化・デジタル化というDX推進の基盤も整いやすくなりますので、OCRを導入する際はどのような機能を備えているかもチェックすることをおすすめします。
オンライン化やWebフォーム、もしくはアプリへ移行する
手書き文字のデータ化に悩んでいるからこそ、オンライン化やWebフォーム、もしくはアプリへ移行することも検討してみましょう。例えば、商品の注文やサービスの依頼や予約など、一般的に何かを受注する仕組みであれば大抵はオンライン化やアプリへの移行は可能です。もし、そういったIT系に疎い顧客やユーザー層を抱えているのであれば、FAXや電話による注文などに切り替えることも検討しても良いでしょう。どの場合においても「手書きを必要としない」ことや「そもそも手書きができない」ようにすることが手書き文字のデータ化のコストやデメリットを改善するということを忘れないようにしてください。
手書き文字のデータ化を「難しく」考えずにスムーズに移行するには?
次に手書き文字のデータ化を「難しく」考えずにスムーズに移行するためにどうすれば良いかご紹介します。
IT技術を用いた仕組みが「昔よりもユーザーに寄り添っている」ことを知るべき
スマートフォン然り、パソコンやタブレットなどのデバイス今ほど急速に普及したのは、誰でも扱えるようにデザインされたことが理由です。IT技術を用いた仕組みが昔よりもユーザーに寄り添っていることを知っておきましょう。
一昔前であれば、ある程度のITに関する知見や経験がなければ扱えなかったような技術においても、クリックやタップのみ、数字を少し入力するみ、簡単に選ぶのみなど「直感的でわかりやすく、間違えにくい」ように成長しています。同様に「覚えやすく、誰にでも扱える」ことにも注力されているため、不安に思う必要はないと言えます。
ITと縁遠い、もしくはITに疎い業界でも既にデジタル技術の導入が進んでいる
IT技術が誰にでも扱えるようになったことで、ITと縁遠い、もしくはITに疎い業界であっても、既にデジタル導入が進んでいるケースもあることも知っておきましょう。
例えば、いわゆるDXの推進とは縁遠いような農業の分野においても、農耕機械の自動運転、ドローンの活用、各種センサーによるセンシングなど、デジタル技術の導入が進められています。
完璧にデジタルで管理することで、人間の勘や経験を必要としない環境、すなわち属人化やブラックボックス化がしにくい環境が得られているとのことであり、誰にでも扱いやすく、その上でさまざまな課題や問題の解決につながっています。
官公庁から発表されているDX推進の先行事例を見るのもおすすめ
日本においては国主導でDXの推進が進められており、各官公庁からDXの推進事例が発表されています。いわゆる先行事例と言われるものであり、どのような課題や問題があって、どのような技術を導入し、結果としてどのような効果があったのかまとめられた情報です。
大手や有名企業、地方自治体、官公庁の事例はとても参考になり、どのような手順で進められたのかも記されているため、理解しやすいのでおすすめです。
紙ありきの地方自治体や公的機関でもデジタル化は進んでいる
現時点においても紙ありきの申し込みや手続きの残る地方自治体においてもデジタル化が進められています。事務作業の量が多すぎる、もしくは範囲が広すぎるために「難しい」と感じることもあるかもしれませんが、紙ありきの公的機関でも進められていることを知ることで、前向きに導入や検討を進めることができます。
実際、手が付けられない、既に作業や業務が累積してどうしようもない状況自体を改善・解決しているケースもあること、利用するユーザーの利便性や快適性がアップしていることなど、具体的な結果を見ることも大切です。
実際に手書き文字のデータ化を体験してみることが一番の近道
どうしても難しいという思い込みから脱却できない時こそ、まずは実際に手書き文字のデータ化、もしくは印字されている帳票をOCRで読み取ることなど、IT技術によるデータ化を体験・体感してみましょう。精度の高さや、想像しているよりも扱いやすいことを知ることができますし、実務での人力入力との差を理解しやすいためです。
実際の画面をチェックし、扱いやすいかを体験してみること、本当に誰でも扱えるか実務担当者にも利用してもらうことなど、行動に移すことで悩むよりも改善・解決に向かいやすくなるということも理解しておくと良いでしょう。
まとめ:人力による手書き文字のデータ化は無理せず、IT技術に頼ろう
今回は手書き文字を人力でデータ化する際のコストやデメリットとIT技術による改善方法についてお話しました。
オンライン化やアプリ化、タブレットによる電子的なサインも含めて、IT技術で代替できる場合は代替した方がスムーズです。しかし、どうしても手書きの要素が廃止できないのであれば、手書き文字の認識が可能なツールやソフトウェアを導入しましょう。
いきなりオンライン化は難しい、もしくはOCRによる手書き文字のデータ化を始めたいとお考えであれば、当社の「AnyForm OCR」の利用をご検討ください。手書き文字に関しても認識精度が高く、実務レベルで運用することが可能です。同時にペーパーレス化やデジタル化など、データの一元管理やFAXの電子化も可能であり、DXの推進の一助となりますので、ぜひともこの機会にご相談、お問い合わせください。