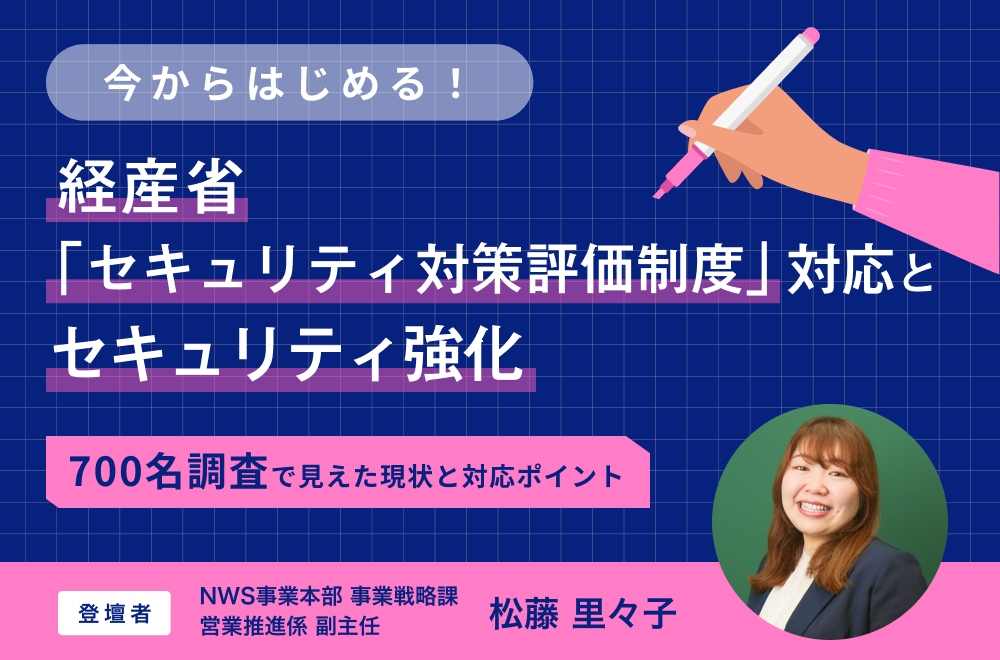不正アクセス禁止法とは?禁止行為・罰則・企業が取るべき対策を解説
- INDEX
-
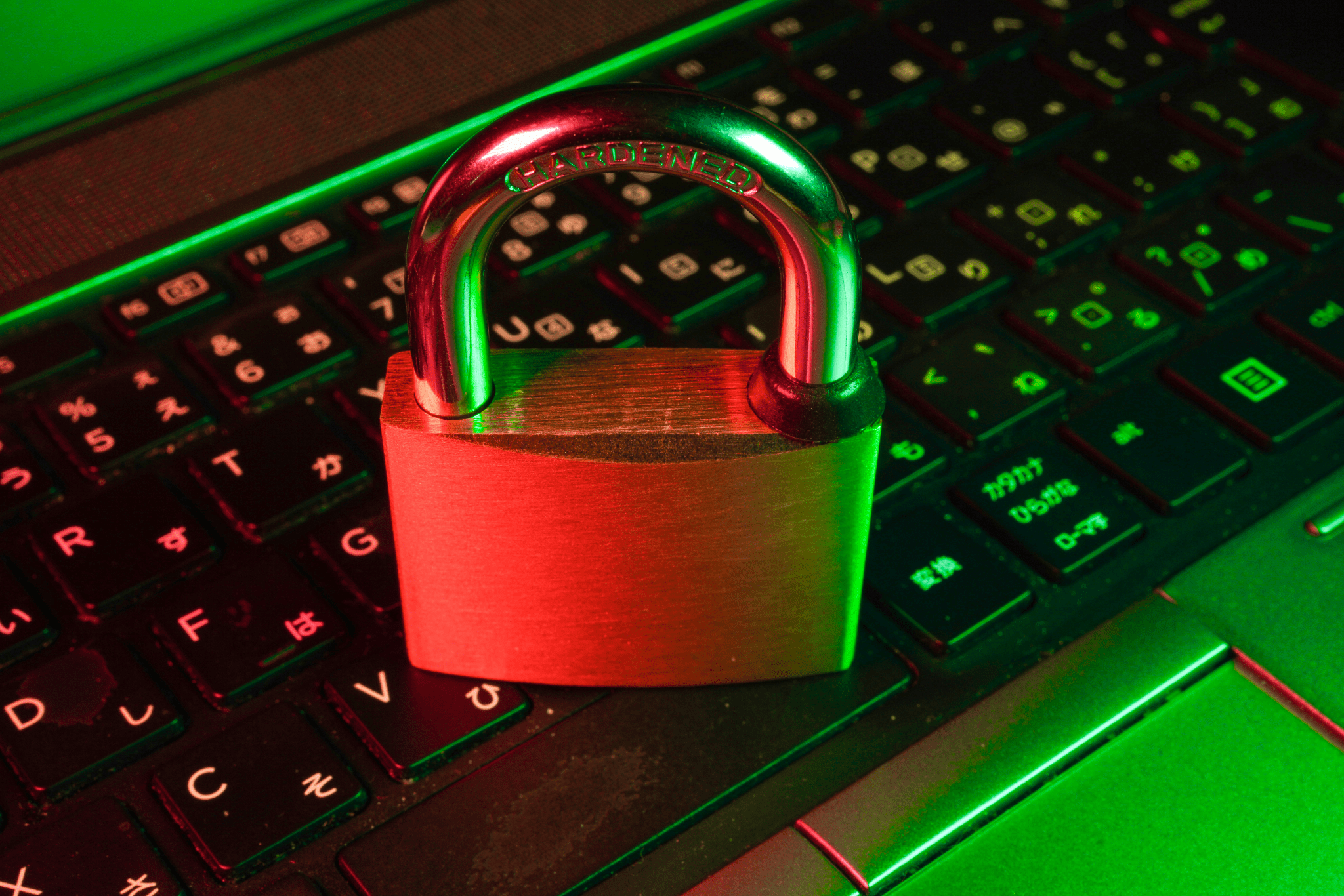
近年、企業を取り巻く情報セキュリティのリスクはますます高まっており、その中でも「不正アクセス」は見えづらく、かつ深刻な被害をもたらす脅威として注目されています。
こうした背景のもとで重要性を増しているのが、「不正アクセス禁止法」です。これは単に違法行為を取り締まるための法律ではなく、企業が情報管理体制を見直し、組織全体でセキュリティ意識を高めるための「基準」とも言える存在です。
本記事では、不正アクセス禁止法の基本的な内容から、実際の違反事例、企業が取るべき具体的な対策、さらにはIT資産管理ツール「AssetView」を活用した実践的な対処法まで、網羅的に解説します。不正アクセス禁止法に関する企業の理解不足は、予期せぬ法的リスクを招く可能性があるため、その詳細な理解が急務となっています。
不正アクセス禁止法への理解を深め、日々の業務に生かすための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
不正アクセス禁止法とは
不正アクセス禁止法は、インターネットやネットワーク社会の発展に伴って整備された、情報セキュリティに関する重要な法律です。ここでは、法律の定義や目的、これまでの改正履歴を紐解きながら、なぜこの法律が企業や個人にとって重要なのかを解説します。
法律の定義と概要
不正アクセス禁止法は、正式には「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といい、インターネットやネットワークを通じた不正なアクセスを禁止することを目的としています。参照:e-Gov法令検索: 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
ここでいう「不正アクセス」とは、他人になりすましてログインする、正当な権限がないのにシステムへ侵入する、他人のIDやパスワードを無断で使うといった行為を指します。
個人や企業の情報資産を守るうえで、この法律は非常に重要な役割を担っています。とくに近年では、業務でクラウドやWebサービスを使う機会が増えたこともあり、不正アクセスのリスクはかつてないほど身近なものとなっています。
法律の対象は個人だけでなく、企業や組織での不正行為、あるいはその助長行為にも及ぶことがあるため、関係するすべての人にとって「知っておくべき法律」と言えるでしょう。
不正アクセス禁止法の制定の背景と目的
不正アクセス禁止法が施行されたのは、IT社会が急速に発展し始めた1999年。当時から、インターネットの普及とともに「他人のIDやパスワードを悪用して、情報に不正にアクセスする」といった問題が社会課題になっていました。不正アクセスは、直接的な被害だけでなく、間接的に企業の信用や個人のプライバシーを大きく損なう可能性があります。しかし、当時の日本の法制度ではこうした行為に対して明確な罰則を設けることができませんでした。
そのため、技術の進歩に対応し、情報セキュリティを守るための法的基盤として、この法律が制定されたのです。
不正アクセス禁止法の目的は大きく2つあります。
法改正の履歴と今後の動向
不正アクセス禁止法は、施行から現在に至るまで、社会の変化に合わせて何度か改正が行われてきました。たとえば、平成24年(2012年)の改正では「不正アクセスに使われる認証情報(IDやパスワードなど)を不正に保管する行為」も明確に禁止されるようになり、取り締まりの対象が広がりました。この改正は、フィッシング行為の禁止・処罰、およびIDやパスワードの不正取得・不正保管行為の禁止・処罰、そして罰則の強化を主な目的としていました。
さらに、直近では令和4年(2022年)に刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律により、不正アクセス禁止法も改正されています。この改正は、刑法の文言変更などに伴う形式的な修正が中心でしたが、それでも法制度の見直しが継続的に進められていることを示しています。
2020年以降はサイバー攻撃の巧妙化を背景に、企業や教育機関を狙った不正アクセス事件が相次いでいます。こうした情勢を受け、国会では法整備の必要性がたびたび議論されており、今後もさらなる改正が行われる可能性があります。
近年注目されているのは、法人や組織に対する罰則の明確化や、AIやIoT機器など新技術の普及にともなう定義の見直しといったポイントです。
情報技術がビジネスに深く入り込んだ今、法律もまた柔軟に進化していく必要があります。現場の実情に即したルールづくりこそが、安全で安心な情報社会の土台となるのです。
参照:不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律の施行について
参照:日本法令索引: 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
不正アクセス禁止法で禁止されている行為
不正アクセス禁止法では、単に「不正アクセス」を行った場合だけでなく、それを支えるような行為、または誘発するような行為も広く規制対象としています。ここでは、法律上明確に禁止されている行為を条文ごとに解説します。
不正アクセス行為(第3条)
第3条では、もっとも基本となる「不正アクセス行為」そのものを禁止しています。具体的には、次のような行為です:
企業にとっては外部からの攻撃だけでなく、内部の人間による不正アクセスも重大な問題です。
他人の識別符号の不正取得(第4条)
第4条では、「他人の識別符号(IDやパスワード)」を不正に取得する行為を禁止しています。識別符号の取得とは、たとえば以下のような行為を指します:
不正アクセスの助長行為(第5条)
第5条は、直接的な不正アクセスではないものの、それを手助けする行為を対象としています。例としては:
識別符号の不正保管(第6条)
第6条では、他人の識別符号を「不正に保管する」行為を禁止しています。これは、たとえその情報をまだ使用していなくても、不正アクセスにつながるおそれがあるためです。
具体的には:
このような行為が発覚した場合、使用の有無にかかわらず処罰の対象となる可能性があります。
「持っているだけでも違法になる」という点で、注意すべき条項です。
識別符号の入力要求(第7条)
第7条では、正当な理由なく他人に対して識別符号の入力を要求する行為が禁止されています。たとえば:
以上が、不正アクセス禁止法において明確に禁止されている主な行為です。
これらの行為はいずれも、企業の信用、個人のプライバシー、社会全体の情報安全にかかわる重要な問題です。
たとえ「意図的ではなかった」「知らなかった」という場合でも、状況によっては処罰の対象になり得るため、正しい理解と日常的な注意が求められます。
参照: 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第三条 e-Gov法令検索
不正アクセス禁止法に違反した場合の罰則
不正アクセス禁止法では、違反行為に対して厳格な罰則が定められています。これは単に刑事罰を科すための制度ではなく、企業の信用や被害者の権利にも深刻な影響が及ぶことを前提とした措置です。
ここでは、行為の種類ごとに定められている主な罰則と、法人・組織として責任を問われる可能性について解説します。
不正アクセスそのものの罰則
不正アクセス行為(第3条)に違反した場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります(不正アクセス禁止法 第11条 第1項)。これは、他人のIDやパスワードを使って無断でログインしたり、認証をすり抜けてシステムに侵入したりした場合に適用されます。
また、犯行の態様や目的によっては、刑法の「電磁的記録不正作出罪」や「業務妨害罪」など、他の法令と併せて処罰されることもあります。さらに、個人情報が窃取・悪用された場合は、個人情報保護法や不正競争防止法なども関連してくることがあります。
とくに近年では、被害者が法人である場合、損害額や社会的影響の大きさを重く見て、厳罰が求められる傾向にあります。
助長・準備行為の罰則
第4条〜第7条で定められている「準備行為」や「助長行為」についても、法律は処罰対象としています。具体的には、以下のような行為に対して罰則が科されます。
これらの行為は一見すると『まだ実害がない』と思われがちですが、法律はこうした行為の早期摘発を可能にすることで、被害を未然に防ぐことを重視しています。
法人・組織として問われる可能性
不正アクセス禁止法自体には「法人処罰規定(両罰規定)」は明記されていません。そのため、違反行為を行ったのが個人であった場合、原則としてその個人に対して罰則が適用されます。
しかし、以下のような状況では、企業や組織が管理責任を問われる可能性があります:
また、企業としての社会的信用を大きく損なうリスクもあるため、法的責任の有無にかかわらず、組織的対策と教育体制を整備しておくことが、組織としての信頼維持にもつながります。
罰則の重さは、不正アクセスがもはや"軽い気持ち"では済まされない重大な行為であることを示しています。
個人であれ法人であれ、こうした行為を「知らなかった」「意図はなかった」では済ませられない時代です。
適切な理解と備えが、組織と社会を守る第一歩になります。
参照: e-Gov法令検索: 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第十一条
実際に起きた不正アクセスの事例
不正アクセスは、ニュースで取り上げられる大規模事件に限らず、私たちの身近なサービスや職場でも発生しています。ここでは、実際に報道された複数の事例を通して、不正アクセスの多様な手口と、その背景にある課題を見ていきましょう。
ゲームサービスへの不正ログイン事例
近年、オンラインゲームのアカウントが不正に乗っ取られる事件が相次いでいます。たとえば、2023年には人気ゲームサービスで複数のアカウントが不正にログインされ、ゲーム内アイテムが勝手に使用・売却される被害が確認されました。
加害者は、第三者から入手したID・パスワードのリストを用い、『リスト型攻撃(流出したID・パスワードのリストを使って複数のサービスに自動的にログインを試行する攻撃手法)』という手法で不正アクセスを行っていたとされています。
こうしたケースでは、アカウント情報の流出元が別のサービスであることも多く、パスワードの使い回しが被害を拡大させる大きな要因となっています。
偽SMSを悪用した認証情報の窃取
スマートフォンの普及とともに増えているのが、「偽SMS(スミッシング)」を用いた不正アクセスの事例です。2022年には、大手キャリアを装った偽のSMSメッセージを送り、ユーザーに偽のログインページを開かせ、そこで入力されたIDとパスワードを盗み取る手口が確認されました。
被害者は、正規のサイトと見分けがつかない偽サイトに誘導されていたため、気づいたときにはすでにアカウントが操作され、電子マネーの不正利用や個人情報の流出が発生していました。
このようなケースでは、見た目では正規の画面とほとんど区別がつかない点に、特に注意が必要です。
ユーザーのリテラシーと通信事業者・サービス提供者側のフィルタリング対策の両輪が求められます。
成績改ざんや社内システムの悪用など、内部による不正アクセス事例
不正アクセスは外部からの攻撃だけでなく、内部の人間によって行われることもあります。たとえば、ある中学校では、在校生が教職員のID・パスワードを不正に入手し、自身の成績を改ざんしたとして書類送検される事件が発生しました。
また、企業においても、退職予定者が在職中に取得していた管理者権限を悪用し、機密ファイルを外部へ持ち出すといったケースが後を絶ちません。
このような内部不正は、物理的に信頼された環境からのアクセスであるがゆえに発見が遅れやすく、被害が深刻化する傾向があります。
アクセス権限の適切な設定や、ログの監視体制が欠かせません。
【補強】企業が巻き込まれたケースと教訓
不正アクセスの影響は、当事者だけにとどまりません。たとえば、ある中小企業では、社員の業務用メールアカウントが不正アクセスを受け、そこから取引先に向けて偽の請求書が送信されるという被害が起きました。
このような「なりすましメール」は、企業間の信頼を大きく損ねるだけでなく、二次被害(誤送金・取引停止)をも引き起こす重大なリスクです。
また、クラウドストレージの共有設定ミスにより、社外秘資料がインターネット上に誰でも閲覧可能な状態で公開されていた例もあります。
これは不正アクセス以前に、設定不備や運用の甘さが招いた情報漏えいと言えるでしょう。
こうした事例は、自分たちは関係ないと思い込んでいる企業ほど、実は無防備であるという現実を浮き彫りにしています。
参照:令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について
参照:情報セキュリティ10大脅威
不正アクセスを防ぐために企業が取るべき対策
不正アクセスの被害を未然に防ぐには、単にセキュリティソフトを導入するだけでは不十分です。技術的な対策とあわせて、社内ルールや運用の徹底、従業員一人ひとりの意識改革が求められます。ここでは、企業として現実的かつ効果的に取り組める4つの対策を紹介します。
アクセス制御・認証強化(例:ID管理・多要素認証)
まず重要なのが、誰が・いつ・どこにアクセスできるかを明確に管理する「アクセス制御」の徹底です。特に業務システムやクラウドサービスの利用が一般化した今、IDとパスワードだけに頼る認証では限界があります。
そこで導入を検討すべきなのが、多要素認証(MFA)です。
パスワードに加えて、スマートフォンの認証アプリや指紋・顔認証といった「もう一つの要素」で本人確認を行うことで、仮にパスワードが漏えいしても不正ログインを防ぐことができます。
また、IDの一元管理も効果的です。
複数のシステムに同じIDを使いまわさず、アクセス権限を必要最小限にとどめる「最小権限の原則」を意識しましょう。
社内ルールと教育体制の整備(例:識別符号共有の禁止)
いかに堅牢なシステムを導入しても、それを扱う人がルールを守らなければ意味がありません。社内での情報セキュリティに関する明文化されたルールと、定期的な教育・啓発活動は不可欠です。
とくに重要なのが、ID・パスワードの共有禁止を徹底することです。
「同じ部署だから」「一時的な対応だから」といった理由でアカウントを共有してしまうと、責任の所在が曖昧になり、ログの追跡も困難になります。
社内研修やEラーニングの導入、セキュリティに関する事例共有などを通じて、「なぜ守る必要があるのか」を社員自身が理解できる環境を整えることが重要です。
定期的なアクセスログの監査とアラート設計
システムの利用状況を見える化することも、不正アクセス対策の基本です。ログイン履歴やファイルの操作履歴といったアクセスログを定期的に監査することで、異常な挙動や不審なアクセスを早期に発見できます。
さらに、あらかじめアラート条件(例:深夜のログイン、海外IPからのアクセスなど)を設定しておくことで、リアルタイムでの検知と対応も可能になります。
アクセスログの監査は「後追い」の手段としてだけでなく、「未然に防ぐ」ためのセンサーの役割も果たします。
人的ミスや内部不正にも対応できる、重要な体制のひとつです。
退職者・異動者のアカウント管理(例:アカウント無効化)
意外と見落とされがちなのが、退職者や異動者のアカウント管理です。「退職後も元社員のアカウントが残っていた」「異動したのに前部署のシステムにアクセスできるまま」、こうした状態は、不正アクセスの温床となり得ます。
退職や部署異動のタイミングで、アカウントの無効化・削除・権限変更を確実に行うための運用ルールを整えておく必要があります。
人事・情シス・現場の連携を密にし、抜け漏れを防ぐフローの構築が求められます。
また、退職時には端末・クラウド・メールの利用履歴の確認も行い、不審な操作がなかったかを振り返ることで、後のトラブルを防ぐことができます。
セキュリティ対策に「絶対」はありませんが、できることをひとつずつ丁寧に積み上げていくことが、結果的に大きな被害を防ぐ最善策となります。
技術だけでなく、人と仕組みを含めた"総合的な備え"が、今の時代には必要とされています。
AssetViewで実現する不正アクセス対策
IT資産管理ツール「AssetView」は、巧妙化する不正アクセスに対し、企業が直面する実務課題に応える設計がなされています。単なる情報収集だけでなく、「外部からの脅威への防御」と「内部からの情報漏洩防止」という両面から、多角的なセキュリティ対策を提供しています。以下では、AssetViewで実現できる主な不正アクセス対策の機能をご紹介します。
外部脅威への防御を担うセキュリティ機能
マルウェア対策・駆除
高い検知力を誇る「カスペルスキーエンジン」を搭載し、進化し続けるマルウェアの侵入を防ぐだけでなく、仮に侵入された場合にも迅速な駆除により、不正アクセスによるシステム破壊や情報窃取から組織を保護します。セキュリティアップデート管理
Windowsのセキュリティアップデートを一元的に管理し、OSやアプリケーションの脆弱性を突いた攻撃から保護します。これにより、既知のセキュリティホールを放置するリスクをなくし、不正アクセスの侵口を塞ぎます。Webアクセス制限
業務に関係のない有害なウェブサイトへのアクセスをブロックすることで、危険なサイトからのウイルス感染やフィッシング詐欺による不正アクセスを予防します。内部不正を可視化・抑止する管理機能
AssetViewは、外部からの攻撃だけでなく、内部関係者による不正行為や情報漏洩のリスクにも対応しています。PC操作ログの取得と活用
従業員の業務中のPC操作ログを詳細に収集することで、「いつ、誰が、何を」行ったかを明確に把握できます。これにより、不審なファイルアクセス、データの持ち出し、システムへの異常なログイン試行などを検知し、内部不正の早期発見はもちろん、万が一のトラブル発生時にも、正確な証跡として活用できます。ファイル持ち出し制御
許可されていないUSBデバイスやスマートフォンなどの外部メディアへの接続を禁止し、機密情報の不正な持ち出しを物理的に制限します。これは、データの流出経路を厳しく管理することで、内部からの情報漏洩リスクを大幅に低減します。PC紛失時の対応
万が一PCが紛失・盗難に遭った場合でも、遠隔からのロックやデータ消去、位置情報管理が可能であり、情報漏洩や不正利用といった二次被害の拡大を防ぎます。AssetViewは、これらの機能により、不正アクセスの侵入口を封じ、内部不正の兆候を見える化し、万が一の事態にも迅速に対応できる体制を実現します。
まとめ|不正アクセス禁止法は企業全体の情報管理体制が問われる
不正アクセス禁止法は、単なる「違法行為への対処法」ではなく、企業が自らの情報管理体制を見直すきっかけとなる法律です。法で禁止されている行為には、実行そのものだけでなく、準備や助長、管理不備といった周辺行為も含まれており、それだけ不正アクセスのリスクが社会的に重大であることを示しています。
本記事では、不正アクセス禁止法の基本的な枠組みから、実際の事例、企業がとるべき現実的な対策、そしてそれを支援するツール「AssetView」の活用方法まで、幅広くご紹介しました。
重要なのは、「知っている」だけでは守れないということです。
法律を理解し、適切な技術的対策と社内体制を構築し、日々の業務に組み込んでいく。
この地道な取り組みこそが、不正アクセスという見えづらい脅威から、組織と社会を守る最大の武器になります。
これからの時代、情報セキュリティは一部の専門部署だけの責任ではありません。
全社的なリテラシーと運用体制の底上げが求められる時代に入っています。
不正アクセス禁止法をきっかけに、情報管理のあり方を見直し、より強固なセキュリティ文化を育てていくことが、すべての企業に求められています。