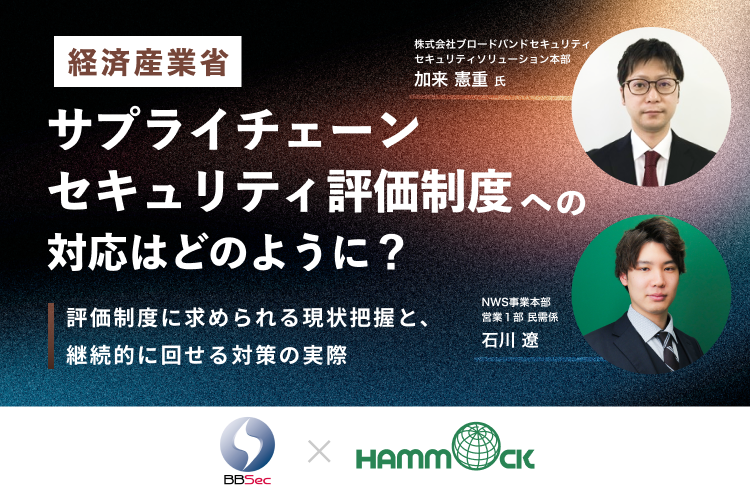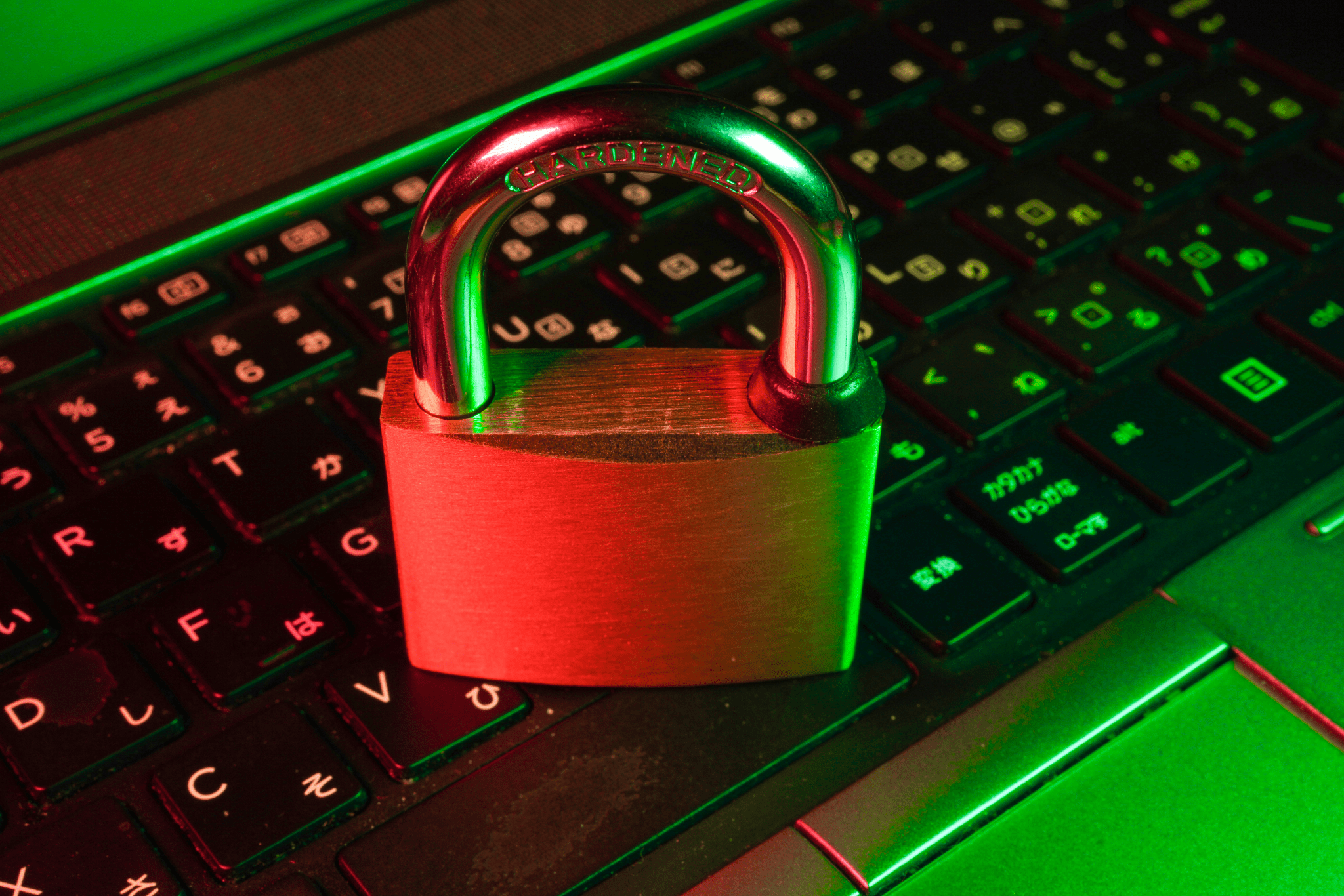EPPとEDRの違いを徹底解説|役割・検知技術・併用の必要性まで完全ガイド
- INDEX
-

サイバー攻撃の高度化により、従来のウイルス対策だけでは企業の端末(エンドポイント)を守りきれない時代になりました。その中で注目されているのが、EPP(Endpoint Protection Platform) と EDR(Endpoint Detection and Response)という二つのセキュリティ基盤です。しかし、EPPとEDRの「違いは何か?」「どちらを導入すべきか?」「併用は必要か?」と疑問に感じる担当者も多いはずです。
本記事では、EPPとEDRの役割・特徴・検知方法の違いから、選定ポイント、導入時の課題までを体系的に解説します。自社環境に最適なエンドポイントセキュリティを検討する際の指針としてご活用ください。
EPPとEDRとは?それぞれの意味と役割は何か
エンドポイントに対する攻撃は年々多様化し、どの端末がどんなリスクを抱えているのか把握しづらくなっています。安全な環境を保つためには、侵入前に守る仕組みと、侵入後に気付いて対処する仕組みの両方を理解することが重要です。ここではEPPとEDRの役割を整理し、企業でこれらがどのように使われているのかを解説します。EPPとは何を守る仕組みで、どのようにマルウェア侵入を防ぐのか
EPPは端末に侵入しようとするマルウェアを入り口で防ぐための仕組みです。既知の攻撃パターンを参照する検出方式に加え、動作の特徴から不審な振る舞いを見つける機能や、機械学習を使った判断を取り入れた製品もあります。日常的な業務を妨げない範囲で端末を保護することを目的としており、多くの企業で基本的な対策として利用されています。ただし、完全に未知の脅威をすべて防げるわけではなく、限界が生じる場面もあります。EDRとは何を検知し、どのようにサイバー攻撃の被害を最小限にするのか
EDRは端末内部の挙動を細かく記録し、普段とは異なる動きを見つけて対応する仕組みです。プロセスや通信、ファイル操作のログを蓄積し、異変があればアラートとして通知します。必要に応じて不審なプロセスを隔離したり、攻撃の経路をさかのぼって調査したりと、被害の広がりを抑える行動につなげられる点が特徴です。自動化だけで完結するものではありませんが、状況把握と初動対応に役立ちます。EPPとEDRが注目される背景(脅威の高度化・テレワーク拡大・運用負荷)
脅威が高度化し、端末管理の難易度が上がったことがEPPとEDRの注目度を高めました。特にテレワークの普及により社内ネットワーク外での利用が増え、従来の境界型防御だけでは対応が追いつかない状況が生まれています。また、情報システム部に十分なリソースがない企業も多く、侵入前の防御と侵入後の検知を組み合わせた多層的な対策が求められています。EPPとEDRはそれぞれ異なる役割を担いながら、総合的なエンドポイント防御の土台となっています。EPPとEDRの違いは?防御範囲・検知方法・運用の観点で比較するとどうなるか
EPPとEDRはどちらもエンドポイントを守るための仕組みですが、担う役割や得意とする領域は大きく異なります。どちらか一方だけではカバーしきれない場面があり、比較して理解することで自社に必要な対策が見えてきます。ここでは防御範囲、検知の仕組み、運用の観点からそれぞれの違いを整理します。主な違い:EPPは侵入前の防御、EDRは侵入後の検知と対応
EPPは端末に不正なプログラムが入り込む前にそれを防ぐ役割を持ちます。マルウェアの実行をブロックしたり、不審なファイルを隔離したりと、被害を未然に抑えるアプローチが中心です。一方EDRは侵入を完全に防げないことを前提に、端末内部で起こる異常な動きを素早く察知し、調査と対処につなげるための仕組みです。攻撃の痕跡を追跡し、被害の広がりを抑える点に重点があります。近年では、EPPやEDRに加えネットワーク側の情報まで横断的に分析する XDR(Extended Detection and Response) も注目されており、脅威把握の精度を高める取り組みが増えています。
検知技術の違い:シグネチャ、振る舞い検知、機械学習、リアルタイム分析
EPPは既知の脅威に強いシグネチャ検知や、怪しい動作を見つける振る舞い検知が中心で、近年は機械学習を採り入れた製品も増えています。ただし未知の攻撃手法に対しては判断が難しい場面もあります。EDRは端末上のプロセスや通信の動きを継続的に記録し、リアルタイムで分析する点が特徴です。異常の兆候をつかむことで、感染後の早期発見や原因追跡につなげられますが、判断にはある程度の知識や経験が必要になる場合があります。運用負荷の違い:EDRに求められる監視、ログ分析、アラート対応の実態
EPPは通常、導入後の運用負荷は比較的少なく、日々の監視が必要な場面は限定的です。対してEDRは端末から得られる大量のログを扱うため、アラートの確認や異常の調査といった運用作業が発生します。すべてを自動で処理できるわけではなく、状況判断が必要になることもあります。十分なリソースが確保できない企業では、運用支援サービスや監視の外部委託を併用するケースもあります。EPPとEDRの違いを理解し、自社の体制に合った運用を検討することが重要です。
製品ページへAI搭載・自律型EDRで進化するエンドポイント防御 >>
EPPはどのようにマルウェアを防ぐ?仕組み・機能・得意分野を知りたい
EPPはエンドポイントの入口を守る役割を担い、端末に不正なプログラムが侵入する前にブロックすることを目的とした仕組みです。いま主流となっているNGAVの登場により、従来型アンチウイルスだけでは対応しづらかった攻撃にも強くなりました。ここでは検知技術の仕組みや得意とする分野を整理しながら、EPPがどこまで防げるのかを確認していきます。従来型アンチウイルスとNGAVの違い(静的検知と振る舞い検知の比較)
従来型アンチウイルスは既知のマルウェアと同じ特徴を持つファイルを照合し、静的に検知する方式を中心としていました。既知の脅威には強い一方で、新しい手口や改変されたマルウェアには反応しづらい面があります。NGAVはその弱点を補うために、怪しい動きや通信といった振る舞いに着目する検知手法を取り入れています。ファイルの特徴だけでなく挙動も合わせて判断することで、新種の攻撃にも対応しやすくなるのが特徴です。マルウェア検出機能:シグネチャ、サンドボックス、機械学習の活用
EPPには複数の検知技術が組み込まれています。代表的なものがシグネチャ検知で、これは過去に確認されているマルウェアの特徴と一致するものを発見する仕組みです。サンドボックスは疑わしいファイルを隔離環境で実行し、悪意のある動作をするかどうかを確かめる機能です。さらに近年は機械学習が用いられ、特徴量や挙動の組み合わせから潜在的に危険なファイルを見極めるアプローチが増えています。それぞれの技術を組み合わせることで、幅広いパターンのマルウェアに対応できるようになっています。EPPで防げる攻撃と、防ぎきれないケースの具体例(ゼロデイ、標的型攻撃など)
EPPは既知のマルウェアや、振る舞いが明確な不正プログラムを防ぐことが得意です。メール添付ファイルによる感染や、改ざんされたウェブサイト経由の攻撃など、日常的に発生する多くの脅威に対して有効に働きます。一方で、防ぎきれないケースが存在します。脆弱性が公表される前に悪用されるゼロデイ攻撃や、特定の企業を狙って高度に準備された標的型攻撃では、挙動が巧妙すぎて入口で判別しきれないことがあります。こうした場面ではEPPだけに依存せず、侵入後の異常を見つけるEDRと組み合わせて対策を厚くする必要があります。EDRはどう脅威を可視化し、インシデント対応を支援するのか
EDRは端末の内部で起こる動きを継続的に記録し、異常の兆候をいち早く察知するための仕組みです。侵入を完全に防ぐことは難しいという前提のもと、被害を最小限に抑えるための可視化と調査、そして迅速な対処を支援します。ここではEDRがどのように情報を収集し、どのような流れでインシデント対応を支えるのかを整理します。ログ収集と分析で把握できる挙動(プロセス、通信、ファイル操作など)
EDRは端末上のプロセスの起動や終了、外部との通信、ファイルの読み書きといった挙動を時系列で記録します。普段の動きと比較しながら異常を判断するため、何がどのタイミングで起きたのかを細かく遡ることができます。攻撃の兆候が目立つわけではない場合でも、小さな不審な動作の組み合わせからリスクを把握できる点が特徴です。こうした継続的なログの収集が、後の原因追跡や影響範囲の確認にも役立ちます。また、ネットワーク上のふるまいを監視する NDR(Network Detection and Response) と組み合わせることで、端末単体では捉えにくい異常通信も把握しやすくなります。不審な動きをリアルタイム検知する仕組みとアラート発生の流れ
EDRは記録された挙動をリアルタイムで分析し、通常とは異なる振る舞いが見られた際にアラートを出します。たとえば短時間で大量のファイルが暗号化される動作や、不自然な外部通信が続くケースなどは、攻撃のサインとして通知される可能性があります。アラートはあくまで異常の可能性を示すものであり、必ずしも攻撃と断定できるわけではありませんが、早めの気づきにつながることが大きな利点です。EDR活用で可能になる対処:隔離、調査、原因追跡、復旧プロセス
EDRでは不審な端末をネットワークから隔離し、被害の広がりを防ぐといった初動対応を取ることができます。また、記録されたログをもとに攻撃の経路や影響範囲を調べ、どのような手口で侵入されたのかを追跡することも可能です。復旧作業に必要な情報を集めやすくなるため、被害からの立ち直りを早める効果が期待できます。ただし対応には一定の知識や判断が求められる場合があり、必要に応じて外部の支援サービスを併用するケースもあります。自社で対応が難しい場合は、専門チームが監視を担う SOC(Security Operation Center) の利用も選択肢に入ります。EPPとEDRは併用すべきか?企業の環境別に最適解は変わるのか
エンドポイントの脅威は年々多様化し、従来の防御だけでは対応しきれない場面が増えています。EPPとEDRはいずれも重要な役割を担いますが、どちらを優先すべきかは企業の環境や体制によって異なります。ここでは併用が推奨される背景や、組織規模ごとの選択基準を整理し、自社に適した導入判断のヒントをまとめます。併用が推奨される理由:防御と検知の両輪でリスクを最小化する必要性
EPPは入口での防御を担い、既知の脅威や不正なプログラムの侵入を可能な限り抑えます。しかし、すべての攻撃を完全に防ぎきれるわけではなく、巧妙な手口やゼロデイを前にすると限界が生じることがあります。EDRはその弱点を補い、侵入後の異常な挙動を早期に捉え、被害の拡大を抑える役割を持ちます。防御と検知を両輪で機能させることで、企業が抱えるリスクをより低く抑えやすくなるため、多くの組織で併用が選ばれています。企業規模、運用体制で変わる選択肢(中小企業、大企業、情報システム部のリソース)
中小企業では、まず入口の防御を確保するためにEPPを優先し、そのうえで余力に応じてEDRを追加するケースが多く見られます。大企業になると端末数や業務の複雑さから、侵入後の調査や影響範囲の把握が重要になり、EPPとEDRの併用が前提となる傾向があります。情報システム部の人員が限られている企業では、EDRの運用負荷が課題になりやすいため、外部の監視サービスや支援ソリューションと組み合わせて運用する方法も選択肢に入ります。ゼロトラスト時代のエンドポイント対策としてのEPP+EDRの位置づけ
ゼロトラストの考え方では、外部と内部を明確に分けて守るのではなく、常に端末の状態を確認し続けることが求められます。この前提に立つと、侵入前の防御だけで完結する仕組みでは不十分であり、内部の動きを継続的に把握するEDRが欠かせません。一方で防御の強化となるEPPも同時に必要で、両者を組み合わせてこそゼロトラストの思想に近づきます。EPPとEDRは競合するものではなく、役割を分担しながら総合的なエンドポイント対策を支える存在です。EPP・EDR導入のメリットとデメリットは何か
EPPとEDRはエンドポイントの強化に欠かせない存在ですが、導入すればすぐに安全が確保されるわけではありません。どのような効果が期待できるのか、また注意すべき落とし穴は何かを理解しておくことで、導入後の運用をより確実なものにできます。ここではメリットとデメリットを整理し、自社での活用イメージを具体的に描けるようにまとめます。メリット:侵入前防止、侵入後検知、可視化、被害抑制の強化
EPPは端末に不正なプログラムが入り込む前にブロックすることで、日常的に発生する脅威を広範囲に防ぎやすくなります。EDRは侵入後の異常な挙動を拾い上げ、攻撃の流れを可視化することで、早期発見や迅速な初動対応を支えてくれます。両者を組み合わせれば、防御と検知の両面からエンドポイントを守ることができ、ランサムウェアのような被害の拡大を抑制しやすくなります。また、境界防御として UTM(統合脅威管理) を併用することで、ネットワーク側の一次防御を強化しやすくなります。デメリット:コスト、運用負荷、アラート過多、専門知識の必要性
EPPとEDRをそろえて導入すると、どうしてもコストは増えがちです。特にEDRはアラート対応やログ調査といった運用作業が発生しやすく、専任の担当者がいない企業では負担を感じる可能性があります。また、アラートが多すぎて重要なものを見落とすケースもあり、適切なチューニングが求められます。判断には一定の知識が必要になる場面があるため、運用体制を整えることが不可欠です。導入しても機能しないケース(設定不備、運用リソース不足、放置状態)
せっかく導入しても、設定が不十分なまま放置されていると、本来の力を発揮できません。EPPでは定義ファイルの更新が止まっていたり、除外設定の誤りで検知が弱くなっていたりする場合があります。EDRでもログ収集設定が不完全だったり、アラートが確認されないまま積み上がっていたりすると、いざという時に対応できなくなります。ツール導入だけで安心せず、日々の運用を継続できる体制を事前に検討することが重要です。
製品ページへAI搭載・自律型EDRで進化するエンドポイント防御 >>
EPP・EDRを選ぶ際の比較ポイントは何か
EPPやEDRは製品ごとに仕組みや強みが異なり、自社の環境に合うかどうかで導入後の成果が大きく変わります。検知精度だけで判断してしまうと、運用が回らなくなったり既存システムと衝突したりすることもあります。ここでは導入前に確認しておきたい比較ポイントを整理し、失敗を避けるための視点をまとめます。検知精度とリアルタイム対応能力(未知の脅威への強さ)
まず注目したいのが、どの程度の精度で脅威を検知できるかという点です。既知のマルウェアに強い製品もあれば、機械学習や振る舞い分析により未知の攻撃に対応する力が高い製品もあります。EDRの場合、リアルタイムで挙動を監視し、異常の兆候をどれだけ早く把握できるかも重要です。検知の仕組みと反応速度は製品ごとに異なるため、自社が狙われやすい攻撃傾向や必要な対処スピードを踏まえて選ぶ必要があります。自社環境、業務アプリ、端末運用との親和性
どれほど高性能な製品でも、自社環境と相性が悪ければ運用が難しくなります。業務で利用しているアプリや既存のセキュリティソリューションとの干渉が起きないか、端末スペックに過度な負荷をかけないかを確認することが欠かせません。また、テレワーク端末やモバイルデバイスの運用が多い企業では、クラウド管理のしやすさやネットワーク制約下での動作も選定ポイントになります。運用サポート、監視サービス、MDRとの連携の有無
EDRは導入後の運用が難しくなる場合があり、アラート対応やログ分析に負担がかかることがあります。担当者のリソースが限られている企業では、製品提供元の運用サポートや監視サービスの有無が非常に重要です。MDR(Managed Detection and Response)のように専門家が調査や初動対応を支援してくれるサービスと連携できる製品であれば、運用体制の弱い企業でも安定したセキュリティレベルを維持しやすくなります。EDRだけで十分か?EPPだけで十分か?よくある疑問に答えるFAQ
エンドポイント対策を検討すると、多くの企業が「どちらか一方で十分なのか」という疑問を抱きます。コストや運用負荷を考えると、できれば最小構成で済ませたいという気持ちも自然なものです。ただし攻撃手法が多様化している今、一方だけで全てを守るのは難しいケースがあります。ここでは、よくある質問に答えながら、自社に合った判断軸を整理します。EPPだけで安全?防げない攻撃がある理由
EPPは侵入前の防御に強く、既知のマルウェアや一定の不審挙動を効果的にブロックできます。一方で、ゼロデイ攻撃や高度な標的型攻撃のように、検知ルールに引っかからない手口も存在します。振る舞い検知や機械学習を備えた製品でも、未知の攻撃を完全に防ぎきるのは難しい場合があります。EPPだけでは抜け道が残るため、防御の"土台"として位置づけつつも過信しない考え方が重要です。EDRだけ導入すればよい?侵入前に止める基盤が必要な理由
EDRは侵入後の挙動を可視化し、異常をいち早く察知できる点に強みがあります。ただし、そもそも攻撃を入口で止める仕組みが弱いと、日々大量のアラートが発生し、運用が追いつかなくなる恐れがあります。また、EDRは攻撃を未然に防ぐための仕組みではないため、初期段階の感染そのものを防ぎきれない可能性があります。入口の守りを固めるEPPと、内部の監視を行うEDRは役割が異なるため、片方だけでは偏りが生じやすくなります。結局どちらを優先すべき?企業の環境別に最適な選択
最適解は企業の体制や端末運用の状況によって異なります。たとえば人員リソースが限られている中小企業では、まず侵入前の防御力を高められるEPPの強化が優先される場合があります。一方、テレワーク端末が多く、攻撃対象になりやすい環境では、EDRによる監視も欠かせません。大企業やセキュリティチームを持つ組織では、EPPとEDRを併用し、ゼロトラストの考え方に近づける構成が一般的です。自社のリスクと運用体制を把握したうえで、段階的に最適な組み合わせを検討する姿勢が大切です。まとめ:EPPとEDRを正しく組み合わせ、エンドポイントの安全性を底上げしよう
EPPとEDRは、それぞれ役割が異なりながらも、どちらも現代のエンドポイントを守るうえで欠かせない存在です。侵入前の防御と、侵入後の可視化・対応。この二つを適切に組み合わせることで、より secure(安全)な端末環境を維持しやすくなります。とはいえ、企業によって抱える課題や運用体制は異なるため、自社にとって無理なく維持できる仕組みを選ぶことが大切です。定期的な見直しと、現場で扱いやすい運用設計を意識することで、エンドポイントの強化は着実に進んでいきます。エンドポイント対策をさらに実運用レベルで高めたい企業にとっては、EPPとEDRを導入するだけでなく、その組み合わせをどのように運用するかが重要になります。ハンモック社は AI 自律型 EDR の SentinelOne と AssetView Cloud + を組み合わせた MDR(監視・対応支援)サービスを提供しており、EPP・EDRを活かした多層防御に加えて、SOCによる監視や分析支援まで一貫した体制を整えられる点が特長です。
EPP+EDRの強みを実運用で最大限に引き出せるため、リソースが限られた企業にとっても現実的な選択肢になります。また、エンドポイント対策とあわせてIT資産管理や内部統制を整備したい場合は、「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策「AssetView CLoud +」の活用も有効です。外部脅威対策、資産管理、情報漏洩防止までを一つの基盤で扱えるため、セキュリティ全体を底上げしやすくなります。自社の環境や運用体制に合うかを検討しながら、最適なエンドポイントセキュリティの形を見つけてみてください。