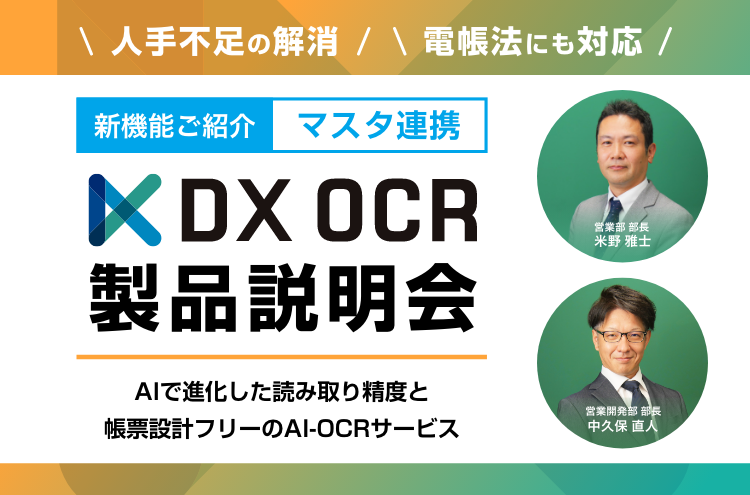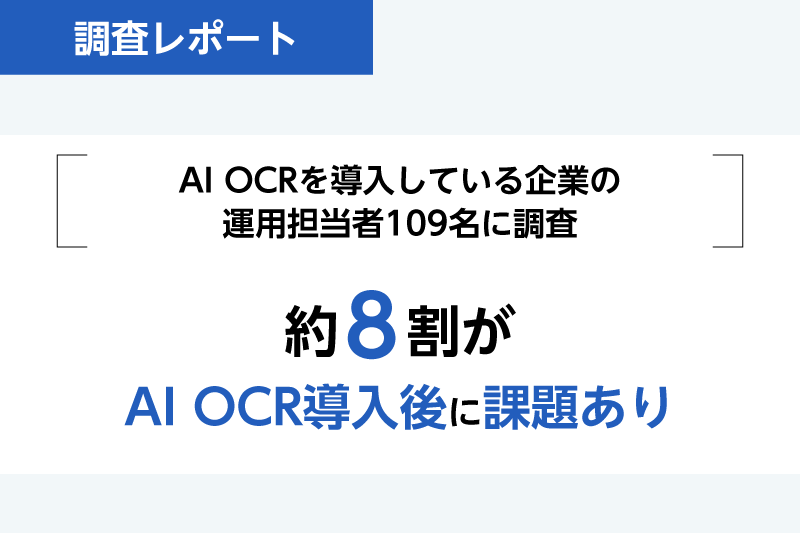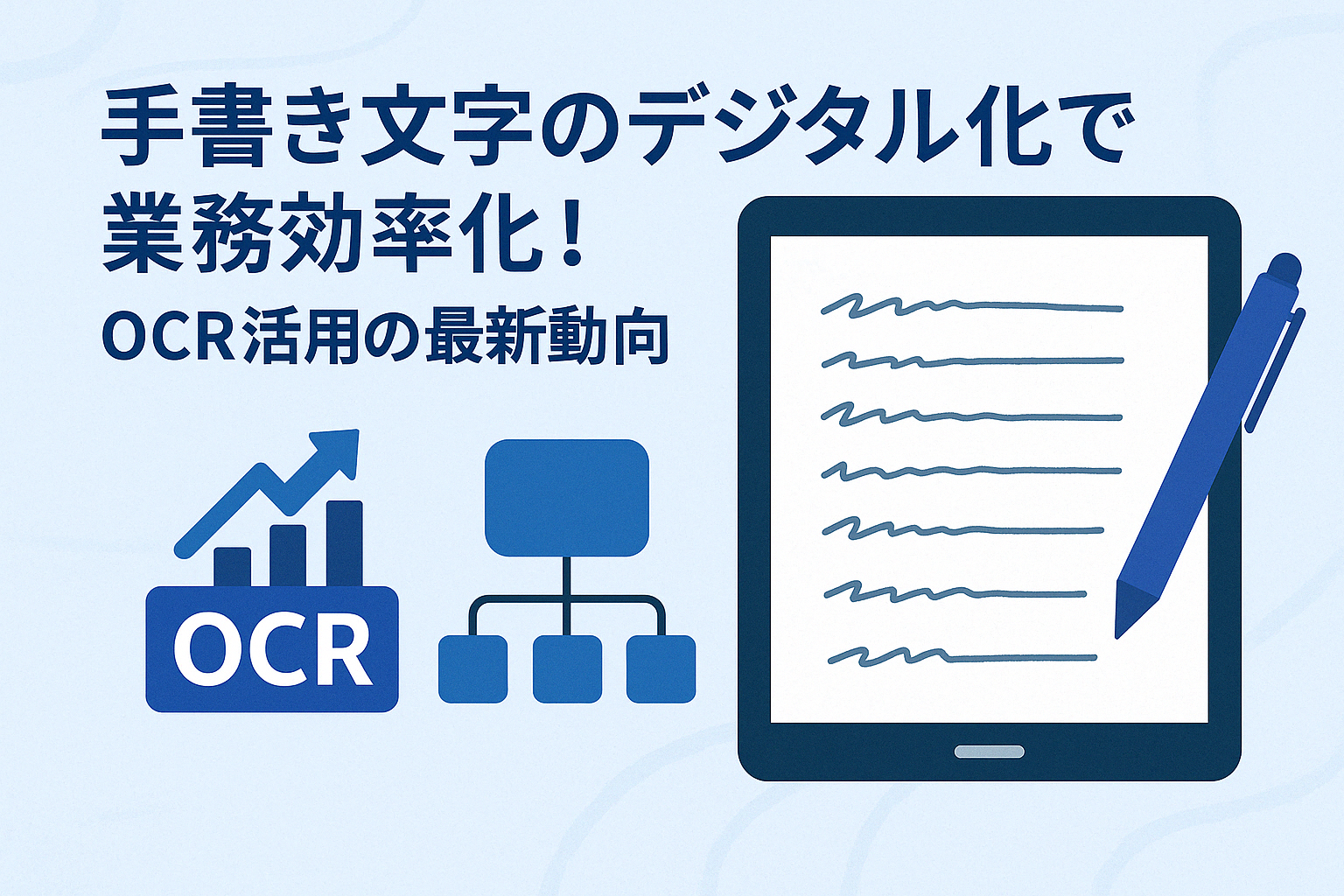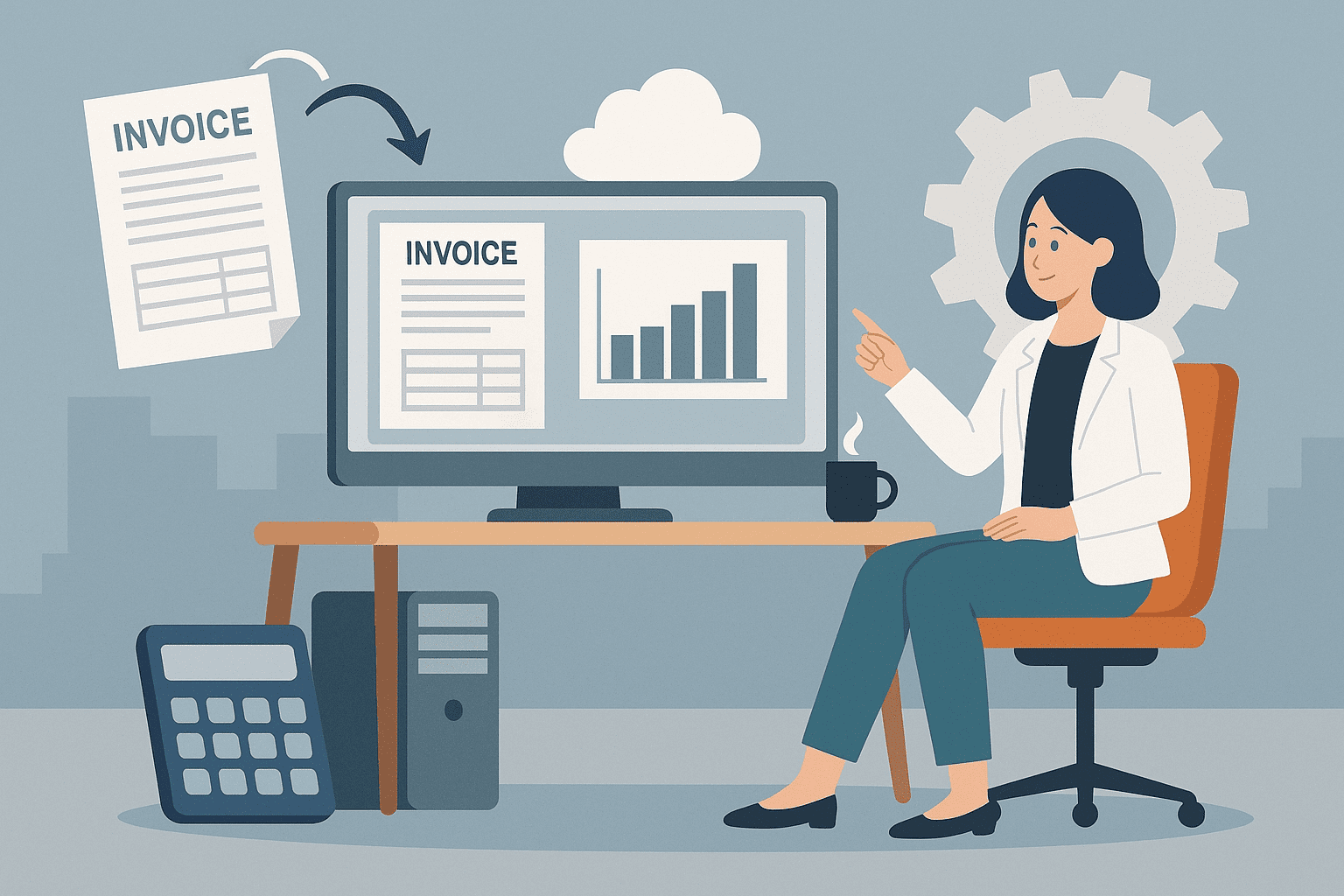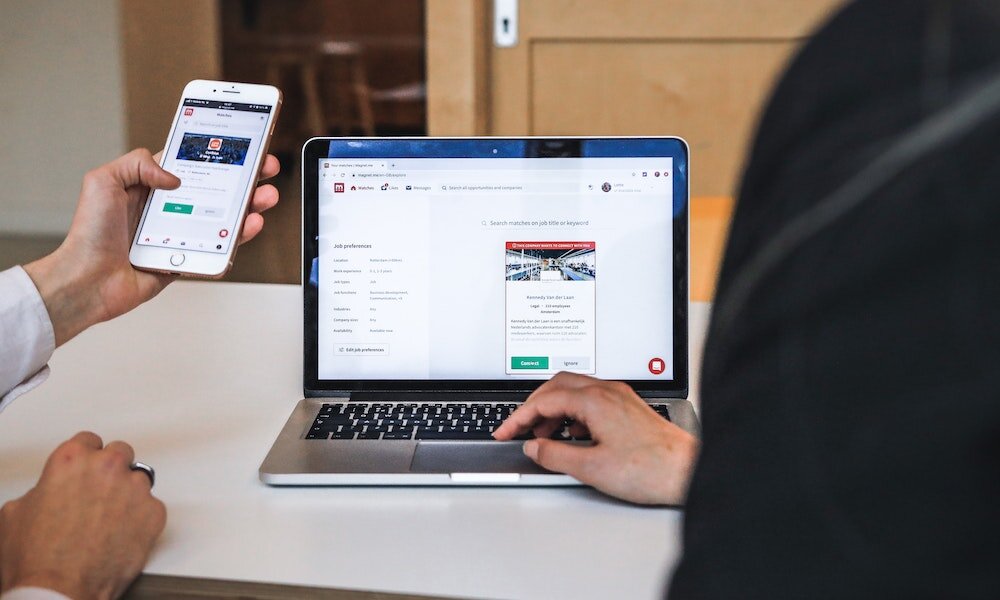OCRで領収書処理を効率化!仕組みと基本機能をわかりやすく解説
- INDEX
-
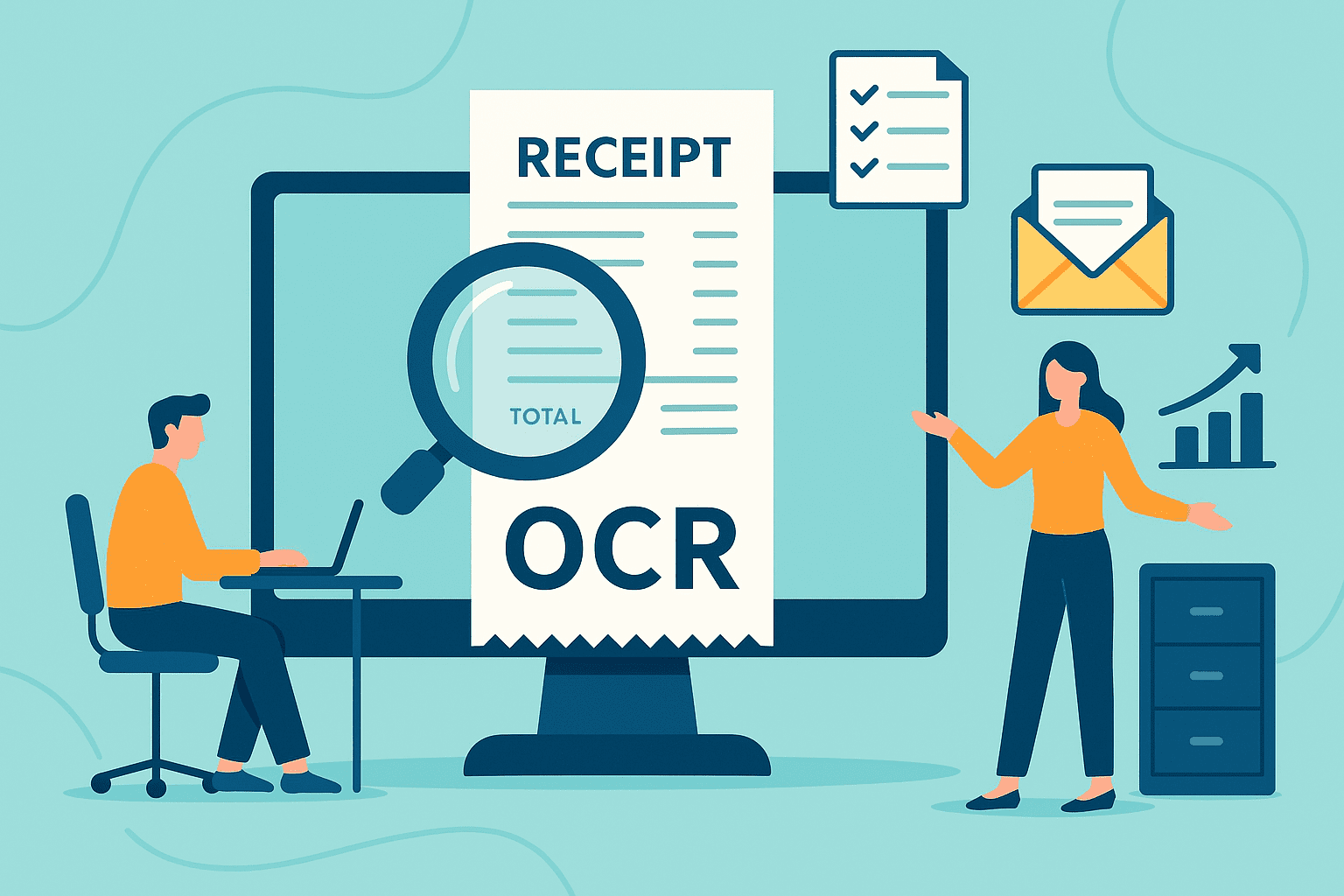
経費精算の現場では、領収書の処理が大きな手間となっています。こうした煩雑な作業を効率化する手段として注目されているのが、OCR技術です。紙の領収書に記載された日付や金額、店舗名などの情報を自動で読み取り、デジタルデータに変換することで、入力作業の負担を大幅に軽減できます。近年では、従来のOCRにAI技術を組み合わせたAI-OCRも登場し、より高精度な読み取りが可能になっています。
この記事では、OCRの仕組みやAIとの違い、領収書処理において読み取り可能な主な項目について、わかりやすく解説します。
領収書の読み取りにOCRが活躍!基本技術とできることを紹介
経費精算に欠かせない領収書の処理は、企業の現場において煩雑な作業のひとつです。書かれている内容を手作業で入力し、保管・管理するという流れには多くの時間と労力がかかります。こうした作業の効率化を実現する技術として、近年多くの企業が導入しているのが「OCR(光学文字認識)」です。OCRは、領収書に記載された情報を自動で読み取り、データ化することで経費精算業務を大幅に簡素化します。ここでは、OCRとAI-OCRの違いや、読み取り処理の流れ、対応可能な項目についてご紹介します。
OCRとは何か AIで何が変わったか
OCRとは、画像や紙に印字された文字を機械で読み取り、テキストデータに変換する技術のことです。たとえば、スキャンした領収書から「日付」や「金額」といった情報を抽出し、手入力することなくデータ化できるのがOCRの基本的な機能です。古くからある技術ではありますが、従来のOCRは印字された文字のみに対応し、手書き文字や複雑なレイアウトには不向きという課題がありました。
こうした弱点を補う形で登場したのが「AI-OCR」です。これはOCRに人工知能の解析技術を組み合わせたもので、文字だけでなく文脈やレイアウトも理解しながら情報を抽出します。手書き文字の認識精度が高く、レシートや領収書のように形式が一定でない書類でも、高い精度で読み取ることが可能です。経費精算にAI-OCRを活用すれば、入力の手間を減らすだけでなく、仕訳や項目分類といった後工程まで自動化できるようになります。
領収書処理におけるOCRの基本的な流れ
OCRを使った領収書の処理は、非常にシンプルです。一般的には、以下のような流れで行われます。
画像の取得(スキャンまたはスマホ撮影)
紙の領収書をスキャナやスマートフォンで撮影し、画像として取り込みます。最近では専用アプリを使ってそのままアップロードできるツールも多く登場しています。
OCRエンジンによる文字認識
取得した画像に対してOCRまたはAI-OCRを適用し、画像内の文字情報を解析。日付や金額、店舗名などの文字列を検出し、テキストデータに変換します。
経費精算ツールとの連携・自動入力
認識された情報は、事前に用意された経費精算フォームに自動入力されます。AI-OCRであれば、経費の種類を判別して適切な項目に振り分けることも可能です。
これらのプロセスにより、従来のような「読み取る → 書く → 確認する」という手作業が不要になり、スピーディかつ正確な精算処理が実現できます。
読み取り可能な主な項目(店舗名・日付・金額など)
OCRは、領収書のどのような情報を読み取れるのでしょうか。多くのOCR・AI-OCRツールでは、以下のような項目の自動認識に対応しています。
店舗名(発行元)
領収書に記載されている店舗や企業名。場合によってはロゴなどの画像情報からも名称を判断する仕組みが組み込まれています。
発行日(取引日)
取引が行われた日付。手書きや日本語表記、スラッシュ・ハイフンの違いなどにも対応できます。
金額(税込・税抜)
合計金額のほか、内訳の消費税や小計なども認識できます。税区分まで正確に読み取れるツールもあります。
支払い方法
「現金」「クレジットカード」などの支払い手段が記載されていれば、その内容も読み取って分類可能です。
摘要や品目
たとえば「昼食代」「タクシー代」といった内容が記載されていれば、それに応じた経費項目に割り振ることができます。
AI-OCRであれば、これらの情報を単にテキスト化するだけでなく、会社のルールに沿った仕訳や重複チェック、帳簿保存要件への対応といった機能も合わせて提供することが一般的です。単純な読み取りにとどまらず、業務全体を最適化する仕組みとして期待が高まっています。
経費精算業務における課題とOCR導入の効果
経費精算の現場では、領収書の処理が大きな負担となっています。ここでは、よくある課題とOCR導入による効果を簡潔に整理します。
手入力によるミスと負荷
領収書に書かれた情報を手入力する作業は、地味ながら非常にミスが起こりやすい工程です。金額の打ち間違いや記載漏れがあれば、申請は差し戻され、余計な確認作業が発生します。特に月末などの忙しい時期には、申請者・経理担当者ともに大きなストレスを感じやすくなります。
OCR導入による業務効率化と工数削減
OCRを活用すれば、領収書の撮影だけで情報が自動入力されるため、申請者の負担が一気に軽くなります。経理側でも、ミスや抜けの少ないデータを処理できるため、確認作業がスムーズに。差し戻しの回数が減ることで、全体の業務効率が確実に向上します。
年間削減できる時間・人件費の目安
1件の申請に5分かかるとしても、月30件×10人では年間300時間もの時間が失われています。OCR導入により、このうち7割以上の時間削減が可能になれば、年間200時間以上の工数カットが見込めます。人件費に換算すると数十万円規模の改善につながります。
無料で使える領収書OCRツールの実力
「OCRを試してみたいけれど、いきなり有料ツールを導入するのは不安」という声は少なくありません。実は、無料で使えるOCRツールにも、業務に役立つ機能を持ったものがあります。この章では、代表的な無料ツールの概要と、注意すべきポイントを紹介します。
GoogleドライブOCRの活用方法
もっとも手軽に使えるOCRツールのひとつが、Googleドライブに搭載されたOCR機能です。PDFや画像ファイルをGoogleドキュメントで開くと、自動的にテキストが抽出される仕組みで、領収書などの印刷物にも対応しています。
例えば、スマートフォンで撮影した領収書をGoogleドライブにアップし、「Googleドキュメントで開く」を選択するだけで、日付や金額などのテキスト情報を取得可能です。ソフトのインストール不要で、Googleアカウントがあればすぐに使える点が大きな魅力です。
他の無料ツールとの比較
無料OCRツールは他にも存在し、たとえばAdobe Acrobatの無料版や、いくつかの国産アプリでも簡易的なOCR機能が提供されています。ただし、対応できる文字数や画像解像度、レイアウトの複雑さへの対応力には差があります。
とくに領収書のようにレイアウトがバラバラだったり、手書きの要素が含まれる書類では、読み取り精度が不安定になる傾向があります。そのため、無料ツールを使う場合は、「読み取りやすい領収書」を中心に活用するなど、用途を限定した運用が向いています。
無料ツールの限界と有料版との違い
無料OCRはコストゼロで導入できる反面、いくつかの制約もあります。たとえば:
一方で、有料のAI-OCRツールであれば、領収書に含まれる項目の自動分類や、経費項目へのマッピング、さらには電子保存要件を満たす処理まで対応可能です。業務として安定的に活用するには、やはり有料ツールの導入を視野に入れる必要があるでしょう。
AI-OCRの強みと活用シーン
従来のOCRが「文字を読む」技術だったのに対し、AI-OCRは「意味を理解して処理する」技術へと進化しています。特に、領収書のように形式がばらばらで情報が分かりづらい書類において、AI-OCRはその真価を発揮します。ここでは、AI-OCRの優れた点と、実際の活用シーンを紹介します。
手書き領収書や複雑レイアウトへの対応
AI-OCRは、手書き文字や傾いた画像、背景がある画像など、一般的なOCRが苦手とする条件でも高精度な読み取りが可能です。ディープラーニング技術により、文字そのものだけでなく周囲の文脈やパターンを学習しているため、フォーマットの異なるレシートや、斜めに撮影された画像からでも正確に情報を抽出できます。
こうした性能は、出張先や現場で手書きの領収書を受け取ることの多い業種にとって、大きな助けとなります。
自動仕訳・経費項目の分類精度
AI-OCRは、読み取った情報をただテキストに変換するだけでなく、「この内容は交通費」「こちらは交際費」といったように、文脈をもとに経費区分まで自動で判断できます。これは従来のOCRにはない大きな強みです。
また、仕訳ルールを事前に学習させておくことで、会社独自の処理フローにも柔軟に対応でき、確認作業の手間も大幅に減らせます。
RPAやクラウドサービスとの連携で更なる自動化
AI-OCRは、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)や経費精算クラウドサービスとの連携により、業務全体を自動化する力を持っています。たとえば、領収書を撮影 → AI-OCRで読み取り → 経費システムへ自動入力 → 承認ワークフローへ送信、といった一連の流れを人手を介さずに実行できます。
これにより、申請から処理完了までの時間が短縮され、ヒューマンエラーや確認漏れのリスクも大きく軽減されます。特に業務量の多い部署や、拠点数の多い企業では、その効果がより顕著に表れるでしょう。
電子帳簿保存法・インボイス制度対応のポイント
領収書のデジタル化を進める上で避けて通れないのが、電子帳簿保存法とインボイス制度への対応です。OCRやAI-OCRを活用する際にも、これらの法制度に沿った運用が求められます。ここでは、最低限押さえておきたいポイントを整理します。
領収書の電子保存に求められる要件
電子帳簿保存法では、紙の領収書をスキャンして電子保存する場合、「真実性」と「可視性」の確保が必要とされています。具体的には以下のようなルールがあります:
OCRやAI-OCRを活用する際は、これらの条件を満たせるツールであるかを事前に確認する必要があります。
タイムスタンプ・真実性確保の方法
多くのAI-OCR搭載のクラウドサービスでは、スキャン後に自動でタイムスタンプを付与する機能を備えています。また、改ざん防止のためのログ記録や、アクセス権限の制御など、保存されたデータの真正性を保つ機能も標準で搭載されているケースが増えています。
自社でタイムスタンプ機能を用意する必要がある場合は、認定タイムスタンプサービスの利用が選択肢となります。
法対応済みOCRツールを選ぶ重要性
電子帳簿保存法やインボイス制度に準拠した運用を実現するには、制度対応済みのOCRツールを選ぶことが最も確実な方法です。特に2024年から本格運用が始まったインボイス制度では、請求書や領収書の記載項目が増えたため、OCRの読み取り精度が業務の正確性を左右します。
また、ツールによってはインボイス番号の有無を自動判別したり、課税区分に応じて処理フローを切り分けるといった機能もあり、業務負担の軽減に直結します。
領収書OCR導入ステップと注意点
OCRツールは便利そうだが、導入のハードルが高そうという印象を持たれている方も少なくありません。実際には、段階的にポイントを押さえながら進めることで、スムーズな導入が可能です。この章では、失敗しないための導入ステップと注意点を紹介します。
導入前に確認すべき業務フロー
まず最初に行うべきは、自社の経費精算フローを棚卸しすることです。
こうした流れを明確にすることで、OCRをどの工程に組み込むかが判断しやすくなります。
現状把握を怠ると、「導入はしたけれど活用できない」といった事態に陥るリスクが高まります。
ツール選定時のチェックポイント
OCRツールを選ぶ際には、精度・対応範囲・運用負荷の3点を意識すると失敗しにくくなります。
あわせて、すでに使用している経費精算システムやRPAとの連携性も確認しておくと、導入後の手戻りを防げます。
導入後の運用と社内浸透のコツ
OCRの効果を最大化するには、現場のスムーズな活用と継続的な改善が欠かせません。たとえば、操作マニュアルを簡易に整えたり、最初は一部部署に試験導入するなど、小さく始めてフィードバックを得ることで社内の不安を解消しやすくなります。
また、AI-OCRは使えば使うほど賢くなるため、「誤読があったときはどう修正するか」などのルールをあらかじめ決めておくと、運用が安定しやすくなります。
導入事例|OCRで変わった企業の経費精算
実際にOCRを導入した企業では、どのような変化があったのでしょうか。この章では、実際の導入事例から得られた効果や気づきを簡潔にご紹介します。
年間120時間削減に成功した事例
ある中堅の製造業では、毎月の経費申請が1人あたり約30件。入力・確認にかかる時間は1件あたり5分ほどで、年間に換算すると部門全体で約150時間を経費処理に費やしていました。
そこでAI-OCRを導入し、スマホ撮影→自動読み取り→申請フォーム反映というフローを整備。結果、年間で約120時間の削減に成功しました。とくに申請者側の作業時間が大幅に短縮され、繁忙期でもストレスなく処理できるようになったという声が挙がっています。
中小企業における段階的な導入成功例
従業員30名規模のサービス業では、「まずは営業部門から」の形でOCRを試験導入。紙の領収書が多く、入力作業のミスや差し戻しが多発していた現場に、読み取り機能付きのモバイルアプリを導入しました。
最初は操作に不安の声もありましたが、マニュアルを配布し、小規模なトライアルを重ねることで、半年後には全社導入へとスムーズに移行。現在では経理担当者の確認作業も約半分に減り、申請から承認までのリードタイムが大きく短縮されています。
領収書の関連業務を大幅に効率化|DX OCR
ここまで、AI技術を活用したOCRが、領収書処理における課題をどのように解決し得るのかを見てきました。ただ、実際に導入を検討する段階になると、「数あるツールの中で何を選べばいいのか」「自社の業務フローに本当に合うのか」といった疑問が浮かぶ方も少なくないはずです。
そうした不安に対して、ひとつの有力な選択肢となるのが、株式会社ハンモックの「DX OCR」です。高い認識精度と柔軟な対応力を兼ね備えたこのツールは、まさに"業務に寄り添うAI-OCR"として、経費精算の現場で力を発揮します。
DX OCRは、印字だけでなく手書き文字や複雑なレイアウトの領収書・レシートも正確に読み取ることが可能です。これにより、多様なフォーマットが混在する経費処理でも安定した運用が実現できます。読み取った情報は、日付・金額・店舗名・品目などに自動で分類され、入力ミスや確認作業の手間を大幅に削減します。さらに、既存の経費精算システムや会計ソフトと連携させることで、申請から承認、仕訳までの流れをスムーズに自動化できます。
もちろん、電子帳簿保存法やインボイス制度といった最新の法制度にも対応しており、コンプライアンス面でも安心です。「業務効率」「正確性」「法令対応」すべてを一歩進めたいとお考えの企業にとって、DX OCRは大きな力になるはずです。
詳しい機能や導入事例はこちら
まとめ|OCR活用で領収書処理の効率と信頼性を両立しよう
領収書処理に関する課題は、業種や規模を問わず多くの企業が抱えています。しかし、OCRをうまく活用すれば、入力作業の負担を減らし、確認の精度も高められます。特にAI-OCRは、単なる読み取りを超えて「業務全体の最適化」に寄与する実用的なツールです。
この記事を通じて、OCRの基本から無料ツール、AI-OCRの導入効果、法対応まで一通り理解いただけたはずです。
まずは自社の経費精算フローを見直し、小さく試しながら"ムリなく、ムダなく"業務改善を進めていきましょう。