多要素認証とは何か? 多要素認証を導入・運用する際の注意点や必要となる技術について
- INDEX
-

多要素認証(MFA)とは?仕組み・具体例・導入メリット・最新リスクまで徹底解説
セキュリティリスクが高まる現代のIT環境では、「パスワードだけの認証」では守りきれない場面が増えています。
そこで注目されているのが「多要素認証(MFA)」。
本記事では、多要素認証の意味や仕組み、よく混同されがちな二段階認証や二要素認証との違い、導入によるメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。さらに、導入時の注意点やMFAをすり抜ける攻撃手法、そして選定時のチェックポイントまで網羅的に紹介。
企業の情報システム部門やセキュリティ担当者にとって、「導入すべきかどうか」の判断に役立つ内容をお届けします。
多要素認証(MFA)とは?その仕組みと基本概念
情報セキュリティへの関心が高まる中、「パスワードだけでは不安」と感じる声が増えています。こうした背景を受け、注目されているのが「多要素認証(MFA)」です。多要素認証は、1つの方法に頼らず、複数の異なる情報を組み合わせて本人確認を行う仕組みです。この章では、認証とはそもそも何かという基本から、MFAの仕組みや関連用語の違いまでをわかりやすく解説します。
参照:総務省|2段階(だんかい)認証(にんしょう)や多要素(ようそ)認証でセキュリティを高めよう参照:IPA|不正ログイン対策特集ページ
そもそも認証とは何か?「本人確認」の基本
認証とは、ある人物が「本人であること」を確認する行為です。たとえば銀行で現金を引き出す際に、通帳やカード、暗証番号を提示することで本人確認が行われます。ITの世界でも同様に、パスワードやIDを使ってログインし、システムやデータへのアクセス権を確認します。
このような本人確認は、サービスを安全に利用するための最初の関門です。しかしながら、パスワードだけに頼った認証は、他人に知られたり推測されたりするリスクがあるため、より強固な方法が求められるようになってきました。
多要素認証の3つの要素(知識・所持・生体)
多要素認証は、異なる種類の情報を組み合わせて行う認証方式です。使用する情報の種類は、主に以下の3つに分類されます。
1つ目は「知識情報」。これはユーザーが知っている情報、たとえばパスワードやPINコードなどです。
2つ目は「所持情報」。スマートフォンやICカード、ワンタイムパスワードを発行するトークンなど、ユーザーが持っている物理的なアイテムがこれに該当します。
3つ目は「生体情報」。指紋や顔認証、虹彩スキャンなど、身体的な特徴を利用する認証方式です。
多要素認証では、これらのうち2つ以上を組み合わせて認証を行います。たとえば「パスワード+スマートフォンに届いた認証コード」や、「社員証+指紋認証」といった組み合わせが一般的です。1つの情報が盗まれても、もう1つの要素が残っていれば不正アクセスを防ぐことができるという仕組みです。
二段階認証・二要素認証との違い
多要素認証とよく似た言葉に、「二段階認証」や「二要素認証」があります。これらは混同されがちですが、それぞれ異なる意味を持っています。
二要素認証は、前述の3つの要素(知識・所持・生体)の中から、異なる2つを使って認証する方式です。たとえば、パスワード(知識)とスマートフォンの認証コード(所持)を使うのがこれにあたります。
一方、二段階認証は、認証プロセスが2回に分かれていることを指します。ただし、この2つの手段が必ずしも異なる要素であるとは限りません。たとえば「パスワード入力→メールで送られてきたリンクをクリック」といった認証も、2段階ではありますが、どちらも知識要素や通信手段に依存しており、厳密には多要素認証とは異なります。
言い換えれば、すべての二要素認証は多要素認証ですが、すべての二段階認証が多要素認証とは限らない、という関係になります。セキュリティを強化するうえでは、「異なる要素を組み合わせているかどうか」が重要なポイントです。
なぜ今、多要素認証が必要とされるのか
近年、セキュリティ対策の最前線において、多要素認証(MFA)の導入はもはや選択肢ではなく必須事項となりつつあります。その背景には、従来の「IDとパスワード」だけに依存した認証方法では守りきれない、さまざまなリスクの増加があります。
パスワードだけの限界:使い回し・漏えい・総当たり攻撃
私たちの多くは、複数のWebサービスで同じパスワードを使い回しているのが実情です。一見便利に見えるこの習慣は、万が一どこか1つのサービスで情報が漏えいした場合、他のサービスへの不正アクセスにもつながる危険をはらんでいます。
また、近年は「総当たり攻撃(ブルートフォース)」や「辞書攻撃」など、プログラムによる自動的なパスワード解析も高度化しています。人間が覚えられる範囲で考えたパスワードは、機械の前では無力です。こうした背景から、パスワードだけに頼った認証方法は限界に来ていると言えます。
クラウドサービスの普及とゼロトラストの流れ
クラウド環境の活用が進み、業務はオフィスの中だけで完結しなくなりました。リモートワークの一般化や、社外からのアクセスを前提とした働き方の広がりにより、従来の「社内ネットワークに入っているから安全」という前提は通用しません。
このような状況下で重視されるのが「ゼロトラスト」――"何も信用しない"という前提で、アクセスのたびに信頼性を確認するセキュリティモデルです。MFAは、このゼロトラストの考え方と非常に相性が良く、アクセスごとに本人確認を強化する手段として注目されています。
サイバー攻撃の高度化と多様化
攻撃者の手法も日々進化しています。フィッシングメールや偽サイトを使った情報詐取、ランサムウェアによる金銭要求、さらにはSNSなどの個人情報を悪用したなりすまし攻撃まで、その手口は多岐にわたります。
これらの攻撃は、「パスワードを知っている=本人である」という前提を簡単に覆してしまいます。多要素認証を導入することで、「知っている情報(パスワード)」に加え、「持っているもの(端末・アプリ)」や「本人にしかないもの(指紋・顔)」を組み合わせ、より強固な本人確認が可能になります。
つまり、攻撃者が突破すべき壁が増え、被害を未然に防ぐ可能性が高まるのです。
多要素認証の具体的な方法と活用シーン
多要素認証は、「知識」「所持」「生体」という3つの異なる要素を組み合わせることで、より強固な本人確認を実現する仕組みです。ここでは、それぞれの要素が具体的にどのような形で活用されているかを見ていきましょう。
知識要素:パスワード・暗証番号
知識要素とは、本人だけが知っている情報のことを指します。もっとも一般的なのが、パスワードや暗証番号です。例えば、メールアカウントにログインする際のパスワードや、ATMで使う4桁の暗証番号がこれに当たります。
ただし、知識要素は漏えいしやすいという課題があります。フィッシング詐欺やソーシャルエンジニアリング(人を騙して情報を引き出す手口)によって簡単に第三者に知られてしまう可能性があるため、他の要素との併用が推奨されます。
所持要素:スマートフォン・ICカード・トークン
所持要素とは、本人が「持っている」物理的なものです。代表的なのは、スマートフォンに届くワンタイムパスワードや、専用の認証アプリ、ICカード、USBキータイプのセキュリティトークンなどです。
この要素は、仮にパスワードが流出しても、それを持たない限りは本人になりすますことはできないという強みがあります。最近では、スマートフォンに送られる認証コードを使った二段階認証が、SNSやWebサービスなどで広く採用されています。
生体要素:指紋・顔・虹彩などの生体認証
生体要素は、その人自身にしかない「身体的特徴」に基づいて認証を行うものです。最も身近なのは、スマートフォンの指紋認証や顔認証です。他にも、虹彩(目の中の模様)や静脈パターン、音声なども利用されることがあります。
この要素は、紛失や盗難のリスクがなく、本人であることを高い精度で判別できるという点で非常に有効です。ただし、誤認識の可能性や、デバイスの精度・環境によって左右されるケースもあるため、単独での利用よりも他の要素と組み合わせた活用が一般的です。
実際の利用例:スマホロック解除、ATM、業務システム
私たちの生活の中でも、多要素認証はすでに幅広く活用されています。たとえばスマートフォンのロック解除では、顔認証や指紋認証に加えて、パスコードの入力を求める二重の仕組みが一般的になっています。
また、銀行のATMではキャッシュカード(所持要素)と暗証番号(知識要素)を組み合わせて本人確認を行っており、これも立派な多要素認証の一例です。
企業においては、社内システムやクラウドサービスへのアクセス時に、IDとパスワードに加えて、スマートフォンに届く確認コードやICカードの認証を求めるケースが増えています。これにより、情報漏えいや不正アクセスのリスクを大幅に軽減できます。
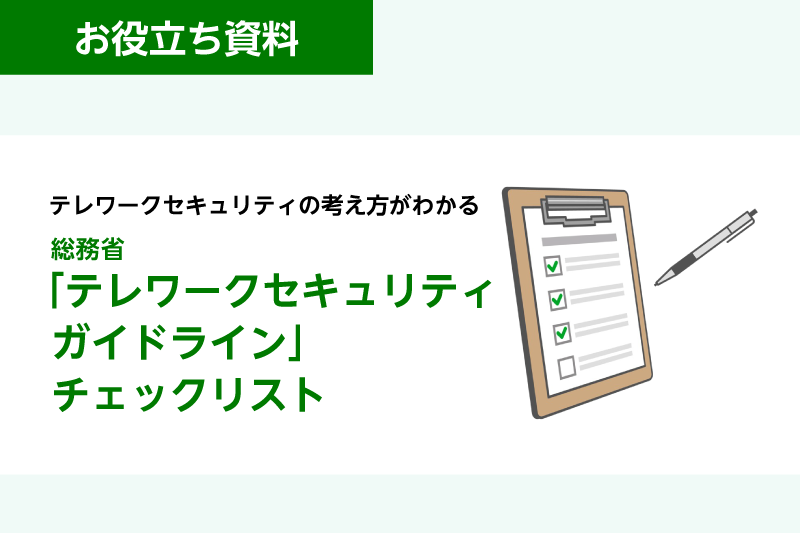
総務省『テレワークセキュリティガイドライン』 チェックリスト
総務省のテレワークセキュリティガイドラインの概要と対策方法、さらにテレワークセキュリティガイドラインのチェックリストもご紹介しております。
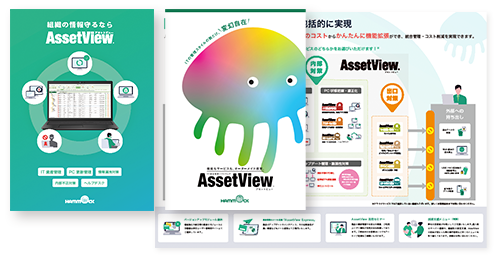
IT資産管理、ログ管理などのIT統合管理ソフトウェア『AssetView』は、お客様の状況に合わせたIT統合管理を実現。

多要素認証を導入するメリットと得られる効果
多要素認証(MFA)は、単なるセキュリティの強化にとどまらず、企業活動の信頼性や業務効率、法令遵守など多方面に好影響をもたらします。ここでは、多要素認証を導入することで具体的にどのようなメリットが得られるのかを整理してお伝えします。
なりすまし・不正アクセスの防止
多要素認証の最大の強みは、「なりすまし」のリスクを大幅に減らせる点にあります。たとえば、万が一パスワードが漏えいしたとしても、ユーザーが持つスマートフォンや本人の指紋認証が必要となるため、不正アクセスをブロックできます。
実際、企業の情報漏えい事件の多くはID・パスワードの使い回しや流出によるものです。MFAを導入することで、これらの攻撃手法に対する強力な防御線を築くことが可能になります。
従業員・取引先の認証強化と信頼性向上
社内システムだけでなく、パートナー企業や外部ベンダーとの取引においても、安全な認証基盤は信頼性に直結します。多要素認証を導入することで、「誰が」「いつ」「どこから」アクセスしているかを可視化・管理しやすくなり、業務の透明性が向上します。
また、テレワークや出張先など、社外からのアクセスが日常的になる中で、ユーザーごとに安全性を担保できる体制は、従業員の安心感や業務効率にもつながります。
セキュリティ基準・法令対応(ISMS、ゼロトラストなど)
多要素認証は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)や、ゼロトラスト・セキュリティの考え方においても重要な要素とされています。特にゼロトラストでは、「すべてのアクセスは常に疑う」という原則のもと、認証を強化する仕組みが欠かせません。
また、金融や医療などの特定業界においては、法令やガイドラインで多要素認証の導入が求められているケースもあります。そうした規制への対応としても、MFAの導入は有効な手段と言えます。
多要素認証の注意点とよくある課題
多要素認証は非常に強力なセキュリティ手段ですが、導入や運用には注意すべき点もいくつか存在します。ここでは、導入を検討する際に押さえておきたい課題とその背景を解説します。
導入・運用コストがかかる
多要素認証を実装するには、システムやデバイスの導入費用、運用・保守のコストが必要です。特に、中小企業や一部の部署のみ導入するケースでは、費用対効果の見極めが難しいこともあります。
また、生体認証やハードウェアトークンなどを活用する場合は、初期投資だけでなく、機器の更新・管理にかかるコストも発生します。導入規模や目的に応じた慎重な設計が求められます。
ユーザーの利便性とのトレードオフ
セキュリティを強化する一方で、ユーザーの利便性が損なわれる場合もあります。たとえば、認証のたびにスマートフォンを使わなければならない、指紋認証がうまく機能しない、といった状況がストレスにつながることもあります。
特にITリテラシーのばらつきがある企業では、導入初期に混乱が生じやすいため、丁寧な説明とサポート体制の整備が重要です。
認証デバイスの紛失・盗難リスク
所持要素を用いた認証では、スマートフォンやICカードなどの「認証デバイス」が不可欠です。そのため、これらを紛失した場合の対応が重要になります。
たとえばスマートフォンの紛失時、万が一悪意ある第三者に拾われた場合でも、追加の生体認証などで守られていればリスクは軽減されますが、すぐに再発行やロックを行える体制が必要です。
企業としては、端末の管理方針や紛失時の対応フローをあらかじめ明確にしておくことが求められます。
進化する脅威:多要素認証をすり抜ける攻撃に注意
多要素認証は強力なセキュリティ手段ではありますが、近年ではその仕組みを逆手に取った攻撃も報告されています。「多要素=絶対安全」とは限らない現実を踏まえ、最新の攻撃手法とその対策を知っておくことが重要です。
参照:Verizon|2025年データ侵害調査報告書参照:IPA: 情報セキュリティ10大脅威
MFA疲労攻撃(MFA Fatigue)とは
MFA疲労攻撃とは、ユーザーに多要素認証の通知を何度も送りつけて、うっかり「承認」をタップしてしまうのを狙った攻撃です。たとえば、スマートフォンに届く認証通知を何度も表示させて、面倒に感じたユーザーが誤って許可してしまう、といった状況が狙われます。
この手法は、特にプッシュ通知型の認証を導入している場合にリスクが高く、攻撃者が認証情報を不正に入手した後に実行されることが多いです。対策としては、「異常な回数の認証要求があった場合はブロックする」などの制御をシステム側で設ける必要があります。
MFAを狙ったフィッシングや中間者攻撃
従来のフィッシング攻撃も進化しており、多要素認証の情報を盗み取る手口が登場しています。たとえば、中間者(MITM)攻撃によって、ユーザーが正規のログイン画面だと思い込んで入力した情報をリアルタイムで盗み取り、その場で攻撃者がログインを試みるケースもあります。
こうした手口では、多要素認証の「2つ目の要素」すらも攻撃者が手に入れてしまうことがあるため、ログインページの真正性を確認する訓練や、フィッシング対策ソリューションの導入が有効です。
セキュリティは「万能」ではない前提で設計する
多要素認証を導入すれば絶対に安全というわけではなく、「破られる可能性がある」ことを前提に対策を講じることが、現代のセキュリティ設計では不可欠です。
たとえば、多要素認証に加えてアクセス元のIP制限を設けたり、端末の脆弱性を検出する機能を加えたりと、複数の層で防御を構築する「多層防御」の考え方が推奨されます。
また、万が一の事態に備えたインシデント対応フローを社内で整備しておくことも、被害拡大を防ぐうえで欠かせません。
多要素認証を選ぶ際のチェックポイント
多要素認証の導入は、セキュリティ強化の手段であると同時に、業務の効率やユーザー体験にも大きな影響を与えます。単に「安全そうだから」ではなく、自社の状況に最適な方式を選定することが重要です。ここでは、導入時に確認すべき主なポイントを解説します。
自社システムや業務フローとの適合性
まず重要なのが、自社が現在利用しているシステムや業務プロセスに無理なく組み込めるかどうかです。たとえば、クラウドサービス中心の環境であれば、SaaS連携が容易な認証方式を選ぶと導入がスムーズです。また、業務上スマートフォンの利用が制限されている職場では、物理トークンやICカード型の方式が現実的です。システム全体との親和性を十分に確認することが、運用負荷の最小化につながります。
ユーザー規模・運用体制に応じた方式選定
多要素認証は、従業員数や管理体制の規模によって適切な方式が変わります。たとえば、大企業であれば一括管理・自動配布が可能なクラウド型サービスが向いています。一方、中小企業ではコストを抑えつつ運用できるソフトウェア型認証や、スマートフォンアプリでの対応が現実的です。IT部門の体制やサポート範囲も含め、運用可能な範囲で選ぶことが肝要です。
災害・障害時の対応フローの確立
セキュリティを強化しても、災害や通信障害などによって認証手段が使えなくなるリスクも想定しておかなければなりません。スマートフォンを紛失した場合やネットワークが使えない状況に備えて、代替手段や管理者による緊急対応のフローを明文化しておくことが重要です。また、定期的な訓練やマニュアル整備により、非常時にも迅速な対応が可能な体制を整えましょう。
現代の脅威から情報を守るAssetView
今日のデジタル環境では、多要素認証(MFA)がセキュリティの強力な盾となることはご理解いただけたかと思います。しかし、MFAをすり抜ける巧妙な攻撃が存在することも事実です。そうした進化する脅威に対して、企業はMFAだけでなく、多層的な防御策を講じる必要があります。
ハンモック社の「AssetView」は、まさにこの多層防御を実現するための統合IT資産管理ソフトウェアです。AssetViewは、単にIT資産を管理するだけでなく、情報漏えいや不正アクセスといった様々なセキュリティリスクから企業を守る機能を提供します。
例えば、記事中で触れた「MFA疲労攻撃」や「中間者攻撃」などの脅威に対しては、AssetViewのデバイス制御機能やログ監視機能が有効です。これにより、不正な接続や不審な挙動を早期に検知し、未然に防ぐ、あるいは迅速に対応することが可能になります。また、セキュリティポリシーの徹底や脆弱性管理を通じて、MFA単体ではカバーしきれない部分を強化し、より堅牢なセキュリティ体制を構築できます。
多要素認証を導入し、さらにその効果を最大化したいとお考えであれば、AssetViewが強力な選択肢となります。貴社の情報資産を包括的に保護し、より安全で効率的なIT環境を実現するために、ぜひ下記URLから詳細をご確認ください。
まとめ|多要素認証の重要性と導入時に意識すべきポイント
多要素認証(MFA)は、従来のパスワード認証に比べて格段に高いセキュリティを実現できる手段として、あらゆる業種・業態で導入が進んでいます。その仕組みは「知識」「所持」「生体」といった異なる種類の認証要素を組み合わせることで、1つの情報が漏れても突破されにくい構造をつくることにあります。
また、クラウドサービスの普及やゼロトラストの考え方が浸透する中で、単一の認証に頼らないアクセス制御の必要性も高まっています。一方で、導入・運用のコストやユーザー体験への影響、さらにはMFAを狙った巧妙な攻撃も存在するため、過信は禁物です。
多要素認証を導入する際は、自社の業務フローやユーザー環境を丁寧に見直し、「セキュリティ強化」と「利便性・継続性」のバランスを慎重に見極めることが求められます。適切な選定と継続的な見直しにより、MFAは企業の情報資産を守る強力な盾となります。
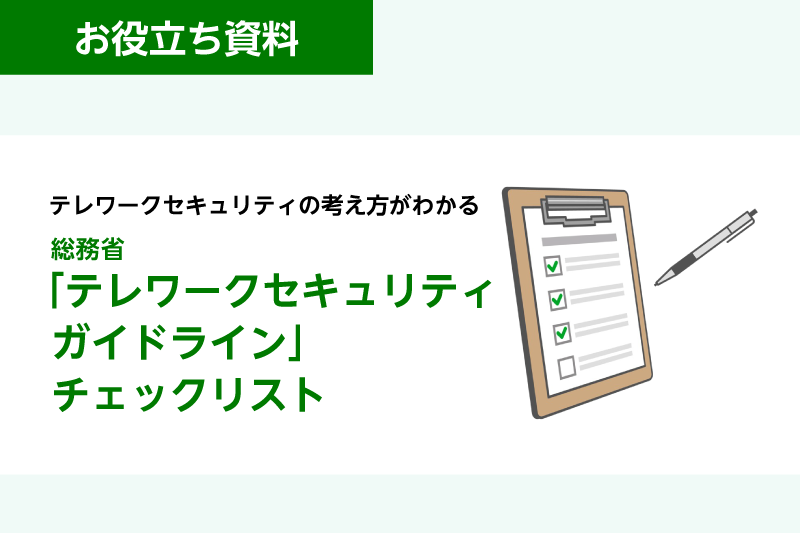
総務省『テレワークセキュリティガイドライン』 チェックリスト
総務省のテレワークセキュリティガイドラインの概要と対策方法、さらにテレワークセキュリティガイドラインのチェックリストもご紹介しております。
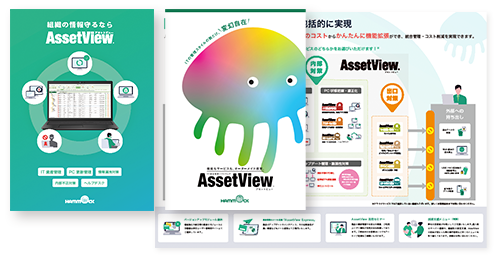
IT資産管理、ログ管理などのIT統合管理ソフトウェア『AssetView』は、お客様の状況に合わせたIT統合管理を実現。






































