ブルートフォース攻撃とは?仕組み・被害・具体的な対策まで徹底解説
- INDEX
-
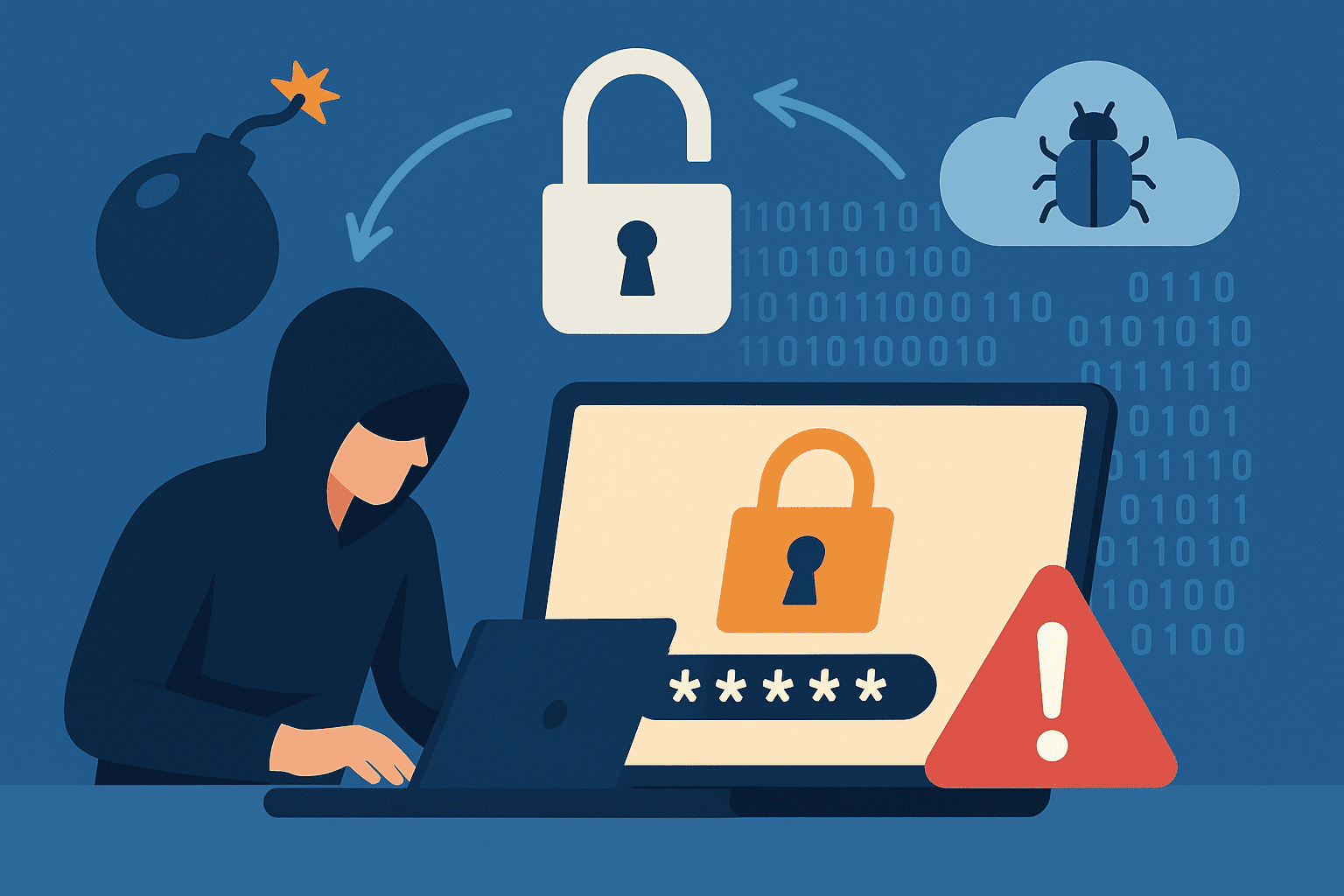
ブルートフォース攻撃とは?仕組み・被害・具体的な対策まで徹底解説
近年、企業のWebサービスや社内システムが「総当たり攻撃(ブルートフォース攻撃)」によって不正アクセスのリスクにさらされるケースが急増しています。特に、パスワードの使い回しや簡易な認証設定は、攻撃者にとって格好の標的です。
本記事では、ブルートフォース攻撃の仕組みや手口、辞書攻撃・リバースブルートフォースとの違い、実際の被害事例について詳しく解説します。また、ブルートフォース攻撃から企業や個人のシステムを守るために取るべき具体的な対策まで、包括的にご紹介します。あわせて、IT資産管理ツール「AssetView」を活用した多層的な防御手段にも触れながら、今すぐに実践できるセキュリティ対策のヒントをお届けします。
ブルートフォース攻撃とは?
企業の情報システムやWebサービスが外部から狙われる中で、今なお根強い手口のひとつが「ブルートフォース攻撃」です。これは"鍵の番号がわかるまで、全通り試してこじ開けようとする"力任せの攻撃タイプで、「総当たり攻撃」や「力任せ攻撃」とも呼ばれています。
ブルートフォース攻撃(Brute-force attack)は、主にログイン認証を突破することを目的としたサイバー攻撃の一種です。攻撃者は、考えうるすべてのパスワードの組み合わせを順番に試すことで、正解のパスワードを突き止めようとします。たとえば、「123456」や「password」といった簡易な文字列は、最初に狙われる可能性が高く、わずか数秒で突破されることもあります。
似たような攻撃手法として「辞書攻撃(Dictionary attack)」や「パスワードリスト攻撃(Credential Stuffing)」があります。辞書攻撃は、よく使われる単語やパスワードを集めたリストをもとに試行する方法であり、ブルートフォース攻撃よりも効率的に突破を狙うものです。一方、パスワードリスト攻撃は、過去に流出したID・パスワードの組み合わせを使って別のサービスへのログインを試みるもので、使い回しパスワードが多い現代において特に深刻な脅威となっています。
こうした攻撃はいずれも、自社システムのログイン認証が「簡単すぎる」状態を突くものです。そのため、複雑で予測されにくいパスワードを使うだけでなく、システム側での防御策もあわせて講じる必要があります。
ブルートフォース攻撃の手法と種類
ブルートフォース攻撃と一口に言っても、その手法にはいくつかのバリエーションがあります。攻撃者は目的やターゲットによってアプローチを変え、最も効果的な手段を選択しています。ここでは代表的な4つの手法を紹介し、それぞれの特徴やリスクについて見ていきましょう。
総当たり型攻撃とは
総当たり型のブルートフォース攻撃は、最も原始的でありながら依然として有効な手段のひとつです。攻撃者は、考えられるすべての文字列の組み合わせを1つずつ試し、正しいパスワードを突き止めようとします。たとえば「a」「aa」「aaa」......といったように、機械的にすべてのパターンを網羅していくイメージです。
この手法では、パスワードの文字数(桁数)と文字の種類(英数字・記号など)によって、試行回数が指数関数的に増加します。逆にいえば、短く単純なパスワードは、あっという間に破られてしまう可能性があるということです。現代では、コンピューターの処理速度向上により、数百万件の試行を一瞬で実行できるようになっているため、軽視できない脅威となっています。
パスワードリスト型攻撃とは
パスワードリスト型攻撃は、以前にどこかのサービスから漏えいしたIDとパスワードの組み合わせ(認証情報)を使って、他のサイトやシステムへの不正ログインを試みる手法です。総当たりとは異なり、「すでに実在する情報」をもとに効率的な突破を狙う点が特徴です。
この攻撃が効果を発揮する背景には、多くの人が複数のサービスで同じID・パスワードを使い回しているという現実があります。たとえば、ショッピングサイトで使っていたパスワードが流出し、それを使って会社の業務システムにログインされてしまう──そんなシナリオも十分にあり得るのです。
辞書攻撃との違い
ブルートフォース攻撃と混同されがちな辞書攻撃は、予め用意された「よく使われる単語やフレーズ」のリストを用いてパスワードを試す方法です。たとえば、「password」「qwerty」「12345678」といったありがちなパスワードを一気に試していきます。
違いとしては、辞書攻撃がリストベースの試行であるのに対し、総当たり型はあくまで文字の組み合わせをすべて試すという点です。効率性の面では辞書攻撃が有利ですが、対象となるパスワードがリストに含まれていない場合には無力です。
リバースブルートフォース攻撃とは
リバースブルートフォース攻撃は、通常とは逆の発想で行われる手法です。つまり、「パスワードをひとつに固定」し、それに対して多数のIDやユーザーアカウントを組み合わせて試していくというものです。たとえば、「password123」というパスワードを用いて、社内の複数の社員アカウントに次々とログインを試みるようなケースです。
この攻撃は、パスワードが単純かつ広く使われている場合に特に効果を発揮します。また、botなどの自動化ツールを使って高速かつ無差別に試行されることが多いため、通常の監視では見落とされやすいという厄介な特徴もあります。
ブルートフォース攻撃による具体的な被害
ブルートフォース攻撃は、単なるログイン突破だけにとどまらず、その先にある情報資産や企業の信用をも揺るがす深刻な被害を引き起こします。ここでは、現実に起こりうる被害とその影響について、4つの観点から見ていきます。
個人情報・機密情報の漏洩
最も深刻で、かつ広範に影響を及ぼすのが個人情報や企業の機密データの漏洩です。攻撃者が不正ログインに成功すると、顧客データベースや従業員の情報、契約書、設計図といった重要情報にアクセスできてしまう可能性があります。
こうした情報は、闇市場で売買されるだけでなく、さらなるサイバー攻撃の足がかりとして利用されることもあります。特に医療機関や教育機関では、個人情報に加え、病歴や学習履歴といったセンシティブな情報が含まれているため、漏洩時の社会的影響も大きくなります。
Webサービスや業務システムの乗っ取り
ブルートフォース攻撃が成功すると、攻撃者は正規ユーザーになりすまして操作が可能になります。これにより、ECサイトの管理画面、予約システム、クラウド上のファイル管理などに不正アクセスされ、サービスが停止したり、データが書き換えられるリスクが発生します。
特にSaaSやクラウドサービスの活用が進む中で、「ログイン情報=鍵」という構図はますます重要性を増しています。攻撃者に鍵を渡してしまえば、内部の資産や業務フローが丸裸になる危険性があるのです。
企業サイトの改ざんやなりすまし
一度ログインに成功した攻撃者は、Webサイトのコンテンツを改ざんしたり、不正リンクを埋め込んだりすることで、訪問者にマルウェアを配布するケースもあります。また、企業のメールアカウントを乗っ取って、あたかも正規の担当者を装い、取引先とやりとりする「なりすまし攻撃」も現実的な脅威です。
このような攻撃は、企業の信用を大きく損なうだけでなく、取引先や顧客にも被害が及ぶため、ビジネス全体の継続性にも影響を及ぼしかねません。
二次被害(他サービスへの不正アクセス連鎖)
ブルートフォース攻撃による初期突破が「入り口」にすぎない場合もあります。ひとつのサービスでログインに成功すると、同じID・パスワードの組み合わせで他のサービスにも次々と侵入されるという「連鎖的な不正アクセス」が引き起こされるのです。
たとえば、2019年に発生した「セブンペイ」の不正アクセス事件では、他サービスから流出したID・パスワードが悪用され、約900人分のアカウントが乗っ取られ、およそ5,500万円分の不正利用が行われました。攻撃自体は単純でも、使い回された情報が被害を拡大させた典型例といえます。
ブルートフォース攻撃の検知・兆候とは?
ブルートフォース攻撃は、単発の強力な攻撃というよりも、静かに・執拗に・繰り返される性質を持っています。そのため、十分な監視体制が整っていない環境では、攻撃を受けていること自体にすぐには気づけないケースも少なくありません。
攻撃者は、数時間〜数日かけて断続的にパスワードの試行を繰り返すこともあり、一見すると通常のアクセスと見分けがつきにくいのです。特にクラウドサービスや社外アクセスが日常的になっている企業では、「不審な挙動」を見逃しやすい傾向があります。
では、ブルートフォース攻撃の兆候として、どのような動きが現れるのでしょうか。以下のようなログイン周りの異常は、早期検知の重要な手がかりになります。
こうした挙動を見逃さないためには、ログイン履歴の監視やアラート設定が欠かせません。特に中規模以上の企業では、SIEM(Security Information and Event Management)ツールの導入により、複数システムのログを一元的に収集・分析し、攻撃の兆候を早期に検知する体制を整えることが効果的です。
また、IT資産管理ツールの中には、不審な操作をリアルタイムで検知・記録する機能を備えたものもあります。これらのツールを活用することで、「いつ」「どこで」「誰が」不自然な動きをしたのかをすばやく把握でき、被害の未然防止につなげることができます。
企業・個人が実践すべきセキュリティ対策
ブルートフォース攻撃は、対策の基本をしっかり実行するだけでも被害を大きく減らすことができます。ここでは、企業・個人がすぐに取り組める6つの重要なポイントを紹介します。
長く複雑なパスワードを設定する
まず最も基本的な対策は、桁数が長く、複雑なパスワードを設定することです。英大文字・小文字、数字、記号を組み合わせた12文字以上のパスワードが理想です。機械的な攻撃に対しては、「時間をかけさせる」ことが防御につながります。
参照:内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)|パスワードは何桁なら大丈夫?
パスワードの使い回しを避ける
いくら強力なパスワードを使っていても、それを複数のサービスで使い回していると、ひとつの情報漏えいが連鎖的な不正アクセスを招く原因になります。パスワード管理ツールの導入なども視野に入れ、サービスごとに異なるパスワードを使いましょう。
多要素認証(MFA)の導入
IDとパスワードだけでなく、別の要素(例:スマートフォンに届く認証コード)を使って本人確認を行う「多要素認証」は、ブルートフォース攻撃に対する強力な防御策です。たとえパスワードが突破されても、攻撃者は次のステップで止められます。
ログイン試行回数の制限設定
一定回数以上のログイン失敗があった場合に、アカウントを一時ロックしたり、警告を表示する設定は、ブルートフォース攻撃を抑止するうえで効果的です。システム管理者は、エラーログの監視も合わせて行うとよいでしょう。
アクセス制限(IP制限、地域制限など)
業務システムなどは、アクセス元のIPアドレスや国・地域を制限することで、海外や想定外のアクセスを未然にブロックすることが可能です。特に社内専用システムの場合は、明確な制限をかけておくことが安全対策の第一歩です。
不正ログインの検知・アラートを設定する
万一、攻撃が始まってしまっても、素早く気づける仕組みがあれば被害は最小限に抑えられます。ログインエラーの多発や異常な時間帯のアクセスに対して、メールやアラートで通知する設定を行いましょう。IT資産管理ツールやSIEM製品には、こうした機能を備えているものもあります。
ブルートフォース攻撃の主な被害事例
実際にブルートフォース攻撃によって被害を受けた事例は、枚挙にいとまがありません。ここでは、特に影響が大きかった2つの事例を取り上げ、その背景と再発防止策まで整理します。
大手決済サービスへの不正アクセス(例:セブンペイ)
2019年に発生した「セブンペイ」の不正利用事件は、日本国内で大きな注目を集めました。攻撃者は、他サービスで流出したIDとパスワードを使ってアカウントに不正ログインし、チャージ金額を不正に使用。約900人の利用者が被害に遭い、被害総額は5,500万円以上にのぼりました。
原因は、パスワード使い回しのリスクに対する認識不足と、多要素認証の未実装でした。事件後、セブンペイはサービスを廃止し、認証強化の必要性が社会的に再認識されるきっかけとなりました。
参照:「7pay」決済サービス、開始早々の大量不正アクセスで約900名/5500万円の被害
大学病院での個人情報流出
ある国立大学附属病院では、職員のメールアカウントがブルートフォース攻撃を受け、不正ログインされる事件が発生しました。この結果、416人分の患者情報が流出し、病院側は謝罪とともに再発防止策の徹底を表明しました。
この事例では、アカウント管理の甘さとログイン試行の監視不足が問題とされました。病院ではその後、パスワードポリシーの強化と外部アクセス制限の導入、不審ログインの自動検知システムの運用開始など、複数の改善措置が取られています。
AssetViewがブルートフォース攻撃対策を支援する理由
ブルートフォース攻撃は、パスワードさえ突破されれば、内部の機密情報や業務基盤にまで影響が及ぶ、深刻なサイバーリスクです。対策の基本は、パスワードポリシーやアクセス制限などの運用管理ですが、それらを確実に継続するための仕組みがなければ、現場では見落としや対応の遅れが生じてしまうこともあります。
こうした課題を解決する手段として注目されているのが、統合型IT資産管理ツールの「AssetView」です。AssetViewは、端末管理・アクセス制御・不正利用の可視化を一元化し、組織のセキュリティ運用を効率化する統合型ツールです。
たとえば、あらかじめ登録された管理端末以外からのアクセスは自動的に遮断され、組織内ネットワークへの不正利用を防止します。
また、管理対象外のPCが検知された場合は、台帳上で「AssetViewの未インストール端末」として可視化され、導入漏れや不正利用の早期発見につながります。
これにより、システム管理者は社内端末の利用状況を正確に把握できるだけでなく、登録外端末からの不正アクセスを防ぐことで、ブルートフォース攻撃によるリスクの軽減にもつなげることが可能になります。
AssetViewは、管理端末の一元管理とアクセス制御を強化し、企業の情報資産を守る頼れるパートナーといえるでしょう。
まとめ|「総当たり攻撃」は、今こそ基礎対策の徹底がカギ
ブルートフォース攻撃は、決して特殊な技術が必要なサイバー攻撃ではありません。むしろ、手法は単純で、誰でもツールさえ使えば実行できてしまうという現実があります。
その一方で、被害は深刻です。個人情報や業務データの流出、Webサービスの乗っ取り、企業の信用失墜といったリスクは、事業の継続性に直結しかねません。
「知っていれば防げたはずの攻撃」を見逃さないためにも、まずは自社や自分の環境を見直し、できるところから対策を講じていきましょう。それが、目に見えにくい脅威から大切な情報と信頼を守る、最も堅実な一歩です。






































