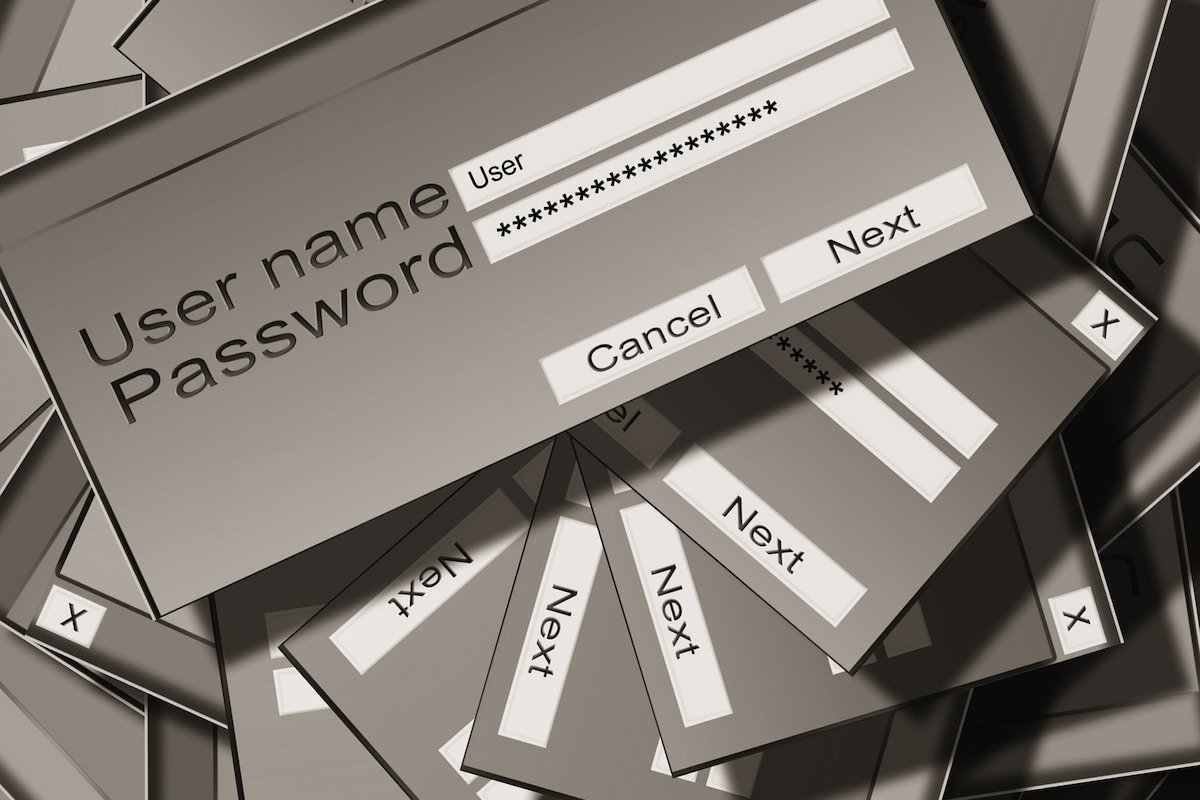スミッシングとは?SMSを悪用したフィッシング詐欺の仕組みと対策方法
- INDEX
-

スミッシング(SMSフィッシング)は、スマートフォンをターゲットにした新しい形の詐欺手法として、近年急速に広がりを見せています。悪質な攻撃者は、SMSメッセージを使ってユーザーに偽のリンクや悪質なアプリを開かせ、個人情報や金融データを不正に取得します。
本記事では、スミッシングの仕組み、被害事例、そしてその対策方法について詳しく解説します。日々進化するこのサイバー脅威から身を守るためには、どのような方法を取るべきか、一緒に考えていきましょう。
スミッシングとは何か
定義と概要
スミッシングとはSMS phishing(SMSとフィッシング)の混成語であり、英語ではSmishingと表記されます。一般的なメールアドレスへのフィッシング詐欺がフィッシングメールと呼ばれることに対して、SMSを利用するフィッシング詐欺を特にスミッシングと呼びます。
通常、「ご予約の確認」「金融情報の確認」などとメッセージに見せかけた信頼できる表現を用いて、リンクやファイルを開かせることが目的です。これにより個人情報や金融情報が搾取され、不正利用に繋がります。
フィッシングとの違い
スミッシングはフィッシングの一種ですが、「メール」ではなく「SMS」を使用する点が特徴です。SMSはメールと比べて通知として信頼されやすいため、誘導につられてしますリスクが高まります。スミッシングの背景と近年のトレンド
スマートフォンの普及と通信手段の多様化により、SMSを使ったスミッシングは日々進化しています。最近は、AIや自動化ツールを使った高度化した攻撃も増えており、個人だけでなく組織が大きな被害を受ける例も見られます。スミッシングの仕組み
悪意のあるSMSの送信方法
スミッシングは、大量の不正SMSをターゲットに送信することから始まります。これには、自動化されたSMS送信ツールが利用され、受信者の注意を引くような「それらしい」件名や内容が工夫されています。たとえば、「お支払いの確認が必要です」「荷物が届いていません」など、緊急性を装った文面が一般的です。攻撃者が狙うターゲットと目的
スミッシング攻撃のターゲットは、一般消費者から企業やその従業員にまで及びます。主な目的は以下の通りです。使用される典型的な手口
スミッシングは携帯番号宛にメッセージを届けることが可能なSMS(ショートメッセージサービス)を悪用するフィッシング詐欺であり、フィッシングメールやフィッシングサイトと同様の手口・手法が用いられます。その代表的な手口は以下の通りです。スミッシングによる被害事例
金融情報の盗難
スミッシングの代表的な被害の一つが、金融情報の盗難です。攻撃者は「クレジットカードが不正利用されています」「大至急! 口座確認が必要です」など、緊急性を装ったメッセージを送信し、受信者の判断力を失わせ、不正なリンクへ誘導します。
リンク先では、クレジットカード番号や銀行口座の情報、パスワードを入力させる偽のフォームが用意されています。入力された情報は即座に攻撃者の手に渡り、クレジットカードの不正使用や銀行口座からの不正な引き出しが行われます。
さらに、これらの情報がダークウェブで売買されることにより、被害の拡大につながります。個人の経済的損失だけでなく、金融機関やカード会社にも多大な負担を与える深刻な問題です。
個人情報の悪用
スミッシングの被害は、金融情報にとどまらず、名前や住所、電話番号、メールアドレスといった個人情報にも及びます。これらの情報を盗まれることで、以下のように悪用される恐れがあります。社内データ漏洩のリスク
企業内の従業員がスミッシングの標的になるケースも増加しています。特に、社内システムにアクセスする権限を持つ従業員の情報が盗まれると、企業全体に被害が及ぶ可能性があります。例えば、従業員を装ったメールで他の社員に不正な指示を送り、会社の資金や機密データが外部に流出することがあります。また、盗まれた情報を足がかりに、社内ネットワークに侵入してランサムウェアを仕掛けるケースも見られます。
これにより、企業の信頼性が失われ、法的責任や多額の復旧費用が発生するリスクがあります。
スミッシング詐欺が狙う盲点
近年、スミッシング詐欺の手口が巧妙化しており、多くの人がその危険性に気づかないまま被害に遭っています。その理由の一つに、スミッシング詐欺が携帯電話番号を利用する点があります。これがどのようなリスクをもたらすのか、具体的に見ていきましょう。SMSの特性を悪用した高い被害リスク
スミッシング詐欺では、直接携帯電話番号宛にメッセージが届くため、メールやSNSのダイレクトメッセージと比べて、ユーザーがメッセージを開いたり、添付されたURLをタップしたりしてしまうリスクが高くなります。
特に、普段から迷惑メールやフィッシングメールに注意している人でも、「携帯電話番号を教えた相手は信頼できるサービスや知人である」という思い込みが油断を生むことがあります。この油断が、スミッシング詐欺の攻撃者が付け入る隙になります。
巧妙な文面による心理的な誘導
スミッシングメッセージの文面には、「至急対応が必要です」「放置すると被害が拡大します」など、受信者を焦らせる表現が多く見られます。このような緊急性を装った内容は、冷静な判断を妨げ、リンクをクリックさせる心理的なトリックです。特に、「本人確認のため」「不正利用の疑いがあります」など、重要事項に関連する文言は、多くの人にとって無視しにくいものであり、詐欺メッセージの開封率を高める原因となっています。
SMS送信の背後に潜むリスク
スミッシングメッセージを受信した時点で、攻撃者は次のいずれかの方法で携帯電話番号を取得している可能性があります。
スミッシングによる被害を防ぐための具体的な対策方法
スミッシング詐欺の巧妙化に伴い、個人が被害を防ぐための具体的な対策を講じることが求められています。以下では、スミッシング被害を防ぐための実践的な方法を解説します。怪しいSMSを見極めるポイント
スミッシング被害を防ぐ第一歩は、怪しいSMSを見分ける力を身につけることです。具体的には、以下のポイントに注意してください。リンクをクリックする際の注意点
スミッシング詐欺の大きな目的は、不正なリンクをクリックさせることです。これを防ぐためには、次の点を徹底しましょう。会社やサービスの公式ページで確認する
スミッシングは企業や組織、サービス名を装ってメッセージを作成します。URLも公式のURLに似せて偽装されている場合があります。そのため、安易にURLをタップせず、以下の手順で慎重に確認することが重要です。また、送信元が知り合い、友人、家族、同僚の携帯電話番号だった場合も油断は禁物です。不審な内容や金銭に関わる事柄が記載されている場合は、別の連絡手段で本人に確認するようにしてください。これにより、不必要な被害を未然に防ぐことができます。
組織におけるスミッシング対策の重要性
スミッシングの脅威は個人だけでなく、企業や組織にとっても深刻なリスクを伴います。特に社員が標的となった場合、企業の機密情報や財務情報が危険にさらされる可能性があります。ここでは、組織全体で取り組むべき具体的な対策を紹介します。社内教育と啓発活動
社内教育と啓発活動を実施し、従業員一人ひとりがスミッシングのリスクを正しく理解し、適切に対応できるようにすることが重要です。ポリシーとインシデント対応プロセスの整備
企業が一貫したセキュリティ対策を講じるためには、以下のようなポリシーとプロセスを整備することが欠かせません。セキュリティツール導入の推奨
スミッシング対策として、最新のセキュリティツールを導入することも有効です。個々に判断させず、セキュリティや情報システム部に報告させる流れを構築する
組織としてのスミッシング対策として効果的なのは、SMSが届いた本人にその後の行動について判断を下させないようにすることです。不審なメッセージが届いた場合、リンクを開くなどの行動を起こす前に、まずはセキュリティ担当者や情報システム部に報告する流れを構築しておきましょう。
スミッシングは冷静に対処すれば怖いものではありません。URLをタップしないこと、SMSに返信しないこと、基本的にはこのふたつを守れば大丈夫です。慌てさせたり、不安にさせたりするようなメッセージが届いた時点で、まずは担当の部署に相談するものと社内ルールを決めておくとよいでしょう。
スミッシングだけでなく、フィッシングやその他の悪意ある攻撃にも備える
スミッシングに限らず、サイバー攻撃全般に対して警戒することが重要です。一つの攻撃手段にのみ注力するのではなく、サイバー攻撃の多様性を理解し、他の手口にも注意を払うことが求められます。たとえば、スミッシングに対しては十分に注意していたものの、フィッシング詐欺に引っかかってしまうという事態が起こらないようにすることが大切です。
セキュリティ対策も同様に、幅広い範囲をカバーした統合的な管理が必要です。組織としては、強固なセキュリティ基盤を構築し、日々運用することが不可欠です。また、従業員一人ひとりがサイバー攻撃の脅威やリスクについての知識を持ち、それを共有することが、企業全体のセキュリティ強化につながります。特に、従業員のセキュリティ意識の向上は、最も効果的な防御手段となることを認識しておきましょう。
スミッシングの被害に遭った場合の対応
スミッシング被害に遭った場合、迅速かつ冷静な対応が必要です。スミッシングとは、SMSを使って偽のメッセージを送信し、個人情報や金融情報を盗み取る詐欺行為です。万が一、スミッシングに引っかかってしまった場合、パニックにならず、被害を最小限に抑えるために、適切な初動対応をとることが求められます。スミッシング被害時の初動対応
冷静になる
最初に行うべきことは冷静さを保つことです。慌てて行動することで、さらに状況を悪化させる可能性があります。スミッシングメッセージを受け取った場合、まずはURLをクリックせず、SMSの返信もしないようにしましょう。携帯電話の設定確認
不審なリンクをタップしてしまった場合、悪意のあるサイトにアクセスした可能性があります。その場合、携帯電話の設定を確認し、不審なアプリケーションや設定が変更されていないかチェックしましょう。不審なアプリがインストールされていた場合は、すぐにアンインストールします。パスワード変更
個人情報や金融情報が盗まれた可能性がある場合、関連するアカウント(銀行口座、メール、SNSなど)のパスワードをすぐに変更することが重要です。可能であれば、二段階認証を有効にし、アカウントをさらに保護しましょう。必要な情報の記録と報告
スミッシング被害を受けた場合は、何よりもまず事実関係を記録しておくことが大切です。以下の情報を確実に記録しましょう。メッセージ内容
受け取ったSMSの内容をスクリーンショットで保存します。URLや送信者の電話番号、メッセージの内容が証拠となります。アクセスしたサイトのURL
不審なリンクをタップしてしまった場合、そのサイトのURLも記録しておきましょう。これにより、後でサイトが悪質なものであることが証明できます。行動の詳細
メッセージを受け取った日時や、その後どのような対応を取ったかをメモとして残しておきます。これらの情報は、後に被害の詳細を伝える際に役立ちます。被害を発見した場合、速やかに関係者へ報告します。特に企業の場合、情報システム部門やセキュリティ担当者に状況を報告し、会社のセキュリティ対策を強化するための対応を協議します。
関係機関への相談と復旧方法
警察や消費者センターへの相談
スミッシング被害に遭った場合、警察や消費者センターへの相談が必要です。警察に相談することで、被害の捜査が始まり、同様の被害が拡大することを防げます。また、消費者センターでは、被害の内容を報告し、適切なアドバイスを受けることができます。金融機関への報告
銀行口座やクレジットカード情報が盗まれた場合、直ちに金融機関に連絡し、カードの停止や口座の凍結を依頼しましょう。また、不正取引があった場合は、その調査を依頼し、適切な返金措置を講じてもらいます。セキュリティソフトの使用と再発防止策
スマートフォンやPCには、セキュリティソフトを導入し、ウイルスやマルウェアをスキャンすることが重要です。これにより、悪意のあるソフトウェアがインストールされていないか確認できます。また、定期的なセキュリティアップデートを行い、ウイルスや不正アクセスからの保護を強化します。復旧手続きとフォローアップ
事後対応として、必要な復旧手続きを行います。パスワード変更、アカウントの復元手続き、金融機関への連絡が終わった後も、引き続き被害の進展を監視し、セキュリティを強化するための行動を続けることが大切です。例えば、メールのスパムフィルター設定や、セキュリティ意識の向上のための社内研修などを実施することも有効です。まとめ:スミッシングを含む外部からの脅威やリスクにシステムで対応する
今回の記事では、スミッシングに関する基本的な知識と、スミッシングによる被害を防ぐための具体的な対策方法について解説しました。
スミッシングをはじめとする、人々の心理を悪用した詐欺的なサイバー攻撃は、常に進化し、身近に存在しています。これらのリスクを未然に防ぐためには、サイバー攻撃に関する知識やナレッジを組織内で共有しておくことだけでなく、システム的なセキュリティ対策が非常に重要です。
当社が提供するIT資産管理ツール「AssetView」シリーズを活用すれば、統合的なセキュリティ管理が可能となり、外部からの脅威やリスク全般に対応しやすくなります。システム全体のセキュリティ強化と従業員のセキュリティ意識向上を目指すのであれば、ぜひこの機会にご相談・お問い合わせください。